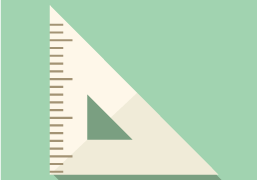 落語
落語 【小論文・表現の選択】「なので」は改まった場面や書き言葉には不向き
語彙力をつけるのは難しいです。なるべく論理的な評論を多く読むことをお勧めします。さらに意識的に使う言葉を選ぶことです。NGな表現をきちんと理解し、もし使ってしまったとしたら、すぐに消して別の表現に変えるべきです。
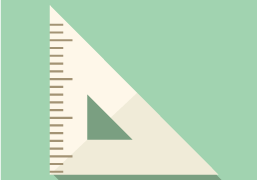 落語
落語  落語
落語  落語
落語  落語
落語  落語
落語  落語
落語  落語
落語 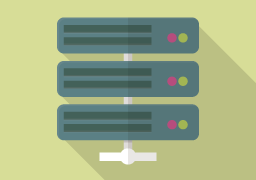 落語
落語 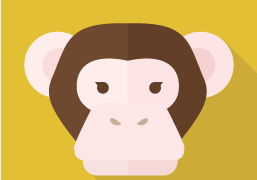 落語
落語  落語
落語 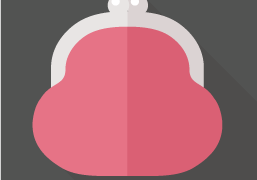 落語
落語  落語
落語 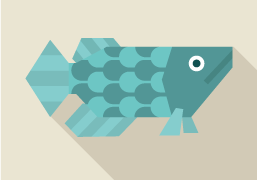 落語
落語  落語
落語 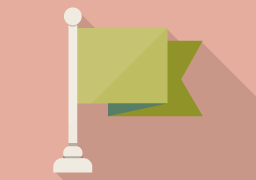 落語
落語  落語
落語