 落語
落語 【落語家・桂枝雀】緊張の緩和を常に意識して自死を選んだ上方噺の雄
桂枝雀を知っていますか。ユニークな芸風で一時代を作り上げました。亡くなってもう20年がたちます。彼の落語はいつも緊張と緩和の繰り返しでした。ドラマツルギーを完全に掌握していたのです。それだけに孤独感も強かったのでしょう。59年の生涯でした。
 落語
落語 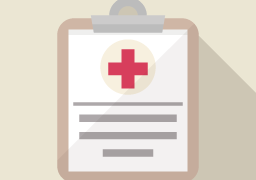 落語
落語  落語
落語 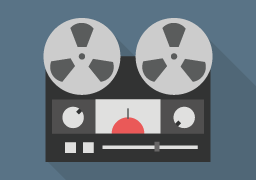 落語
落語  落語
落語  落語
落語  落語
落語 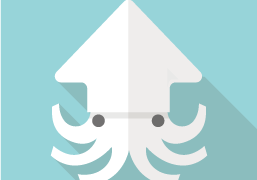 落語
落語  落語
落語 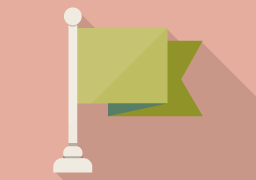 落語
落語  落語
落語  落語
落語 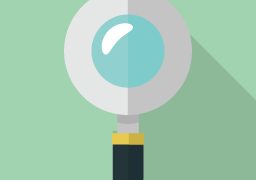 落語
落語  落語
落語 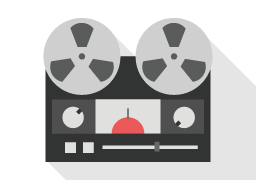 落語
落語 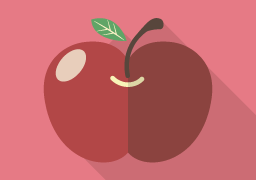 落語
落語