 本
本 【漢文・世説新語】人生の達観した生き方を一兵卒から学ぶ【身の丈】
『世説新語』という本をご存知ですか。高校の漢文の授業でも習います。今回はその中でもよく取り上げられるある兵士の話です。命を狙われている人を助けるために、お酒を飲み、酔っ払ったフリをして、わざとここにお尋ね者がいると叫んだのです。その結末は。
 本
本 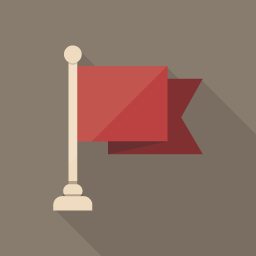 本
本 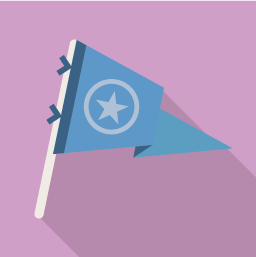 本
本  本
本  本
本  本
本 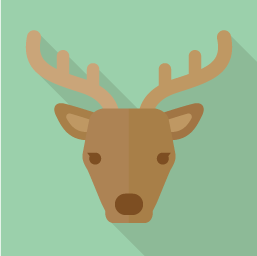 本
本  本
本  本
本  本
本 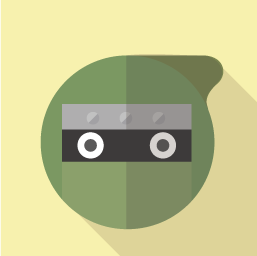 本
本  本
本 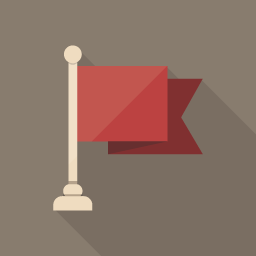 本
本  本
本 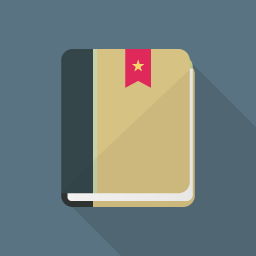 本
本  本
本