若き日の恋
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は阿仏尼の日記を読みましょう。
『十六夜日記』で有名な彼女がまだ若かった頃の日記です。
『うたたね』という書名がそれです。
ある高貴な青年と激しく燃えた初恋の思い出を、憂愁の中で綴りました。
失恋の思い出が容易に消えなかったことがよくわかります。
失恋の痛手から立ち直れない彼女に、上京してきた養父が遠江に来るように誘ったのです。
かつて遠江国(とおとうみ)と呼ばれたのは、現在の静岡県西部に当たる地域の呼称です。
しばらく田舎暮らしをすれば、気持ちが少しは柔らぐだろうと考えたに違いありません。
彼女自身もつらい思いを忘れられるかもしれないと、都を離れることにしました。
しかし、逢坂山の関の清水を見ると、自身の涙に思えてならなかったのです。
逢坂山(おうさかやま)は、滋賀県大津市の西側に位置する標高300mほどの山です。
この作品の成立は、鎌倉時代中期の1240年頃といわれています。

阿仏尼は安嘉門院に仕え、出仕中10代で失恋したことから出家を決意し尼になりました。
しかしその後も世俗との関わりを持ち続けたのです。
30歳頃、藤原為家の側室となり、冷泉為相をうんだことがわかっています。
出家して尼になった後、僧であることを捨て、再び現世に還俗(げんぞく)したのです。
当時から現在に至るまで、それほど多くはないケースだと思われます。
これはあくまでも憶測ですが、10代の若さで出家してしまった阿仏尼に、
なぜ養父が旅を勧めたのかという背景とも関係がありそうです。
いっそのこと、旅に出て全てをなかったとことにできないかと考えたのかもしれません。
還俗するチャンスをうかがったとも想像できるのです
本文
嘆きながら、はかなく過ぎて、秋にもなりぬ。
長き思ひの夜もすがら、やむともなき砧の音、寝屋近ききりぎりすの声の乱れも、ひとかたならぬ寝覚めのもよほしなれば、
壁にそむけるともし火の影ばかりを友として、明くるを待つもしづ心なく、尽きせぬ涙のしづくは窓打つ雨よりもなり。
いとせめてわび果つる慰みに、誘ふ水だにあらばと、朝夕の言草なりぬるを、そのころ後の親とかの、頼むべきことわりも浅からぬ人しも、
遠江とかや、聞くもはるけき道をわけて、都の物詣せむとて上り来たるに、何となくこまやかなる物語などするついでに、
「かくてつくづくとおはせむよりは、田舎の住まひも見つつ慰み給へかし。
かしこももの騒がしくもあらず。
心澄まさむ人は見ぬべきさまなる」など、なほざりなくいざなへど、さすがひたみちにふり離れなむ都の名残も、いづくをしのぶ心にか、心細く思ひわづらはるれど、あらぬ住まひに身を変へたると思ひなしてとだに、憂きを忘るるたよりもやと、あやなく思ひ立ちぬ。
下るべき日にもなりぬ。
夜深く都を出なむとするに、ころは神無月の廿日あまりなれば、有明の光もいと心細く、風の音もすさまじく、身にしみとほる心地するに、

人はみな起き騒げど、人しれずこころばかりには、さてもいかにさすらふる身の行方にかと、ただ今になりては心細きことのみ多かれど、
さりとて留まるべきにもあらねば、出でぬるみちすがら、先ずかきくらす涙のみ先きに立ちて、心細く悲しきことぞ、なににたとふべしとも覚えぬ。
ほどなく、逢坂山になりぬ。
おとに聞し関の清水も、絶えぬ涙とのみ思ひなされて、
越えわぶる逢坂山の山水はわかれに堪へぬ涙とぞみる
現代語訳
嘆いているうちに、むなしく時が過ぎ秋になってしまいました。
長いもの思いの一晩中、やむこともない砧の音や、寝所に近いところで聞こえるこおろぎの声の乱れも一通りではなく寝覚めを誘うものなので、
壁に背を向けてともした火の光だけを友として、夜があけるのを待つのも落ち着いた気持ちではなく、尽きない涙のしずくは窓をうつ雨よりも多いほどなのです。
ひどく思いつめてしまった心のなぐさみにもなるかと、
「誰かが誘ってさえくれるならどこへでも行こう」と朝な夕なに口癖に言っているのを、そのころ養父として頼りにするべきいわれも浅くない人(平度繁)がちょうど、
遠江とか、聞くだけでも遙かな道を分けて、
「物詣でをしよう」と上洛して来たので、何となくこまごまと話をするついでに、養父が私に「このようにぼんやりと沈んでいらっしゃるよりは、田舎(遠江)の暮らしもしてみてこころをお慰めなさい。あちらはわずらわしいこともありません。
心を落ち着けようという人には住みよいところですよ。」などと、いいかげんでなく
誘ってくださるけれど、さすがにひたすら住み慣れた都をふり捨てて行くのも名残惜しく、
捨てられた私が何を偲ぶ心でもないのに、心ぼそく思い迷っていましたが、
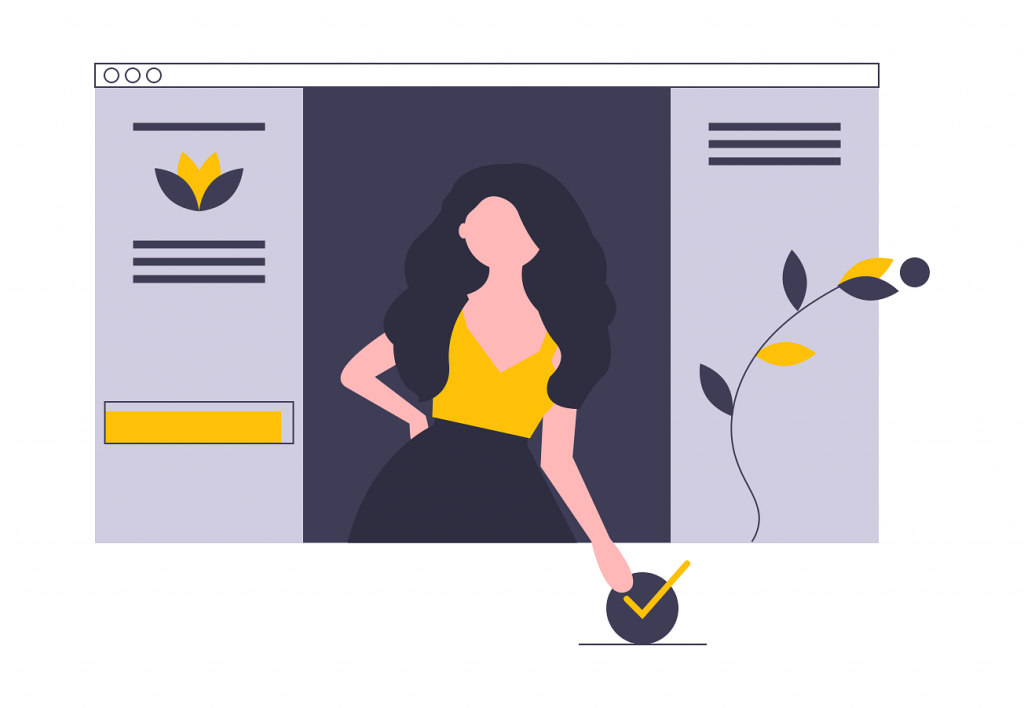
「今までとは違った住まいで出家した」と思ってみさえすれば、この憂いを忘れるきっかけにもなるかなと遠江に下ることをと深いわけもなく思い立ちました。
とうとう下る予定の日になったのです。
夜遅く都を出ようとしたところ、10月の20日過ぎだったので、有明の月の光もひどく心細く、風の音も怖ろしいほどで、身に沁みとおる気がするところ、
みな起きて騒いでいるのが、人知れず、私の内心では、それにしてもさすらう我が身の行方であろうかと嘆きました。
今となっては心細いことばかり多いけれど、だからといって都にとどまるわけにもいかないので、出ていった道の途中も、まず目の前を暗くする涙ばかりが先に立って心細く悲しいことは、何にたとえることができるとも思えません。
しばらくして、逢坂山に至りました。
うわさに聞いた関の清水も尽きせぬ涙とばかりに感じられて
越えるのに苦労する逢坂山の関の清水は、別れに耐えられないで流す涙にみえたのでした。
逢坂山の関の清水
『うたたね』のあらすじが理解できたでしょうか
簡潔にまとめると次のようになります。
主人公の彼女が日々嘆いているうちに、時は容赦なく過ぎていきます。
やがて秋になってしまいました。
それでも涙はなかなか尽きることがありません。
そんな折もおり、養父が上京してきます。
しきりに田舎へ行こうと誘うのです。
もの思いに沈んでいると身体に触るから、田舎で心を慰めればいいと言います。
気持ちは少し傾くものの、都を去るのはやはり心細いものでした。
しかし今までと違う環境で過ごせば、少しはつらい思いも忘れられるかもしれないと彼女は思います。

結局、夜遅く遠江へ旅立つことにしました。
旅には最も不向きな冬の夜だったことも想像してみてください。
我が身の行く末がどうなるかと思うと、心細くて仕方がなかったでしょう。
しかしだからといって、とどまるわけにもいかないのです。
自身を薄命の佳人になぞらえたり、盛りを過ぎた悲哀を詠んだ小野小町の名歌を引いたりして、わが身を嘆きます。
白居易の歌や、楊貴妃と玄宗の恋も思い出されました。
夢の中に恋人をみたいという一人寝のさびしい心境をうたった、新古今和歌集の歌も踏まえて文章を書いています。
床近しあなかま夜半のきりぎりす夢にも人の見えもこそすれ、がそれです。
このあたりは歌人だけに、かなりの思い入れがあったことでしょう。
しかし若書きのため、まだ十分に咀嚼されていない印象が残ります。
最後に見た逢坂山の関の清水をみた時にできたという歌は、その時の彼女の本当の気持ちだったのでしょうね。
失恋の痛手から立ち直れない様子がみてとれます。
これ以降、阿仏尼次は々と作品を発表していきます。
文章を書くことで、心を穏やかにしたいと願ったのに違いありません。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


