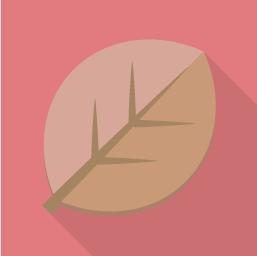 本
本 【美を求める心・小林秀雄】美しさがわかるとはどういう意味なのか
小林秀雄の評論はどれも難解です。けっして難しい言葉を使っているワケではありません。しかしその内容は実に深みがあり、含蓄に富んでいます。美しいとはどういうことなのか。それをじっくりと考えてみた文章です。味わってみてください。
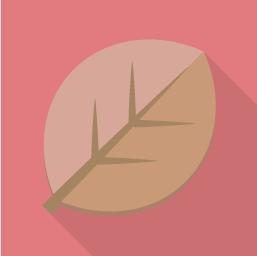 本
本 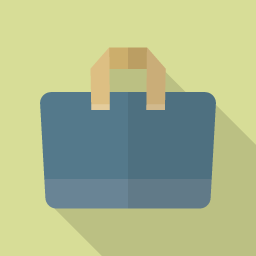 本
本  本
本  本
本  本
本 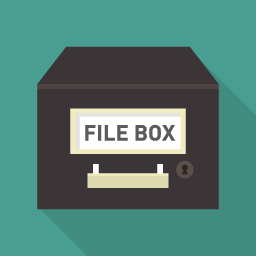 本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本 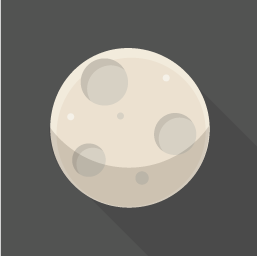 本
本  本
本 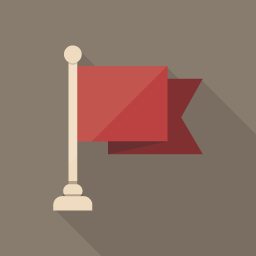 本
本  本
本