風の歌を聴け
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は村上春樹の処女作『風の歌を聴け』を取り上げます。
本当に久しぶりに読み直しました。
この小説は1979年4月の群像新人文学賞受賞作品です。
タイトルは、トルーマン・カポーティの短編小説「最後のドアを閉じろ」の最後の一行からとられています。
当時の村上春樹は29歳です。
はじめて小説を書いた作品が、これなのです。
同じ年齢の「僕」が、1970年8月8日から8月26日までの18日間の物語をまとめたという体裁になっています。
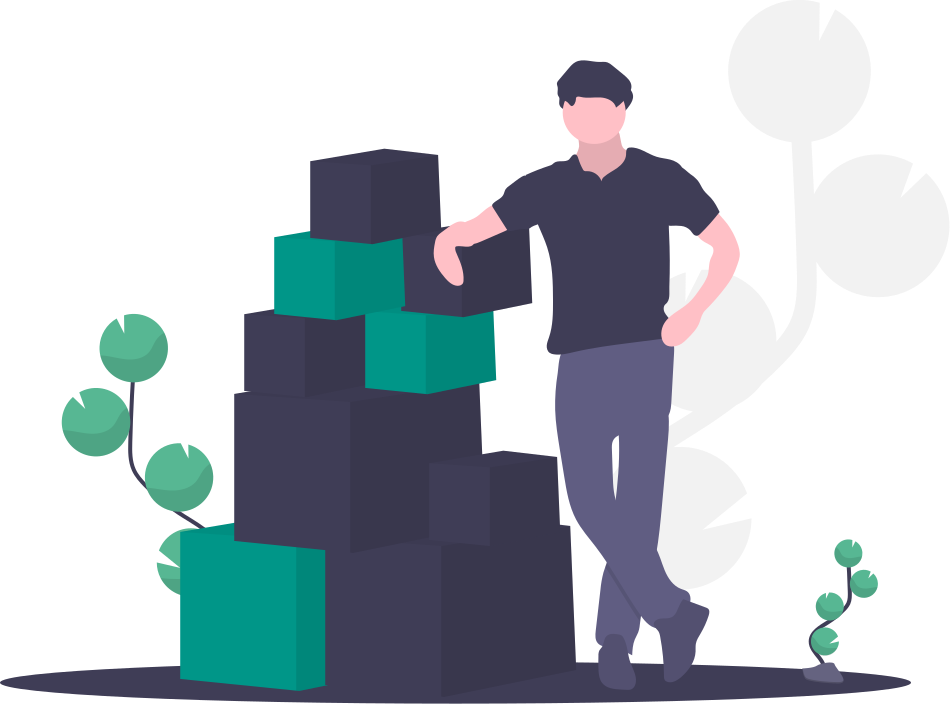
ストーリーがあるのかといえば、ないこともないということでしょう。
断章を集めたものともいえます。
最初にいくつかのチャプターに分けて書き、それを後でシャッフルしたという話は有名です。
全体は40の断章から出来上がっています。
書き出しは有名な次の言葉から始まります。
完璧な文章などといったものは存在しない。
完璧な絶望が存在しないようにね。
他者と繋がることがいかに難しいのかということを、彼独自の表現で描いています。
本当に書きたかったのはチャプター1の冒頭の文章だけだったと村上春樹は語っています。
あとは自分の世界を次々とパッチワークのように紡ぎあげていったというのが真実なのではないでしょうか。
小説の原点
東京の大学生だった1970年の夏が舞台です。
僕は港のある街に帰省し、一夏中かけて「ジェイズ・バー」で友人の「鼠」と日々を過ごします。
たまたま洗面所に倒れていた女性を介抱し、家まで送りました。
この部分から女性の部屋の記述は、いかにも村上の世界です。
彼のフィルターにかかると、不必要なものは全て捨象され、そこに存在しなくなります。
自分の横に眠る女性の裸体の表現も、一種の記号と化してしまうのです。
作家はそれぞれの持つ現実を言葉に託して表現します。
その際、村上春樹はすべてをオブラートでくるみ、自分の目的とする事象だけにスポットをあてます。
読者に他のものは見せないのです。
どんなに乱雑な部屋であっても、彼の視野には見えません。

たとえ見えていたとしても、それは表現されないのです。
読者を村上ワールドに引きずりこむ装置は、音楽と酒です。
その甘い響きを聞きながら、ほろ酔い気分になっていく間に、世界の全てが自分のものになります。
それ以外のものは消えてなくなるのです。
そこに愚かな人間は登場しません。
貧しくてもも豊かでも、それは同じラインの上に乗っています。
事実、鼠と呼ばれる友人は大変な財産家の子息です。
一方、4本指の女性は貧しい家で苦労して育っています。
しかしそれが小説の中に入った途端、同じ線の上を歩き始めるのです。
いくら裕福であっても、鼠は幸福ではありません。
それが痛いくらいにわかります。
レコード店員の女性はさまざまな過去を持ちながら、それを公にしようとすることもありません。
僕に少しだけ告白した後も、態度にこれといった変化はないのです。
これが村上春樹の小説の原点です。
全ての登場人物がパラレルな線の上をひたすら歩きます。
死すべき命
それを一言でいえば、まさに死すべき命をもった人間の運命とでも呼ぶしかないものです。
女性はいいます。
死んで100年もすれば、だれも私のことを知っている日はいなくなるのね。
そこに全ての人間が持っている現実があります。
末期の眼からみれば、現在がいかに危ういものかがはっきりと見えるでしょう。
しばらくしてたまたま入ったレコード屋で、ぼくは店員の彼女に再会します。
鼠はある女性のことで悩んでいるようですが、僕にも相談しようとはしません。
彼女と僕は港の近くにあるレストランで食事をします。
その後、夕暮れの中を倉庫街に沿って歩きました。
彼女は中絶したばかりであることを僕に告げます。
ここでこの女性が抱えている現実が少しだけ明かされます。
しかしだからといってそこから先に解決があるワケではありません。
再び街に帰ったとき、彼女はレコード屋を辞め、アパートも引き払っていました。

それだけの話です。
それから何も起こらない。
これが本当の意味での現実なのかもしれません。
風の歌はどこにあるのか。
それを聴く意思もなければ、聴きたいとも思わない。
現在の僕は結婚し、東京で暮らしています。
鼠はその後、どうしても小説を書き続けるといって引きこもったままです。
毎年クリスマスの頃に彼の小説のコピーが送られてきます。
しかし鼠がどこへ向かうのかは誰にもわかりません。
作品の舞台
中国人が経営しているジェイズ・バーがこの作品の主要な舞台です。
ここで酒を飲み、女性と出会い、そして別れていきます。
今までに僕が知り合った女性の話も1つの話題に過ぎません。
1人目は、高校のクラスメイト。
2人目は、地下鉄の新宿駅で出会った16歳のヒッピー。
3人目の女の子は、大学の図書館で知り合った仏文科の学生です。
しかし彼女は翌年の春休みに林で首を吊って自殺してしまいます。
彼らとの出会いと別れも、1枚の絵を次々と見せられているような感覚だけが残ります。
結局はそれも風景の1部です。
だから自分が変化したということもありません。
つねに外部の心象として、そこに存在したということなのでしょう。
では僕にとっての真実とは何だったのか。
それはわざわざアメリカへ行き、彼の墓まで訪ねたという作家の存在です。
もちろん、これは架空の話でしかありません。
その人の名はデレク・ハートフィールド。

アメリカの作家です。
宇宙人や化け物の登場する小説を多く執筆し、のちに投身自殺します。
彼の文章に多くを学んだとありますが、もちろんこれもフィクションです。
いくつかの作品名まで作り上げて、小説を登場させた意図は何なのか。
それを考えてみるのも楽しいかもしれません。
全体を読み直して感じるのはこの作家の孤独の深さです。
誰にも理解されずに、生きていく人間の横顔だけが強烈でした。
ぼく自身、村上春樹の作品はほぼ読んでいます。
まさに作家は処女作に向かって遡っていく存在なのかもしれません。
それが作家の業なのだといえば、それまでのことです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


