字のない葉書
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は向田邦子の作品を読みます。
このエッセイは中学2年生用の国語教科書に載っています。
実に短い作品です。
しかし読み終わると、心の中にあたたかなものがひろがるのを感じます。
まさに昔の父親の姿です。
余計なことは何も言わない。
寡黙な人間です。
しかし子供に対する愛情は人一倍深いのです。
それが短い文章を通して感じられます。
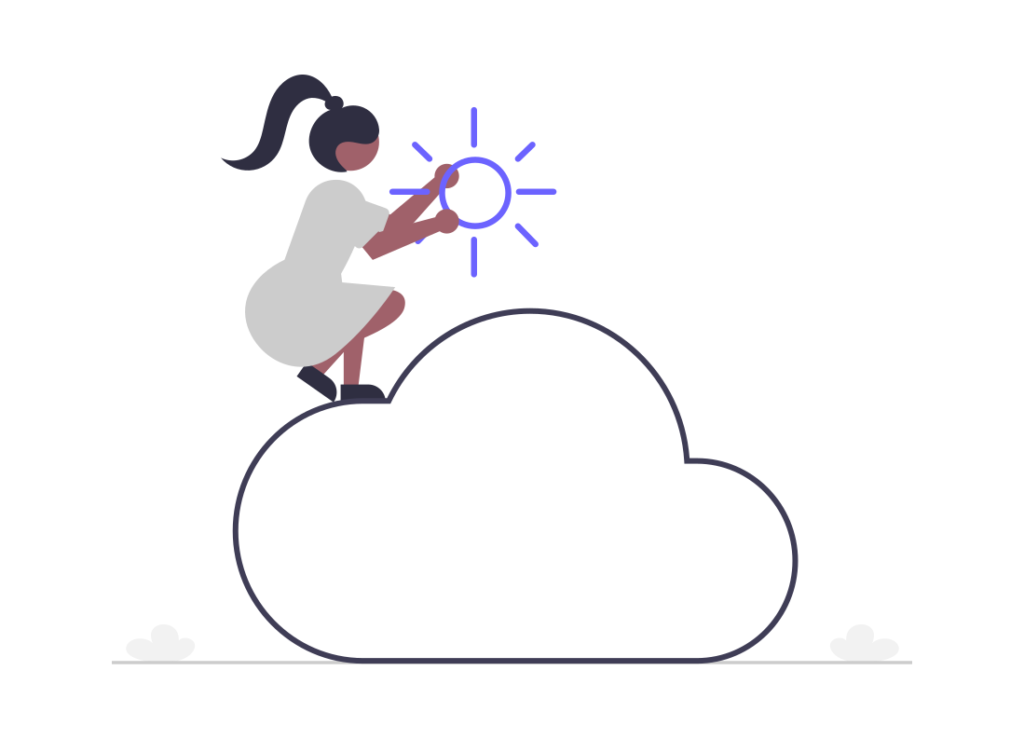
テレビの脚本家から直木賞作家への転身も見事でした。
向田邦子のブームが一気に起こったのです。
作品はどれも読みやすいものです。
読後感は深い人間味に溢れていました。
しかし亡くなり方があまりにも唐突だったのです。
飛行機事故でした。
1981年(昭和56年)8月です。
台湾への取材旅行中、突然飛行機が墜落したのです。
51歳の若さでした。
仕事への意欲が充実しきった絶頂の時でした。
それ以後、彼女の特集号が次々と出版されました。
ぼくも「クロワッサン」の別冊を大切に持っています。
テレビでの活躍
いずれも伝説の作品ばかりです。
テレビドラマの研究をしている人ならば、向田邦子に触れないワケにはいきません。
代表的な作品が確実に1つの時代を作りました。
『時間ですよ』『だいこんの花』『寺内貫太郎一家』などを御存知ですか。
この頃からエッセイも書き始めていました。
『父の詫び状』は今でもロングセラーとして人気があります。
『冬の運動会』『阿修羅のごとく』も人気がありました。
昭和の父親の横顔を書かせたら、この人の右に出る人はいませんでした。

森繁久彌、佐分利信、小林亞聖などがそれぞれの父親役を好演したのです。
そこには彼女の父親の姿が反映していると言われています。
無口で頑固、それでいて子供に対する愛情は人並以上という、ある意味厄介な人物像です。
彼女の実父もまさにそうだったのです。
『阿修羅のごとく』はNHKの和田勉がプロデュースした伝説の番組です。
父親の女性関係をめぐって、家が次第に崩壊していくという今日の世相を彷彿とさせる内容でした。
時代の背景をしっかりと見据えながら、人間の持つ弱さをありのままに見据えたところに向田邦子の真骨頂があったのでしょう。
その全体像を中学生に実感させるのは元来、無理があります。
しかしこのエッセイの中にこめられた、戦時中の疎開生活がもっていた非情さを、感じとることはできると思います。
彼女が事故にあわなければ、多くのすぐれた作品がさらに生まれたに違いありません。
あらすじ
「私」が女学校1年となり親元を離れると、父はたびたび手紙をよこすようになります。
父は、「おい、邦子」といつも呼び捨てにしていました。
ところが届いた手紙の表書きには「向田邦子殿」と几帳面な筆で書かれていたのです。
折目正しい時候の挨拶などもあり、「貴女」という敬称で呼ばれます。
他人行儀な手紙の裏側には、威厳と愛情にあふれた父がいました。
ここで心に残るものとして紹介されているのが「字のない葉書」です。
終戦の年、下の妹が甲府へ学童疎開することになりました。
母は肌着を縫い、父はたくさんの葉書を用意します。
「元気な日はマルを書いて、毎日一枚ずつポストに入れろ」というのが約束でした。

父は自分の宛名だけをそこに書いたのです。
妹は、まだ字が書けませんでした。
最初は大きな赤マルだったのです。
しかしそれが小さな黒マルになり、さらにバツに変わるようになりました。
やがてその葉書も来なくなります。
母が迎えに行くと、妹は百日咳をわずらいしらみだらけの頭で狭い部屋に寝かされていたのです。
帰ってくる妹を喜ばせようと、私と弟は家庭菜園のかぼちゃを全て収穫します。
小さいのをもぎとると普段は叱る父も、その時は何も言いませんでした。
妹が帰った日、父は裸足で家を飛び出します。
痩せた娘の肩を抱き、大声を上げて泣いたのです。
大人の男が声を立てて泣くのを私は初めて見ます。
それから30年が過ぎ、父は亡くなり妹が当時の父と同じ年齢になりました。
あれ以来、字のない葉書を1度も見ていません。
つらい思い出
けっして明るい話ではありません。
東京にいてはいつ空襲があるかわからないという極限状況です。
学童疎開と呼ばれ、東京の子供たちは地方の安全な場所へ避難せざるを得ませんでした。
しかし受け入れる村の人々にとってはどういう存在だったのか。
けっして歓迎されたワケではないのが、文章の端々から見て取れます。
1番の心配はやはり健康でしょう。
それを知るために文字の書けない子供のために考えた通信方法が、葉書でした。
〇か×かだけで、その日の体調を知らせろということなのです。
最初のうちは葉書からはみ出すほどの威勢のいい赤鉛筆で、マルが書いてありました。
地元の婦人会が赤飯やぼたもちをふるまって歓迎してくれたのです。
しかしそうした日は長くは続きません。
付き添った大人に見せるためのセレモニーでしかなかったのです。
客扱いが終われば、後は邪魔者です。
少し離れたところにいた上の妹が、下の妹に会いにいくと、しゃぶっていた梅干しの種を吐き出して泣いたという記述にもその時の様子が表れています。
男は泣かないというのが時代の常識でした。
それが妹が帰ってきた時の意外なほど、脆かった父の姿に反映されています。
逆に愛情の深さがそこに浮き上がって見えます。
この部分の描写は見事というしかありません。

それをじっと見ていた作者の透徹した目が、ある意味では怖いくらいです。
小さなカボチャを収穫してしまえば、そこで成長はとまります。
しかしそれでも子供に食べさせてやりたいとする親の気持ちがわかればわかるほど、心の痛みが滲み出てきます。
短編だから内容が浅いということはありません。
ほんのわずかな断面を切り取る目があれば、そこで語られる内容は豊饒なものです。
向田邦子はそれができた人なのです。
それだけに事故がなかったならばと、悔やむ気持ちが人一倍強くなります。
彼女のエッセイはちっとも古びていません。
そこに生きた人間がいるからです。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。


