一字の違ひ
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は授業でもめったに取り上げることのない『正徹物語』について解説します。
これは2巻からなる歌論書です。
つまりどの歌のどういうところがすぐれているのかといった、評論集なのです。
著者は当時の歌人で禅僧だった正徹です。
1448年ごろ成立した本だと言われています。
幽玄を重んじ、全体の文章には藤原定家への敬慕の念がみなぎっています。

正徹は和歌を冷泉為尹、今川了俊に学びました。
当時の歌壇の指導者の1人として沈滞した二条家歌風を排して、定家への復活を唱えたのです。
保守的な家の歌風が次第に時代の流れとあわなくなっていたのでしょう。
歌集には『草根集』があります。
教科書に所収されているのは、今回扱う章段だけかもしれません。
たった1つの文字にも、細やかな神経をはりめぐらすのが、歌人の生きる道です。
それをどのように実践してきたのかという文章です。
もしこの使い方だったら、どういう印象を持たれるのか。
あるいはこの表現がなければ、どういう歌に聞こえるのかといった、内容の細やかな本です。
当時の歌人たちは、こうした歌論書を読みながら、自分の歌を少しでも後世に残るものにしようとしたのでしょうね。
息が苦しくなるような、ギリギリの推敲を試みています。
たった1つの文字に歌人たちが生命をかけていたという事実が、よくわかります。
本文
為秀の、「あはれ知る友こそかたき世なりけれひとり雨聞く秋の夜すがら」の歌を聞きて、了俊は為秀の弟子になられたるなり。
「ひとり雨聞く秋の夜すがら」は、 上の句にてあるなり。
秋の夜、ひとり雨を聞きて、「あはれ知る友こそかたき世なりけれ」と思ひたるなり。
あはれ知る友のあるならば、誘はれて、いづちへも行きて、語りも明かさば、かく雨をば聞くべからず。
行かんともせぬところが殊勝におぼえはべるなり。
「ひとり雨聞く秋の夜半かな」ともあらば、果つべきが、「秋の夜すがら」と言ひ捨てて、果てざるところが肝要なり。
「ひとり雨聞く秋の夜すがら思ひたるは」といふ心を残して、「夜すがら」とは言へるなり。
されば、「ひとり雨聞く秋の夜すがら」が上の句にてあるなり。
「ひとり雨聞く」が下の句ならば、させる節もなき歌にてあるべきなり。
杜子美が詩に、「聞雨寒更尽、開門落葉深」といふ詩のあるを、我等が法眷(はつけん)の老僧のありしが、点じ直したるなり。

昔から、「雨と聞く」と点したるを見て、「この点悪し」とて、「雨を聞く」とただ一字始めて直したり。
ただ一字の違ひにて、天地別なり。
「雨と」と読みては、始めから落葉と知りたるにて、その心狭し、
「雨を」と読みつれば、夜はただまことの雨と聞きつれば、
五更すでに尽きて朝に門を開きて見れば、雨にはあらず、落葉深く砌(みぎり)に散りたり。
この時始めておどろきたるこそ面白けれ。
されば歌もただ文字ひとつにてあらぬものに聞こゆるなり。
現代語訳
為秀の「あはれ知る友こそ難き世なりけれ独り雨聞く秋の夜すがら」の歌を聞いて、
了俊は為秀の弟子になられたということに気づきました。
「独り雨聞く秋の夜すがら」という表現は、最も上位ランクのレベルの位置にあるべきなのです。
秋の夜、ひとりで雨の音を聞いて、「ものの情趣のわかる友達というのは、なかなかいない時代であるよな」と思ったのでしょう。
仮に「あはれ知る友」がいたとしましょう。
その人に誘われて、どこかへ行ったとします。
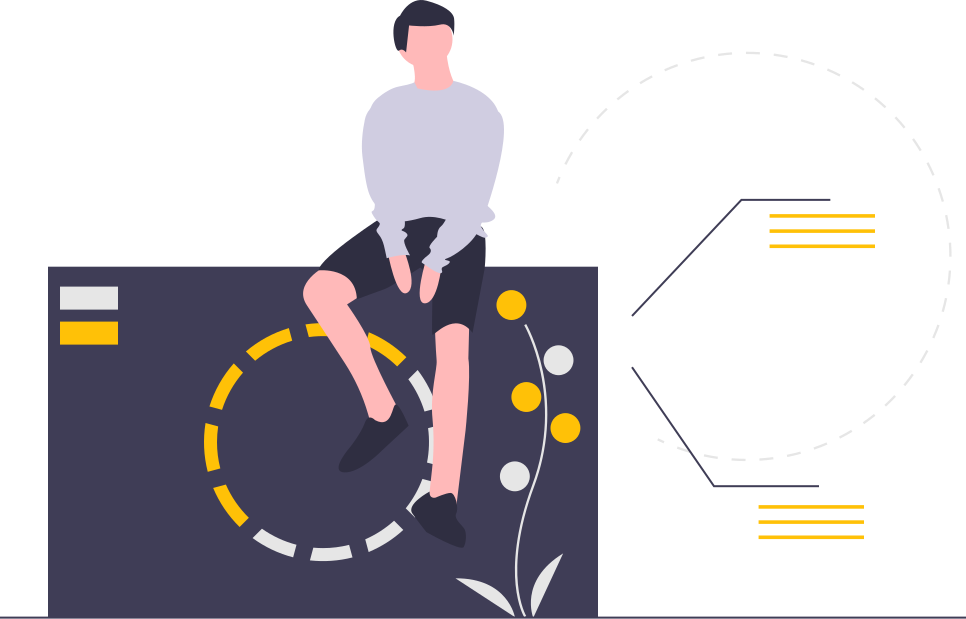
一晩中風雅な話をして夜を明かしたならば、このように雨の音が耳に残るはずはないのです。
ところが、風雅の心がある友というのがなかなかみつからないのでどうしようもない、
というところが、この歌の一番肝心なところではないでしょうか。
まさにそう思われてならないのです。
「ひとり雨聞く秋の夜半かな」とでも詠んだら、詠嘆の終助詞が効果をあげて和歌は、きちんと完結したに違いありません。
しかし「秋の夜すがら」と言いかけてやめて、わざと完結させなかったところが実は最も大切なのポイントなのです。
「ひとりで雨の音を聞いている秋の一晩中、思ったことは」という気分をどこかに残したまま、
「夜すがら」という表現を使い、ここを体言止めにして余情を残して言ったのです。
だから、「ひとり雨聞く秋の夜すがら」が最も効果的な表現になっているのです。
「ひとり雨聞く」が、もしダメな表現だとしたら、たいしておもしろみもない歌になってしまったはずです。
杜甫の漢詩に、「聞雨寒更尽、開門落葉深」というのがあります。
私と同じ宗門の老僧が、かつてこの訓読を訂正したことがありました。
昔から、「雨と聞く」と訓読しているのを見て、「この訓読は正しくない」として、「雨を聞く」とたった1字だけ初めて直したのです。
ところが、たった1字直しただけで、まったく別の内容になってしまいました。
「雨と」と訓読してしまうと、「雨だとして」という意味になり、最初から落葉の音だと知っていたことになって、趣向に広がりが感じられないのです。
「雨を」と詠むと、夜のうちはひたすら本物の雨だと思って聞いていたのに、
夜の時間が終わって朝になって門を開いてみると、雨が降った形跡はなく、落葉が深く砌(みぎり)に散っていましたとなります。
その時になってやっと、「実は雨だと思っていた音は、落葉の音だったのだ」と気づくからこそ、趣深くなるのです。
この漢詩と同じで、だから歌もただ文字ひとつ変えるだけで、全く別のものになってしまうというワケなのです。
歌のいのち
歌人とは歌のプロフェショナルのことです。
自分のつくった歌だけでなく、たくさんの名歌を分析し、推敲します。
1つの文字が持つ表現の多彩さに気づいている人達です。
「てにをは」を1文字変えただけで、確かに意味が大きく変化します。
そのバリエーションの豊かさに、見ているものをあっと言わせてきました。
「なさけ知る友こそかたき世なりけれ独り雨聞く秋の夜すがら」の歌を例にして、細かな分析を試みていますね。
わかりやすくいえば、この歌を読み感動した人が弟子になったという話です。
秋の夜、独りで雨音を聞いて、「あはれ知る友こそかたき世なりけれ」としみじみ考えているのです。
「かたき」というのは漢字で書くと「難き」です。
難しいということなのです。
なかなか情趣を解する人物に巡り合えないという現実があります。
もしも「あはれ知る友」が存在していたならば、誘い出されてどこかへ出向き、語り明かしでもすることでしょう。
しかしそんな現実は訪れそうもありません。

風雅な友がいれば、こんな風にさみしく雨音を聞いていたりはしないはずだという感慨です。
もちろん、そういう友がいたとしてもあえて出かけずにいるところも、風雅の道ではありますけどね。
「秋の夜半かな」などと簡単に句を切ってしまったのでは面白くないのです。
「秋の夜すがら」と体言で終えたところに味があると、正徹は言っています。
杜甫の漢詩では「雨と聞く」としてしまうと最初から雨の音ではないことを知っていたことになります。
それでは面白くない。
実は雨だと思っていた音は、落葉の音だったのだと気づくところに味があるのです。
歌も、漢詩の訓読も同じです。
ただ文字ひとつ変えるだけで、別のものになるというワケなのです。
歌人の鋭い感性が横溢した文章です。
①「独り雨聞く秋の夜すがら」②「独り雨聞く秋の夜半かな」③「秋の夜すがら独り雨聞く」
の違いを本文の内容に即して考えてみたりするのも面白いですね。
「雨と聞く」と「雨を聞く」の違いも理解できましたか。
歌人とは今も昔も、言葉に命をかけて身を削るように暮らしている人のことです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


