源氏物語玉の小櫛
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は本居宣長の代表的な評論『源氏物語玉の小櫛』について考えます。
この本は国学者・本居宣長による「源氏物語」の注釈書です。
全9巻からなる長大なものです。
『源氏物語』を扱った本はそれまでにもたくさんありました。
しかしこの本が刊行されて以来、『源氏物語』といえばまずこの注釈書を紐解くようになったのです。
完成したのは宣長が66歳になった1796年です。
京都での遊学を終えて、出身地の松阪に戻ったのは29歳の時でした。
そこから約40年近くに及ぶ講義の内容をまとめたものです。
書名の由来は、巻首にある彼の歌です。
そのかみのこゝろたづねてみだれたるすぢときわくる玉のをぐしぞ
内容の基本は何でしょうか。
とにかくそれまでになかった斬新な考え方を説いている点です。

以前は仏教的な道義に背くことをしてはならないという、江戸期の基本的な考え方に彩られた注釈本が主流でした。
しかし彼は違います。
人のこころは思い通りにはならないということを主張したのです。
人間には自ずと我慢しきれない感情があり、それに善悪をつけることには意味がないと論じました。
これを宣長は「もののあはれ」と呼んだのです。
ものごとの情趣が深い点を「あはれ」と呼び、決して否定することはありませんでした。
以前の価値観をガラリとかえたという意味で、この本が持つ意味は大きいのです。
本文
この段は高校の教科書でも学びます。
しかし十分に『源氏物語』を読み込んでいない段階では、ここだけを読んでも意味を捕まえるのが大変です。
ある程度、作品の全体像を捉えてから、読むと味わいが全く違うものになります。
文章が長いので、代表的な部分だけを紹介しましょう。
——————————–
さて、物語はもののあはれを知るを旨(むね)とはしたるに、その筋にいたりては、儒仏の教へには背けることも多きぞかし。
そは、まづ人の情こころのものに感ずることには、善悪邪正さまざまある中に、
理(ことわり)にたがへることには感ずまじきわざなれども、
情は我ながらわが心にもまかせぬことありて、おのづから忍び難きふしありて、感ずることあるものなり。(中略)

物語は、儒仏などのしたたかなる道のやうに、迷ひをはなれて悟りに入るべき法にもあらず、
また国をも家をも身をも治むべき教へにもあらず。
ただ世の中の物語なるがゆゑに、さる筋の善悪の論はしばらくさしおきて、さしもかかはらず、
ただもののあはれを知れる方のよきを、とりたててよしとはしたるなり。
この心ばへをものにたとへて言はば、蓮(はちす)植ゑて愛でんとする人の、濁りてきたなくはあれども、泥水を蓄ふるがごとし。
物語に不義なる恋を書けるも、その濁れる泥(ひぢ)を愛でてにはあらず、もののあはれの花を咲かせん料(しろ)ぞかし。
現代語訳
物語は「もののあはれ」を味わい知ることを趣旨とはしていますが、その筋立てにいたっては、
儒教や仏教の教えには反することも多いものです。
まず人の感情が物事に動かされることとしては、善悪邪正さまざまある中で、道理に反することには感動してはいけないものです。
しかし感情というものは自分でも自分の意のままにならないことがあって、
自然と抑えがたい時があり、人の道に背くようなことにも心動かされることがあるものなのです。
これが物語の本旨であって、その「よしあし」は儒教や仏教などの書物での善悪とは違う種類のものです。
そうだからといって、あの源氏の君のような不義を良しとするのではありません。
不義が悪いことは今さら言わなくても明白です。
そのような種類の罪を論ずることは、自然とその方面の書物が世の中にたくさんあるのはご承知の通りです。

善悪邪正を論じることには縁遠い物語に期待するべきではありません。
物語は、儒教や仏教などの厳格な道理のように、迷いを離れて悟りに入るための教えでもなく、
あるいは国をも家をも自分自身をも治めるための教えでもないのです。
ただ世間の人々の様子を描いた物語であるのですから、儒教や仏教の方面での善悪の論議は少し置いておいて、それほどこだわらなくてもよいのです。
ただもののあはれを理解している方面が優れていることを、特に取り上げているのです。
この意味を分かりやすく説明するためにものにたとえて言いいましょう。
つまり蓮を植えて愛でようとする人が、濁って汚くはあるが、泥水を蓄えるようなものなのです。
おわかりでしょうか。
もののあはれ
本居宣長といえば、すぐ連想される表現が「もののあはれ」です。
いったいなんのことなのでしょうか。
彼の生きた時代を考えてみてください。
江戸時代後期に国学者が学んだ学問は、第一に儒学でした。
儒教の思想は「仁義礼智信忠孝悌」を基本としたものです。
幕府の保護下にあった林家の朱子学は、武士道のためにあったといっても過言ではありません。
長幼の序は、目上のものにとって実に意味のある教えだったのです。
当然、本居宣長もその思想に感化されたと考えるべきです。
ところが彼が読み始めた『源氏物語』はそれとは全く異なる世界を描いた作品でした。
どのような物語だったのでしょうか。
光源氏を主人公とした実に情趣先行型の創作でした。
そこでは儒教や仏教の教義に反することが、あからさまに行われていたのです。
本来なら、道徳に反することは許されるべきものではありません。
しかし宣長にとって、『源氏物語』に書かれたことは、明らかに真実でした。
そこに抑えがたい人間のこころが宿っていると感じたのです。
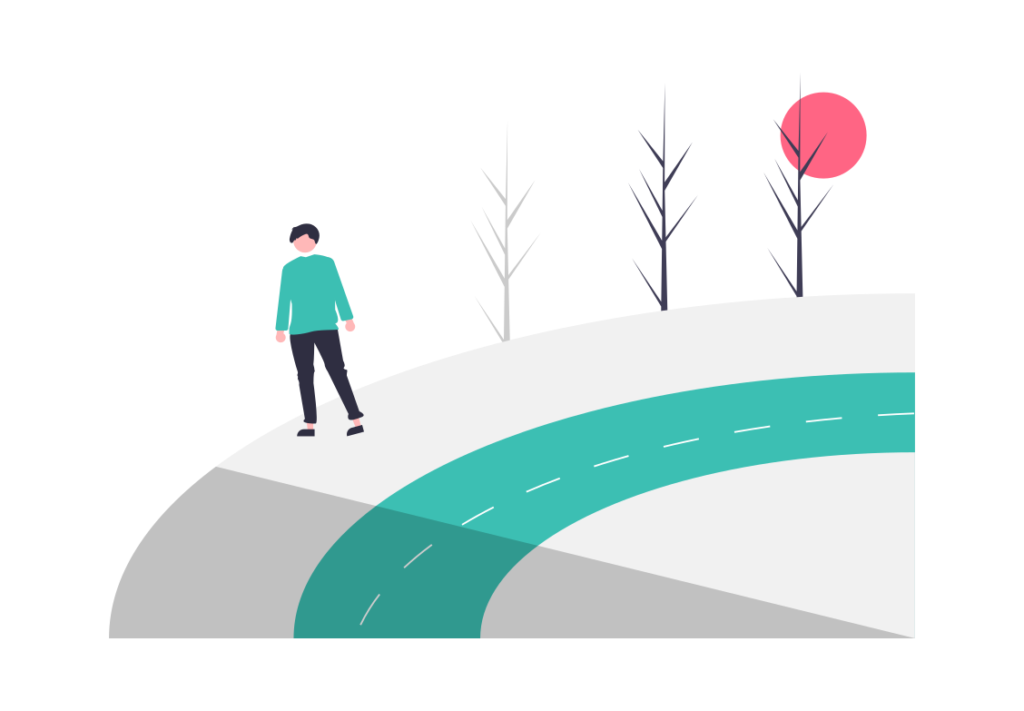
まさにそれを描くのが物語なのだと彼は得心しました。
人間のこころは自分の思い通りにはならないこと、我慢しきれないことがあることを知ったのです。
どんなにそれをしてはならないと自分を戒めてみても、こころや身体はそれは全く違う動きをするというところに彼は人間の真実をみました。
作中に出てくる空蝉の君、朧月夜の君、藤壺の中宮などは不義をおこない、良い人間とは言えません。
しかしそこに人間の本当の姿が描かれ、物事の情趣が深く籠められていたのです。
光源氏は決して悪徳にみちた主人公ではありません。
儒教や仏教の善悪観だけでは判別しがたい、世界がそこには現出しています。
そのことを宣長は「忍びがたきふし」「感ずること」と書いています。
これはしてはならないということと、それをしてしまうことの間には、ほんのわずかな差しかありません。
本来ならば、自制のこころでそれを抑えています。
しかしそこに愛情や恋情がからむと、人間は想像もしなかった行動を起こすことがあります。
それを「もののあはれ」と呼びました。
誰もが聖人君子のように正しい行いをしたいと夢見ているものです。
しかし人間を人間たらしめるのは、実はそこにはありません。
むしろ、教旨に反する行動の中に、人間の奥底に秘められた全く別の要素があるのかもしれないのです。
そこが光源になってつくられた作品の中に名作が多いのも事実なのです。
止むにやまれぬ思いで行われたそれらの行動の中に、芸術の持つもう1つの真実があります。
人間の裏側といってもいいかもしれません。
ドストエフスキーの作品に登場する主人公たちが、どういう行動をし、その故により人間味にあふれていたかを思い出してください。
ラスコーリニコフの懺悔に人はなぜ涙するのか。
物語は一見すると無駄なものかもしれません。
しかし人を正しく導くのではなく、人の真実をこれでもかとえぐってみせてくれるもう1つの装置でもあるのです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


