 本
本 【玉勝間・本居宣長】師の説になづまざることの中で最も言いたかったのは
本居宣長は日本を代表する国学者です。彼の随想集に『玉勝間』があります。この本は長い間の研究生活の中で、感じたこと、考えたことを自由に綴ったものです。特に自分の師の学説になじめない時、どうすればいいのかについて、言及しています。
 本
本  本
本  本
本 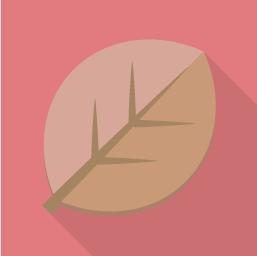 本
本 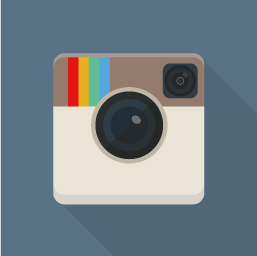 本
本  本
本  本
本  本
本 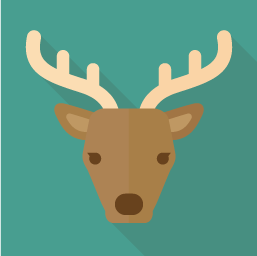 本
本 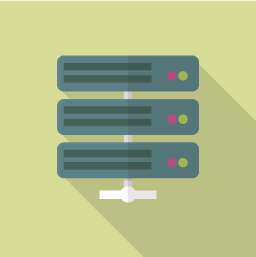 本
本 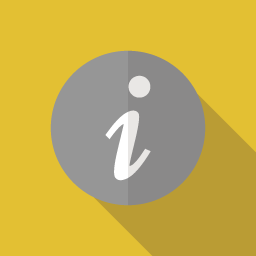 本
本  本
本 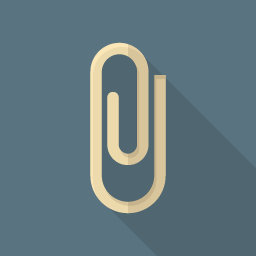 本
本 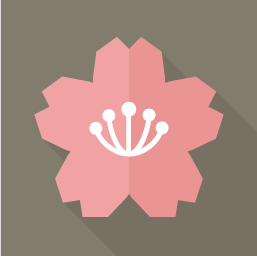 本
本 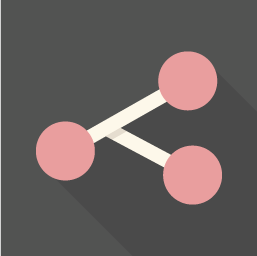 本
本 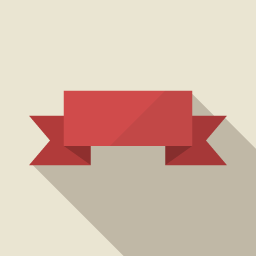 本
本