 本
本 【真夏の死・三島由紀夫】子供を失った母親が見た海の風景【死生観】
三島由紀夫の短編『真夏の死』を読みます。ここには彼の死生観がよく出ています。海の事故で子供を失った母親がどのようにその悲しみの記憶を拭い去っていったのかという軌跡を追いかけて行った作品です。一読をお勧めします。
 本
本  本
本  本
本  本
本 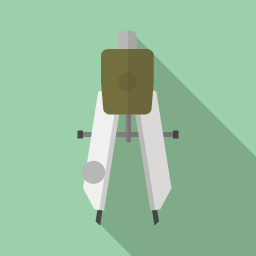 本
本 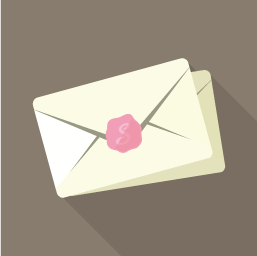 本
本  本
本  本
本 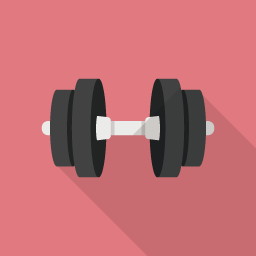 本
本 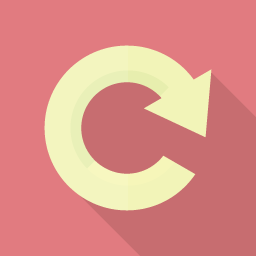 本
本  本
本 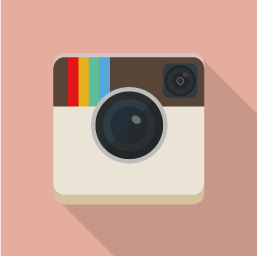 本
本 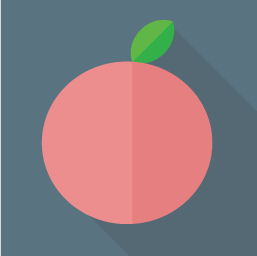 本
本 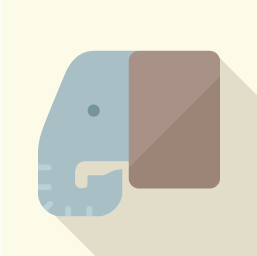 本
本 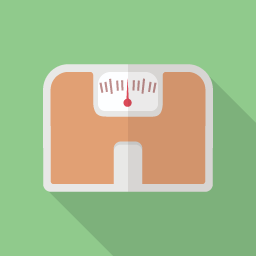 本
本 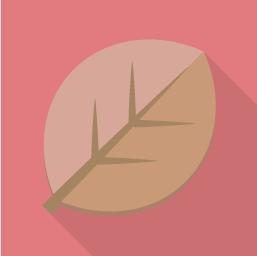 本
本