 本
本 【タイの僧院にて】文化人類学者が素手で知った托鉢とアジアの純真
文化人類学を研究していた著者は自ら、タイの僧院に入ることを決意します。内側に入らなければ何も見えないと信じたからです。最も厳しいと言われる総本山で托鉢修行の日々を送りました。やがて栄養失調になり還俗。その時の様子を描いた本です。
 本
本  本
本 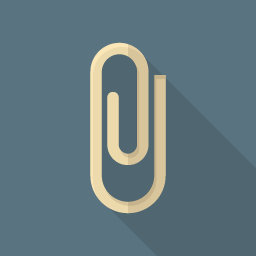 本
本  本
本  本
本 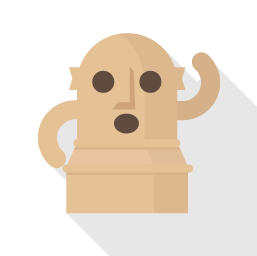 本
本 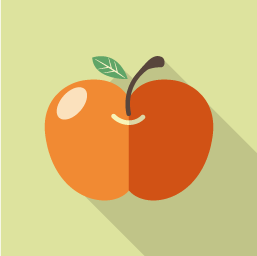 本
本  本
本  本
本 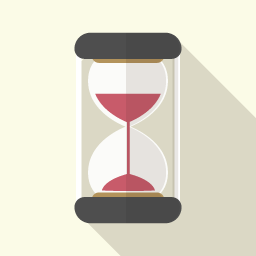 本
本 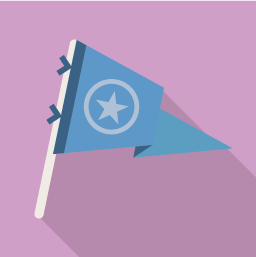 本
本 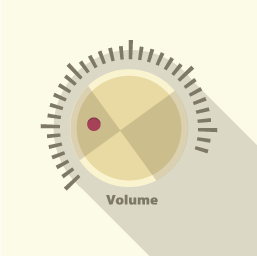 本
本  本
本  本
本  本
本 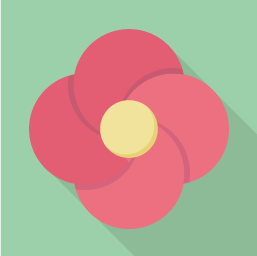 本
本