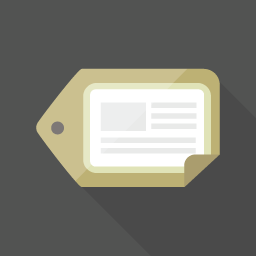蜜柑
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は芥川龍之介の短編を取り上げます。
タイトルは『蜜柑』です。
読んだことがありますか。
学校ではめったに扱いません。
所収している出版社もありますけれど。
教科書ではもっぱら『羅生門』でしたね。
これは高校1年で習う小説の定番です。
何度授業で取り上げたことでしょうか。

生きるとは何か。
正義と悪の境はどこにあるのか。
非常にわかりやすい対比が続きます。
以前、記事にしましたので、リンクをはっておきます。
読んでみてください。
しかし一番印象に残る作品を1つあげなさいと言われたら、やはり『蜜柑』かもしれません。
『羅生門』のような劇的な内容はどこにもありません。
日常がそのまま描き出されているだけなのです。
芭蕉臨終の様子を描いた『枯野抄』とか、『杜子春』のような作品も確かに心に残ります。
あるいは黒澤明監督が『羅生門』というタイトルの映画の題材にした『藪の中』なども素晴らしいですね。
しかしあえて一作と言われたら、やはり『蜜柑』です。
どうということのないストーリーです。
彼は横須賀の海軍機関学校の英語の教官として勤務していました。
大正5年(1916)から約2年4か月の間、嘱託教官をしていたのです。
25才から28才の結婚前後の期間です。
その時に偶然、電車の中で垣間見た風景を描いた小説です。
『蜜柑』の主人公は芥川龍之介その人です。
当時は英語の教師と作家の活動を同時にしていました。
自分がどこへ進むのか、まだ決まっていない段階です。
心の風景
或曇つた冬の日暮である。
私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下して、ぼんやり発車の笛を待つてゐた。
とうに電燈のついた客車の中には、珍らしく私の外に一人も乗客はゐなかつた。
外を覗くと、うす暗いプラツトフオオムにも、今日は珍しく見送りの人影さへ跡を絶つて、唯、檻に入れられた小犬が一匹、時々悲しさうに、吠え立ててゐた。
これらはその時の私の心もちと、不思議な位似つかはしい景色だつた。
私の頭の中には云ひやうのない疲労と倦怠とが、まるで雪曇りの空のやうなどんよりした影を落してゐた。
私は外套のポツケツトへぢつと両手をつつこんだ儘、そこにはいつてゐる夕刊を出して見ようと云ふ元気さへ起らなかつた。

——————————-
作者の暗い内面が天候ま描写にもよく表れていますね。
曇った冬の日暮れ、薄暗いプラットホーム、どんよりとした影などという表現をみているだけで、作者の世界が疲労と倦怠にまみれたものであることがよくわかります。
そこへ突然あらわれたのが、1人の少女です。
その描写に当時の生活が透けてみえます。
これから奉公に出る少女だったのです。
その外見を見ただけで、豊かでない暮らしぶりがわかります。
——————————-
それは油気のない髪をひつつめの銀杏返しに結つて、横なでの痕のある皸だらけの両頬を気持の悪い程赤く火照らせた、如何にも田舎者らしい娘だつた。
しかも垢じみた萌黄色の毛糸の襟巻がだらりと垂れ下つた膝の上には、大きな風呂敷包みがあつた。
その又包みを抱いた霜焼けの手の中には、三等の赤切符が大事さうにしつかり握られてゐた。
私はこの小娘の下品な顔だちを好まなかつた。
それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だつた。
最後にその二等と三等との区別さへも弁へない愚鈍な心が腹立たしかつた。
不可解で下等で退屈な
2等車と3等車の違いもわからずに乗り込んでくる娘の愚かさに、彼は腹をたてています。
日々の憂鬱な暮らしの裏返しでしょうか。
あらゆるものに腹が立つというのがその心理状態でしょう。
仕方なく、彼は目を閉じます。
倦怠の中に沈んだ日常を追いかける言葉にいらだちが残ります。
その無部分の心理描写は次の通りです。
———————————-
この隧道の中の汽車と、この田舎者の小娘と、さうして又この平凡な記事に埋つてゐる夕刊と、――これが象徴でなくて何であらう。
不可解な、下等な、退屈な人生の象徴でなくて何であらう。
私は一切がくだらなくなつて、読みかけた夕刊を抛り出すと、又窓枠に頭を靠せながら、死んだやうに眼をつぶつて、うつらうつらし始めた。
——————————–
ところがそれからしばらくした後、芥川は意外なシーンに出っくわすのです。

無理に汽車の窓ガラスを開けようとする少女の姿でした。
トンネルを抜ける際に煙が車内に飛び込んでくる様子が、そこにいるかのように描写されます。
———————————-
それから幾分か過ぎた後であつた。
ふと何かに脅されたやうな心もちがして、思はずあたりを見まはすと、何時の間にか例の小娘が、向う側から席を私の隣へ移して、頻に窓を開けようとしてゐる。
が、重い硝子戸は中々思ふやうにあがらないらしい。
あの皸だらけの頬は愈赤くなつて、時々鼻洟をすすりこむ音が、小さな息の切れる声と一しよに、せはしなく耳へはいつて来る。(中略)
すると間もなく凄じい音をはためかせて、汽車が隧道へなだれこむと同時に、小娘の開けようとした硝子戸は、とうとうばたりと下へ落ちた。
さうしてその四角な穴の中から、煤を溶したやうなどす黒い空気が、俄に息苦しい煙になつて、濛々と車内へ漲り出した。
元来咽喉を害してゐた私は、手巾を顔に当てる暇さへなく、この煙を満面に浴びせられたおかげで、殆息もつけない程咳きこまなければならなかつた。
蜜柑を投げる少女
少女はトンネルを過ぎた後、とうとう窓を開けます。
そして半身を乗り出したのです。
そこにいたのは姉を見送りに来ていた弟たちでした。
———————————
彼等は皆、この曇天に押しすくめられたかと思う程、揃って背が低かった。
そうして又この町はずれの陰惨たる風物と同じような色の着物を着ていた。
それが汽車の通るのを仰ぎ見ながら、一斉に手を挙げるが早いか、いたいけな喉を高く反らせて、何とも意味の分らない喊声を一生懸命に迸らせた。
するとその瞬間である。
窓から半身を乗り出していた例の娘が、あの霜焼けの手をつとのばして、勢よく左右に振ったと思うと、忽ち心を躍らすばかり暖な日の色に染まっている蜜柑が凡そ五つ六つ、汽車を見送った子供たちの上へばらばらと空から降って来た。
私は思わず息を呑んだ。
そうして刹那に一切を了解した。
小娘は、恐らくはこれから奉公先へ赴こうとしている小娘は、その懐に蔵していた幾顆の蜜柑を窓から投げて、わざわざ踏切りまで見送りに来た弟たちの労に報いたのである。
私は昂然と頭を挙げて、まるで別人を見るやうにあの小娘を注視した。
小娘は何時かもう私の前の席に返つて、不相変皸だらけの頬を萌黄色の毛糸の襟巻に埋めながら、大きな風呂敷包みを抱へた手に、しつかりと三等切符を握つてゐる。
私はこの時始めて、云ひやうのない疲労と倦怠とを、さうして又不可解な、下等な、退屈な人生を僅に忘れる事が出来たのである。
———————————
大正8年4月に発表されたこの小説には当時の芥川の心の風景が、そのまま描写されています。

窓から弟たちに蜜柑を投げる少女に、人間の真実を見たのでしょう。
それが倦怠と疲労を忘れさせてくれたのです。
行きたくて奉公にでるワケではありません。
全て暮らしのためです。
それでも見送りにきて弟たちへ感謝の気持ちをあらわしたいという、気持ちに嘘はありません。
貧しくても、こういう真実の生き方があるという事実が重たかったのでしょう。
自分はそこまで真剣に向き合っているのかという反省をしたのかもしれません。
名作です。
芥川龍之介の生の声が聞こえてくる、数少ない小説の1つです。
青空文庫で読めます。
本当に短い魂のこもった小説です。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。