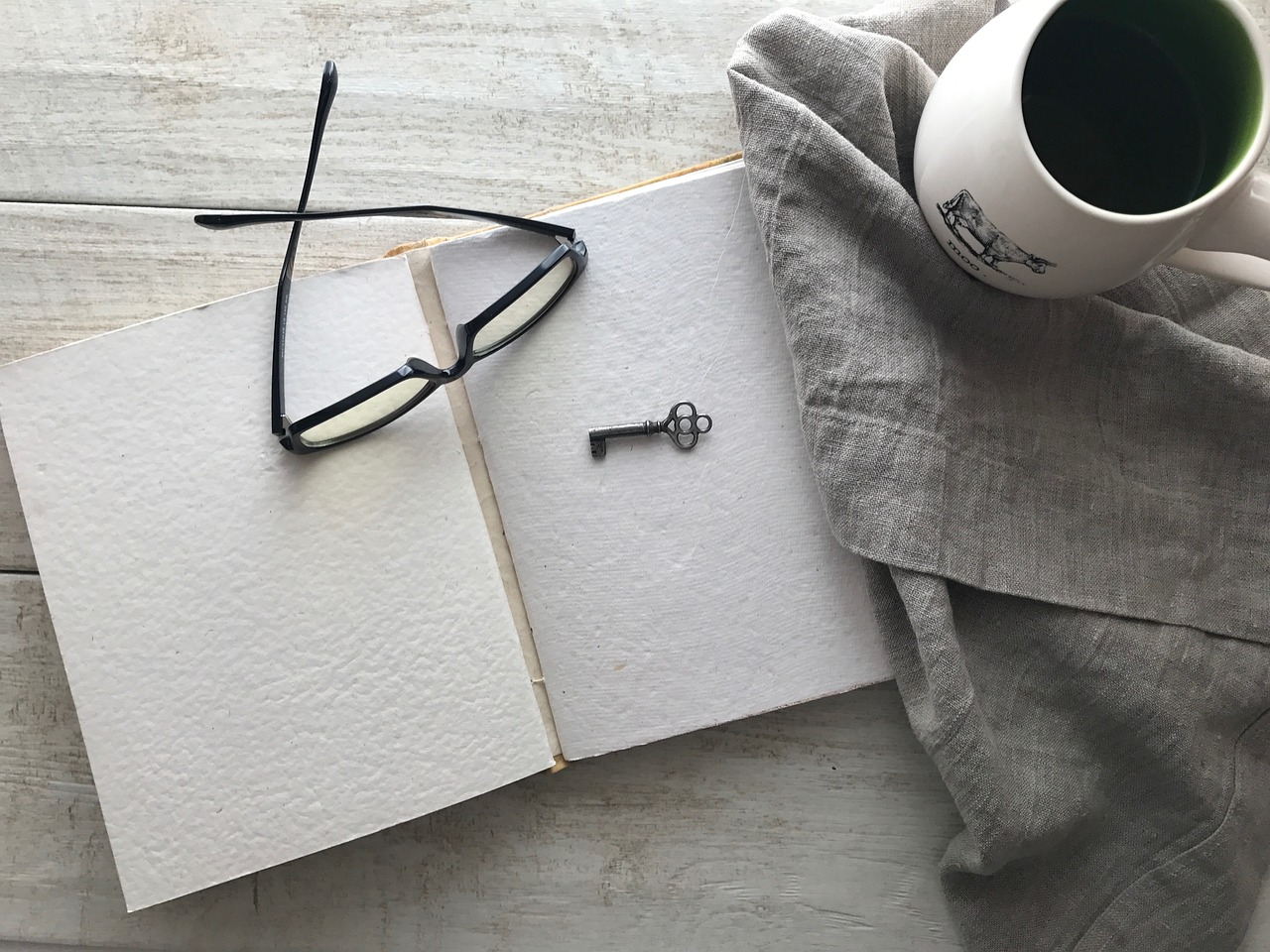 本
本 【魯迅・故郷】貧しさに苦しむ中国の未来に文学の可能性を託した人
魯迅の『故郷』は中国の現実を描き出した小説です。貧しさの故にかつての友達との階級を意識せざるを得なくなります。自然な付き合い方がもうできないのです。その現実を見た時、これではいけない。息子の代になるまでには改革をと考えるのでした。
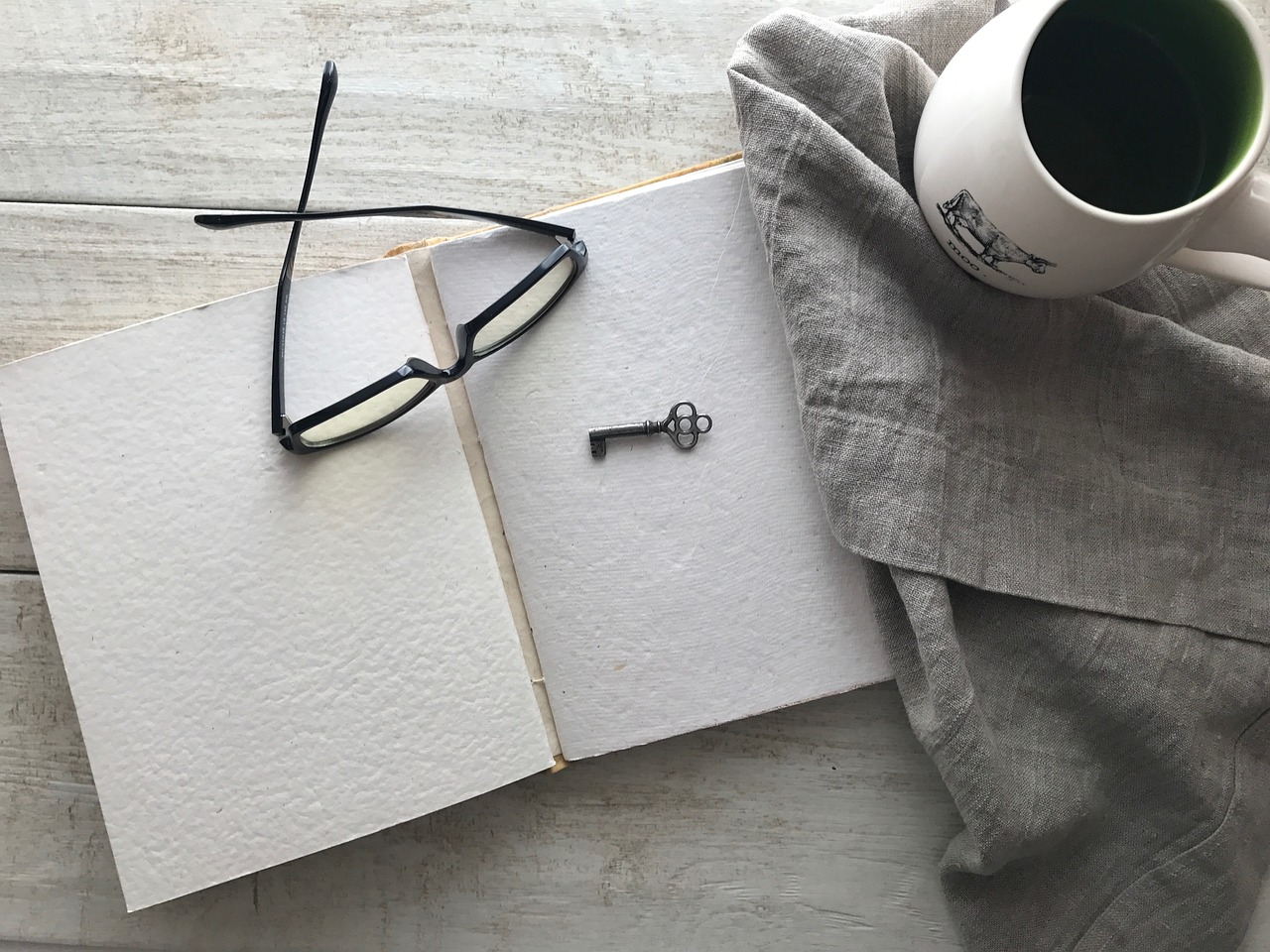 本
本  本
本  本
本  本
本 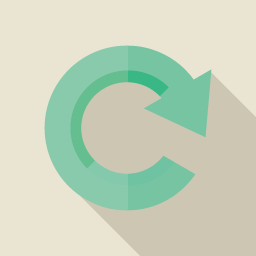 本
本  本
本 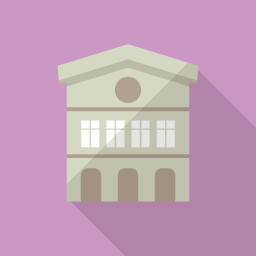 本
本  本
本  本
本  本
本 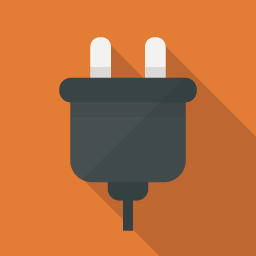 本
本 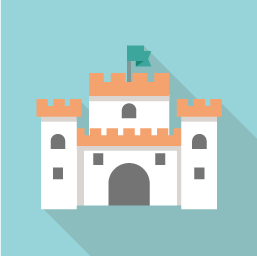 本
本  本
本  本
本  本
本  本
本