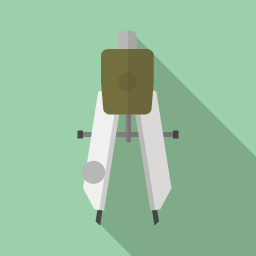授業が消える
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今日はここのところ気になっていて仕方のないことを書かせてもらいます。
それは2022年から開始される、国語科の新しい科目のことです。
ぼくはつい1年前まで、ある高校の非常勤講師をしていました。
その時は2年生6クラスを相手に森鴎外の『舞姫』を教えました。
来る日も来る日も『舞姫』でした。
生徒はかなりまいってましたね。
なにしろ日本語じゃない。
もちろん彼らにとってですけど…。
通常ならCDをかけて、あとは教師がぼんやりしてるというパターンもあります。
しかしぼくはなにがなんでも生徒に読ませようと思いました。
『舞姫』はある意味で完全な古文です。

geralt / Pixabay
明治の時代にこうした文章を書ける人がいたということだけでも、読み取ってもらいたいと願ったからです。
読むだけで、授業を2コマ分は完全に使いました。
誰もがつっかえて読めないというわけじゃありません。
きちんと読める生徒もいます。
やはりできる生徒は読める。
どうもこれは永遠の真実です。
国語力が他の科目の基礎になっているということがよくわかります。
明治の時代の官僚がどのようなものであったのか。
友情とはなにか。
それを少しずつ解読していきました。
わかった生徒がどれくらいいたのか。
期末試験の点数もあまりよくありませんでした。
生徒の一人は、日本語の試験の方が英語より悪いといって笑っていました。
おそらく彼らは2度とこの作品を読むことはないと思います。
だからこそ、やりたかったのです。
二度と読まない
夏目漱石『こころ』、中島敦『山月記』、芥川龍之介『羅生門』など、今までさんざんに言われてきました。
こんな作品を教科書に載せる必要があるのか。
毎年同じ教材で、先生は楽をしている。
しかし現場にいた教師の実感として、このチャンスを逃したら彼らはもう読まないのです。
あるいはいつか手にした時、昔、高校でわけのわからない授業でやったというかすかな記憶がよみがえるかもしれません。
それでもいいと思ってやりました。
つい先日も『山月記』をていねいに説明した時、生徒は登場人物の性格と自分の性格がいかに似ているかを自己分析して聞かせてくれました。

geralt / Pixabay
アイデンティティの確立が十分にできていない時代に、こうした作品を通じて、自分と周囲との距離を測る作品はけっして無駄ではないのです。
長編にまじって村上春樹、小川洋子、川上弘美、三島由紀夫、太宰治、梶井基次郎などの短編も所収されています。
難しい定番教材の間に、このような作品をおりまぜて学習すると、大変新鮮にみえます。
教えている方の気分もどこか救われるのです。
さらに俳句、短歌、詩などの作品群があります。
古典で習うものとは違う、同時代感覚も養えるというわけです。
文学は誰もが口にしない、人のこころの中に踏み込んで、これでも人は生きる価値があるのかと呟きます。
たとえ授業中でさえ、自分というものに肉薄する契機になりうるのです。
もう一つ、先生も文学が好きなのです。
それ故に教師になった人が多い。
だから作品について語る時の先生の素顔に人間が垣間見えます。
それも学習の契機になるのです。
今もある高校で補習の授業を担当しています。
もちろん、使っている教科書は現行の学習指導要領にのっとったものです。
それがまもなく改訂され、大きく方向を変えようとしています。
新学習指導要領登場
変わるのは、国語の科目構成です。
「国語総合」4単位
「国語表現」「現代文A」「現代文B」「古典A」「古典B」が選択科目
「現代の国語」2単位「言語文化」2単位
「論理国語」「文学国語」「国語表現」「古典探究」が選択科目
1単位とは1週間に1時間の授業をさします。

geralt / Pixabay
「現代の国語」では、目的が「情報と情報との関係」と「情報の整理」とに分けられています。ここに文学の入りこむ要素はありません。
「言語文化」では上代から近現代につながる我が国の言語文化への理解を深めるとあります。現在のところ、内容はもう一つ明らかではありません。
問題点として、選択科目が「論理国語」と「文学国語」に再編されたことです。
「論理国語」を選択すると、従来に比べて、評論や、報道や広報の文章や報告書、企画書、法令文など実用的な文章を教材として扱う機会が増えると思われます。
小説などの文学作品を読む機会が一気に減少することになるでしょう。
こうした変化を避けるために、全体で単位数は増えてしまうものの、「文学国語」を加える学校が出てくるかもしれません。
しかし4単位は重いです。
結局、高校の国語科での文学や小説は、新学習指導要領によると大幅に減らされたあげく、高校1年生までしか学ばない生徒たちが普通になりそうです。
今まで以上に文学離れが進むのは間違いありません。
その代わりに入ってくるのが、「論理国語」です。
契約書や法律の条文、統計資料、電子メールなど、非常に実用的・実務的な内容の教材になりそうです。
このことは実際過去に2回行われた「大学入試共通テスト」の試行版をみればよくわかります。
1回目はある高校の部活動に関する生徒会規約の文章、2回目は著作権法の条文が主な題材でした。
参考までに大学入試センターが過去に行った試行版のテストをリンクしておきます。
気が向いたら、問題を解いてみてください。
実は数年前にこれを生徒にやってもらいました。
結果は惨憺たるもので、全くどう解答していいのかわからないという生徒もいました。
本当にこういう問題がこれからの主流になっていくのだとしたら、ちょっと怖ろしい気もします。
文学が消えた後
各高校は、大学入試を意識して授業を行います。
生徒のニーズを全く無視するわけにはいきません。
カリキュラムの編成にも気を遣うことになります。
選択科目については、大学進学者の多い高校では、「論理国語」「文学国語」「国語表現」「古典探究」(各4単位)のうちから2科目を履修するのが一般的になるでしょう。
現在のセンター試験は「国語総合」を出題範囲としているものの、実際に「国語総合」の学習だけでは古典で高得点を獲得するのは難しい状況です。
「国語総合」と「言語文化」の古典の難度が同程度になる可能性は十分に考えられます。
さらにセンター試験と共通テストの難度も同程度となった場合は、「古典探究」の履修が必要になるでしょう。
実際にまだ教科書ができていない段階なので、何とも言えませんが、「文学国語」をあえてとるのかどうか。
これも悩ましいところです。
「論理国語」などの時間には法律の条文や規約、契約書などを扱うことが増えるでしょう。
非常に実用的・実務的な文章を高校の国語の時間に扱い、おそらく文学は軽視されるようになります。
グローバル化の影響はここにもあらわれているのです。

一言でいえば、実用主義です。
ビジネスの方向に向いた力です。
今回の国語科の教育内容の「改革」は、実利的、実用的なものを重視する流れにのっていると考えるのが自然でしょう。
かつて女子大生が増えすぎ、文学部は不要だという説をとなえた学者もいました。
今、まさにビジネス偏重の社会になり、文学は不要だいう考えが主流になりつつあります。
短期大学の文学系学科は消え去り、その流れは4年制にも向かっています。
世界は政治、とくにその背景にある経済で回っているという社会の認識が教育の形を変えようとしているのです。
また、今回の「改革」にはPISA(生徒学習到達度調査)の結果も関わっています。
以前の調査によれば、日本の生徒は実用文読解の記述式の正答率が低かったので、それを引き上げることを文科省は考えているようです。
契約書やグラフの読み取りも大切でしょう。
しかし文学や物語、小説には潜在的な力があります。
それを無視して先にすすめるものかどうか、考えてみれば結論はすぐにでるのではないでしょうか。
そんなことをずっと考えていたら文芸誌の「すばる」と「文学界」が、新しい国語科指導の特集をしていました。
文学の未来はどうなるのでしょう。
皆さんも一緒に考えてみてくださいね。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。