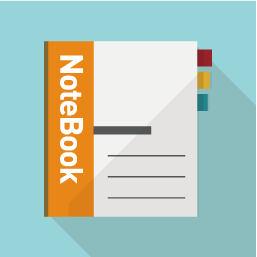落語ってなに
みなさん、こんにちは。
アマチュア落語家、ブロガーのすい喬です。
テレビの人気番組、「笑点」を見たことがありますよね。
色とりどりの着物を着た噺家さんが、たくさん布団を並べて、面白いことを言って…。
どうやったら、あんなウィットに富んだギャグを次々と思いつくのか。
不思議で仕方がないのではないでしょうか。
この番組は1966年から日本テレビ系列でずっと放送されている、ご長寿番組の一つです。
視聴率も20%を超える時もあるというお化け番組です。

3D_Maennchen / Pixabay
しかしあれは正確に言うと、落語そのものではありません。
大喜利と呼ばれ、落語が一通り終わったあとに、余興として行われるものです。
笑点はその大喜利の部分だけを拡大して、制作された特別バージョンなのです。
誰が始めたのかって。
それは落語界の大立役者。
立川流元祖家元、立川談志です。
当時はやっていた三浦綾子の小説『氷点』をもじって命名されました。
まさかここまで続くとは、当時は誰も想像してなかったでしょうね。
さて落語の話に戻りましょうか。
一度、寄席というところに行ってみたいと思ったことはあるけれど…。
どこでチケットを買えばいいかわからないし…。
ホール落語とどこが違うのかな。
チケット代がいくらなのかも知らないし…。
どんな噺があるのか…。
それに、なんとなく敷居が高いし…。
なんといっても時代は令和ですからね。
AI革命、GAFA全盛の時代です…。
落語なんて聞いて、暢気に笑ってる場合じゃないかな。
でも、ちょっと待ってください。
つい最近読んだ本、鈴木貴博『令和を君はどう生きるか』にはこんなことが書かれていました。
これは若者向けに書かれた本ですが、どんな年齢の人にとっても共通だろうと感じます。
コミュニケーションの力
お金についての知識
ITリテラシー
このうちの最初の2つが、落語にあてはまると思いませんか。
でもどうしたら身につくのか。
ちょっとしたスキマ時間を使って、身につくもの。それは相手を和ませる術です。

この人はこういう一面をもっているんだという意外性。
これがものすごい武器になります。
それは相手を楽しく和ませ、自分のことを好きになってもらうための話術です。
人に不愉快な感情を抱かせない。
これだけで、すごいスキルだと思いませんか。
もう一つ。
3つの道楽
落語にはお金にまつわる話が山のように出てきます。
その中のいくつかを知っていたら、相手に対して説得力が増します。
ものすごくケチな人、その反対にやたらと強欲な人。
登場人物はいくらでもいます。
彼らの最後はどうなったのか。
それを見極めるのも落語の楽しみです。
という以上に生きていく上での、大きな教訓になるのではないでしょうか。
お金のことなら落語で全て学べます。
富くじ(宝くじ)にあたったものの、その後の生活が乱れてしまった人物。
その反対に人の情けを身にしみて味わった男。

さらにいえば、男女の仲です。
これは落語の永遠のテーマ。
夫婦の機微や若い男と女の哀れな結末。
どうしても別れられない男と女はその後どうなったのか。
金が縁の切れ目とはいうものの、それだけではすみません。
さらに子供との親子の愛情にからむ噺もたくさんあります。
最後は酒。
これも永遠のテーマです。
江戸の昔も現代も、なにひとつとしてかわったものはありません。
酒は百薬の長ともいいますが、酒は毒水だという人もいます。
これを題材にした落語は山のようにあります。
短いものなら10分くらいから、長いものなら1時間を超えるものまで。
たった一人で演じるのです。
音曲の力を借りるのもありますが、基本的には素噺といってただ喋るだけです。
たよりになるのは手拭いと扇子だけ。
これほどに簡素な芸能は珍しいのではないでしょうか。
元はといえば、歌舞伎のように高い入場料を払えない庶民が編み出した娯楽です。
しかしそこにやがて血が通い、人の情けが付け足されました。
オチによって噺の種類がたくさんに分類されています。
しかしそんなことはどうでもいい。
とにかくまず聞いてみることです。
youtubeにはこれでもかというくらい落語の動画があります。
好きな噺家を探すのもいい。
時間があったら寄席にも足を運んでほしいです。
寄席は1年365日、休まずに営業を続けている不思議な空間です。
都内の寄席ならば、いつでもその場でチケットを買って入れます。
ネットで予約をする必要もありません。
シニア割引もあります。
年会員になると、招待券も届きます。
聞いてよし、見てよし、演じてよし
これが落語なんです。
落語を聞くと、言葉に対するリテラシー(記述表現力)が飛躍的に増えます。
さらには他人に対してやさしくなれる。
落語は強いものに対して徹底的に意地をはりますが、弱者に対しては限りなくあたたかいです。

geralt / Pixabay
多くの経営者、知識人がなぜ落語を聞くのか。
面白いだけではないのです。
他者に対する思いやりの気持ちをどう育てていくのか。
人の心理の裏側にまで入り込むからです。
滑稽話、人情噺。
どちらもすばらしい。
まず聞いてみましょう。
それから見てみましょう。
さらに自分で演じてみましょう。
そのためにはどうすればいいのか。
落語にはどんな演目があるのか。
これから少しずつ探っていきます。
どこで誰がいつどんな噺をしてくれるのか。それも知りたい。
どうやって調べればいいのか。
なんにも知らなくてもいい。
面白かったら笑う。
そして元気になる。
これが落語の醍醐味です。
最後に得になる5つの理由を復習しておきましょう。
お金についての知識が増す
人に対してやさしくなれる
言葉のリテラシー(記述表現力)が向上する
人間の煩悩を知り、観察力が深まる。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
さあ、一緒に落語を楽しみましょう。