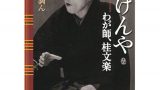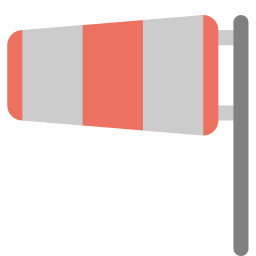若旦那
みなさん、こんにちは。
アマチュア落語家のすい喬です。
今回は落語にでてくる「若旦那」について考察してみましょう。
最後まで暢気な話です。
そのつもりでお付き合いください。
落語に出てくる若旦那は、たいていが道楽者です。
親の身代を食いつぶすパターンがほとんどなのです。
二宮金次郎とは正反対だと考えてください。
子供の頃から乳母日傘で育てられています。
大きな店を経営している親は、どうしても息子に甘くなりがちです。
たいていの場合、自分の財産をやがては倅に譲るということになるのです。
そのために幼いうちから、厳しくしつけをした家もあったでしょう。
しかしどこかに親子の甘えがでます。
それは現代も同じこと。
他人の家の釜の飯を食べなければ、世間の厳しさはわからないものです。
親のつくりあげた会社をアッというまにダメにしてしまうケースが、あとをたちませんね。
つい最近の例でいえば、「ビッグモーター」でしょうか。
2代目の息子を社長にしたのが失敗でした。
そうでなければ、今のような惨状にはならなかったでしょうしね。
自業自得だといえば、それまでのことです。
そこへいくと、「ジャパネットたかた」はうまくいっているようですけれど……。
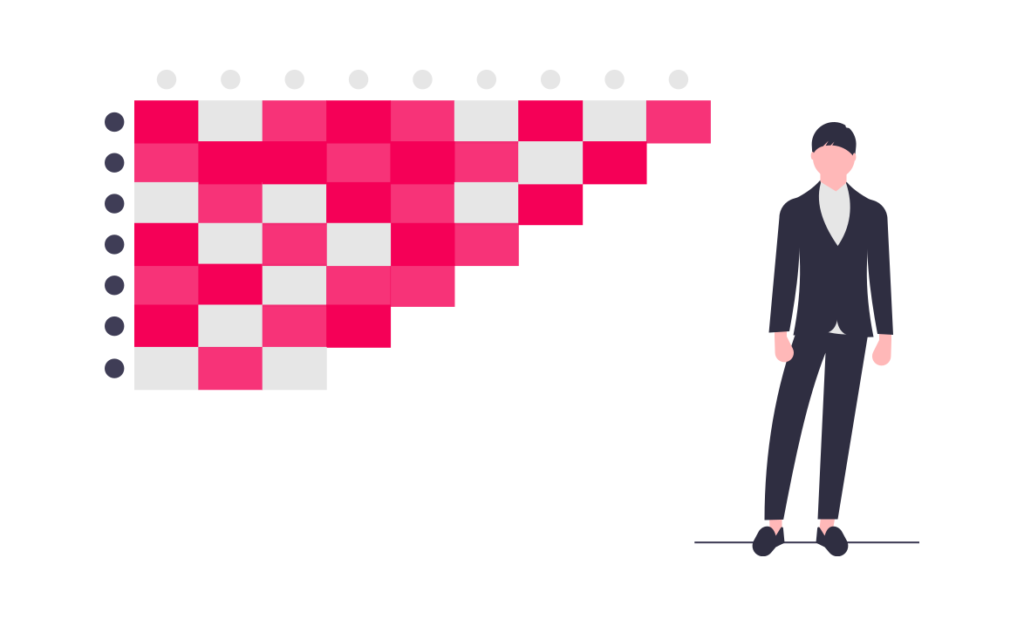
ところが落語はそこまでいきません。
根っこには笑いがあります。
どうしようもないこんなヤツが世の中にはいるよ、確かにね、というところで、ぎりぎりセーフになっています。
ぼく自身、もう15年も落語をやっているので、いくつか若旦那ものもやります。
そのなかで、ダントツに楽しいのはやはり「船徳」でしょうか。
船徳
男の三道楽といえば、「呑む」「打つ」「買う」と相場が決まっています。
そこでちょっと「船徳」の中身を覗いてみましょう。
この噺に出てくる若旦那は、三道楽で失敗したのでしょうか。
どうもそこまではっきりとした原因はなさそうです。
ただ働くのがイヤというころでしょうか。
背景が夏の暑さにピッタリなのです。
なんといっても船頭の話ですからね。
大川(隅田川)と四万六千日の設定です。
この日は、ほおずき市で有名ですね。
浅草の観音様の縁日で、旧暦7月10日にあたります。

現在の暦だと8月の半ば。
とんでもない猛暑の最中ということになります。。
昔はこの日にお参りすれば、四万六千日(約128年)参詣したのと同じご利益が得られると信じられていました。
噺の主役は道楽が過ぎて勘当された居候の若旦那、徳兵衛です。
柳橋の知り合いの船宿の2階で、毎日ブラブラしています。
大旦那に世話になっているので、親方も預かってはみたものの、どうしようもありません。
そこで働いてみる気はないかともちかけると、何を勘違いしたのか、姿形の良さに憧れ「船頭になりたい」などと、言い出す始末です。
使用人たちも若旦那と呼んでいた人を、仲間と同じように呼びつけにもできません。
親方もどうせすぐに嫌気がさすだろうと半ば諦めて、ちょっとだけやらせてみることにしたのですが…。
八代目桂文楽
「船徳」といえば、八代目桂文楽でしたね。
文楽存命の頃は、他の噺家はほとんど高座にかけませんでした。
やったのは古今亭志ん朝くらいでしょうか。
よほど自信がないとできませんでした。

比べられるのが嫌だっただろうと思われます。
文楽が高座にあがると、「船徳」と声をかけられることがよくあったそうです。
弟子の柳家小満んが書いた本がありますのでリンクしておきます。
ぼく自身、何度も動画を見て、参考にさせてもらいました。
噺の前後を分ける決めゼリフがあります。
客がいやがる友人を無理に船宿まで連れてきて、観音様まで一艘頼むと女将に頼むシーンから後半が始まるのです。
前半で繰り広げる船頭たちの様子がここで一変します。
とにかくジリジリと焼けるように暑い日の様子が描かれるのです。
この後、新米船頭がとんでもない失敗を繰り返します。
やっていてすごくくたびれますね。
扇子1つで、櫓を漕いでいる姿を連想してもらわなければなりません。
有名なシーンです。
その決めゼリフとは……。
「四万六千日、お暑い盛りでございます」というものです。
文楽が少し声を張り、高い調子で呟くと、本当に寄席全体が、真夏の隅田川に変貌しました。
さて、船宿に来てはみたものの、船頭が1人もいません。
せっかく友達をつれてきたのにと残念がる客の前で、部屋の柱に寄りかかって、船頭が1人居眠りをしています。
その姿を見た客は、お約束なら大桟橋まで行ったら、すぐに返すからと客は早とちりするのです。
「この人はダメ、ダメ」と大きな叫ぶ女将に客が無理に頼み込みます。
ここからが落語ですね。
案の定、とんでもないことになるのです。
演者の力量がものすごく必要なシーンの連続です。
サゲまでが痛快
船を出してはみたものの、櫓を漕ぐのに慣れていません。
同じところを三度も回ったり、石垣に張り付いたまま、船が動かなくなります。
「この船は石垣が好きなんです。そこのコウモリ傘を持っている旦那、石垣をちょいと突いてください」
言われて、傘で突いたのはいいのですが、石垣の間に挟まって抜けなくなってしまいます。
「もう諦めてください。2度とあそこへは行きません」
途中で、徳さんが「竹屋のおじさん、今からお客を大桟橋まで送ってきます」と橋上の人物に呼びかけるシーンがあります。
このおじさんが、「徳さん1人かい。大丈夫かい」と絶叫して、船中の客をふるえあがらせるギャグも楽しいです。

そのうち、目に汗が入ったのか、前が見えなくなりました。
さんざんお客に冷や汗をかかせて、大桟橋までもう少しのところまできます。
しかし目前で、浅瀬に乗りあげてしまうのです。
客は船を嫌がる友達をおぶって水の中を歩きながら、桟橋にやっとのことで辿り着きます。
船に残された徳さんは、真っ青な顔をして呟きました。
「お客さん、おあがりになりましたら、船頭を一人雇ってください」
落語に出てくる若旦那は、罪がなくていいですね。
こういう噺をしていると、気分が高ぶってきます。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。