 本
本 【女生徒・太宰治】少女の不安を巧みに表現したお得意の自意識日記【怖い】
太宰治の小説『女生徒』はなかなかユニークな作品です。1日の朝から夜までを日記風にまとめてあるのです。全編にわたって、1人の女生徒の自意識をそのまま、言葉でまとめ切っているのです。自己愛の中身をのぞいてみましょう。
 本
本 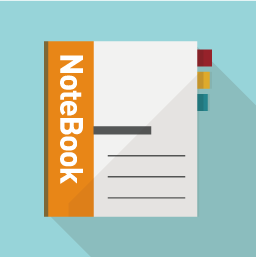 本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本 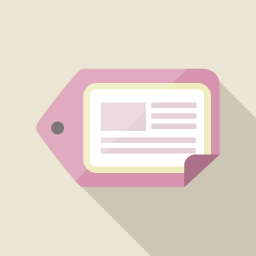 本
本 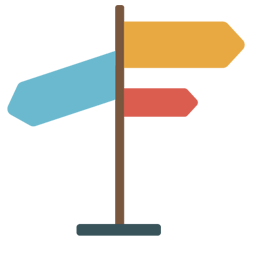 本
本  本
本 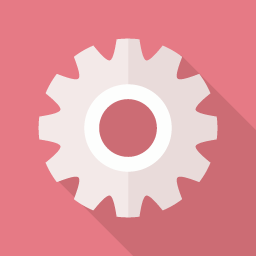 本
本