 小論文
小論文 「小論文・オリジナルであるために学び続ける」という坂本龍一の真意は
音楽家、坂本龍一の言葉を使って小論文を考えてみましょう。都立高校の推薦入試に出題された問題です。ポイントはオリジナリティを探す道のりは、日々の学びの中にあるということです。珍しいことでなく、むしろ地道な探求の連続が新しい地平を生むのです。
 小論文
小論文  学び
学び 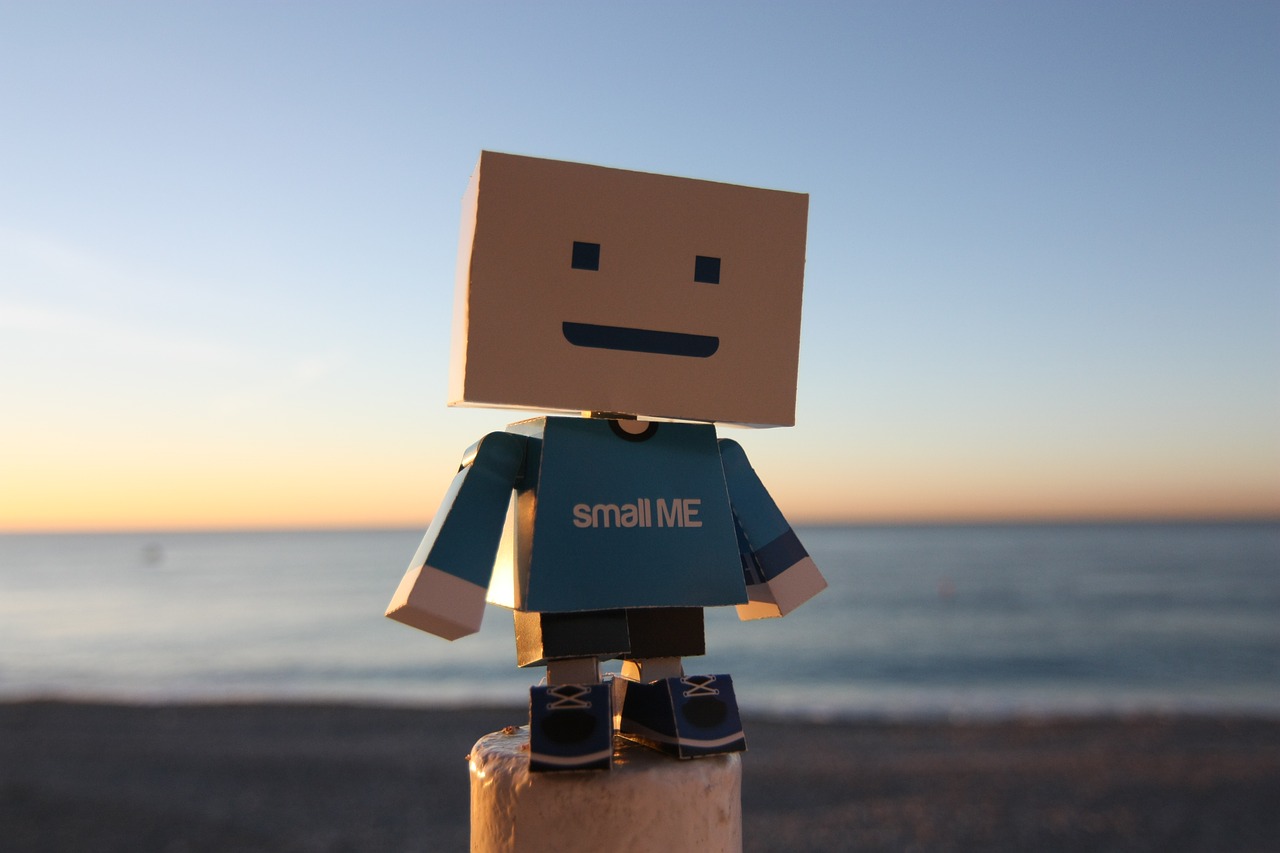 学び
学び  本
本  ノート
ノート  ノート
ノート  学び
学び  本
本 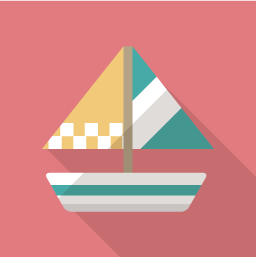 学び
学び  本
本 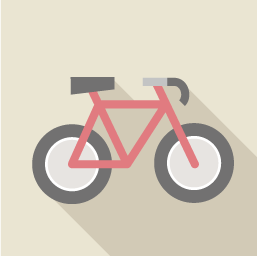 学び
学び  ノート
ノート  学び
学び  小論文
小論文  小論文
小論文 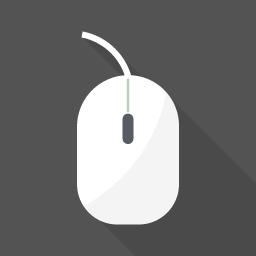 学び
学び