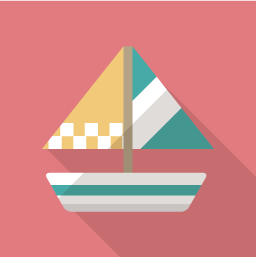 学び
学び 【対話の言葉】対等な関係の表現を模索する過渡期の日本人【平田オリザ】
日本人が現在使っている言葉は、開国以来短い期間で、翻訳されたものが多いのです。それだけに全てが身体になじんだものであるとはいえません。特に対話をする時の語彙は、浮いた印象のものが多いのです。ジェンダーフリーの時代に適した表現は何なのでしょうか。
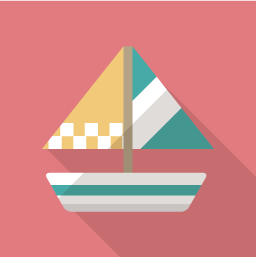 学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び 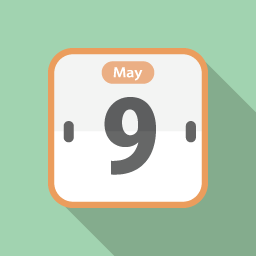 学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び 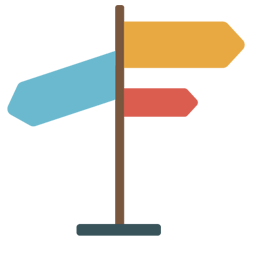 学び
学び  学び
学び