 学び
学び 【わたしを束ねないで・新川和江】紡ぎ出された言葉の1つ1つが痛い
詩のことばは強いですね。何気なく呟かれた表現の中に真実があるからです。新川和江さんのこの詩には、たくさんの思いがつもっています。その表現に触れるだけで、自分がどれほど世間という枠組みの中で生きて来たのかということがわかるのです。
 学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び 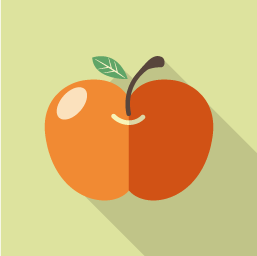 学び
学び  学び
学び 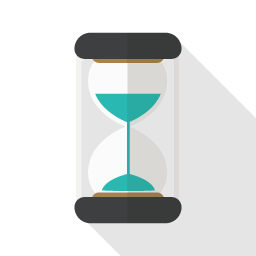 学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び 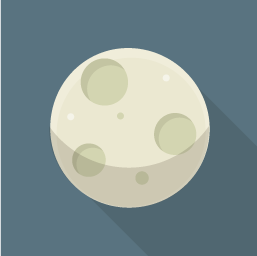 学び
学び  学び
学び 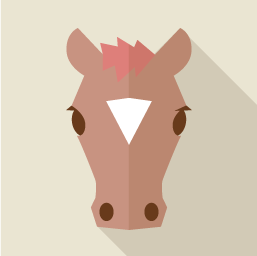 学び
学び 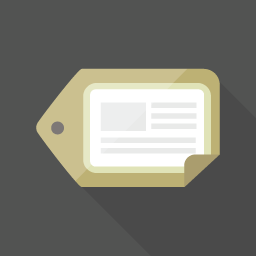 学び
学び  学び
学び