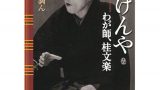若旦那は苦労知らず
みなさん、こんにちは。
アマチュア落語家でブロガーのすい喬です。
お暑くなりました。
昨日、今日の暑さはもう赤道直下そのもの。
40度近いなんて言われると、そんな気温があるのかと思わず疑いたくなります。
この国は完全に亜熱帯になりました。
地球温暖化はさまざまな被害をもたらしていますが、コロナウィルスとのコラボだけはご勘弁です。
今はエアコンの中でじっとしている以外に方法はありません。
炎天下で仕事をしている方をみていると、本当に頭が下がります。
暑い時に思い出す落語といえば、「これ1本」だけ。
「船徳」です。

ご存知ですよね。
若旦那噺は数あれど、これくらい色気があって笑いのとれる噺はそうありません。
世間知らずの若旦那が船宿の2階に居候して船頭になるという落語です。
当然のことながら失敗ばかり。
しかし一生懸命に船を漕ぐ姿にはなんともいえない風情があります。
気の毒なのはその船に乗った2人の客です。
この若旦那との掛け合いも実によろしい。
どうしてもやってみたくなる噺なのです。
とはいえ、船を漕ぐのですから、きちんとした仕草が大切。
扇子1本をさおにしたり艪にしたり、それらしく見せなければなりません。
扇子を少し広げて船を漕ぐところの味わいがきちん出せないと、この噺はウソになってしまいます。
どうしてもこの噺を夏の落語会にかけたくて、2か月くらい稽古しました。
懐かしいですね。
本番でも汗だくになってやりました。

あれからもう2年ほど過ぎています。
今年は夏の「あさがお寄席」が開けませんので、この噺はまた来年でしょうか。
それもできるんですかね。
みんなでZoom寄席をやろうなんて話も持ち上がっている昨今です。
新型コロナウィルスの影響はどこまでも深刻です。
桂文楽の芸
「船徳」といえば先代の文楽です。
存命中は誰もが恐れ多くてやれませんでした。
師匠が高座にあがると「船徳」という声がかかったものです。
今でもビデオが残っています。
Youtubeなどでも見られます。
1度試しにご覧ください。
文楽はきれいなおじいさんでした。
弟子の柳家小満ん『べけんや・わが師桂文楽』を読むと、この噺家の人となりがよくわかります。
こういう人を本当の芸人と言うんでしょうね。
幇間などの噺を聞いても、とても今の人にはできないと思います。
身体中に芸人の血が流れているというのでしょう。
どこを切っても桂文楽です。
たくさんの落語を稽古したそうですが、そのレパートリーはごく少なく30話くらいでした。
それを磨いて磨いて磨きぬいて高座にかけたのです。
この「船徳」には前半と後半を分ける大切なキーワードがあります。
それが「四万六千日、お暑い盛りでございます」という表現です。
この日は観音様の縁日。
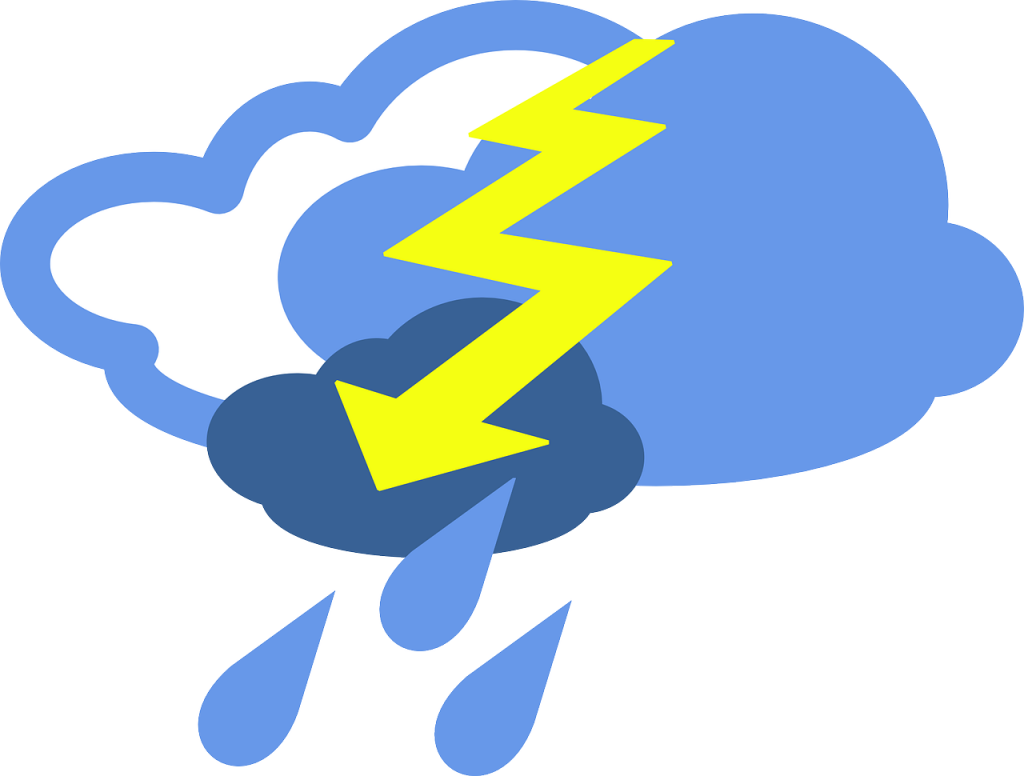
お参りをすれば4万6千日参拝したのと同じご利益があるという日です。
今のほおずき市です。
文楽師匠のちょっと疳高い声でこのフレーズを聞くと、ああ炎暑の中を観音様まで歩くのは大変だなと思います。
船に乗って楽をしようという2人の気分がよくわかるのです。
あらすじ
道楽が過ぎて勘当された若旦那の徳兵衛。
柳橋の船宿の二階に居候の身となります。
突然、自分も船頭になりたいと言い出すのです。
世間を知らない若旦那の突飛な行動に周囲がふりまわされます。
親方は大旦那に世話になっていますので、イヤとも言えません。
「若旦那、あなたみたいな細い体で、船頭なんぞになれやしませんよ」
「なれやしねえったって、おんなし人間じゃねえか、みんなにやれてなぜ俺にできねえんだ」と若旦那は無鉄砲の世間知らずそのもの。
「そうかい。駄目だって言うなら、よそへ行って船頭になるよ」と親方の顔色をみます。
このあたりは駄々っ子そのものです。
仕方なく親方はそれじゃやってみなさいと諦めてしまいます。
若い者を呼んできたものの、いつも世話になっている若旦那が突然船頭の仲間にはいるというのでお世辞をいって取り入ろうとします。
このあたりの会話は、船頭仲間の日常がみえて楽しいところです。
さてお暑い盛り。

浅草観音の四万六千日です。
船頭たちはみな仕事で出払ってしまいました。
残っているのは徳さん一人。
そこへなじみの客が、嫌がる友達を連れてやって来ます。
大桟橋まで行ってほしいと言うのです。
船宿のおかみは船頭が誰もいないと断ります。
しかしお客は柱に寄りかかって居眠りをしている徳さんを見つけるのです
断り切れずに、とうとう船を出すことになりました。
ここから若旦那の大活躍。
客を待たせてひげをあたってみたり。
舫ったままの船を出そうとしたり。
同じ所を三回も回ったり。
それでもなんとか大川まで船を出します。
しかも徳さんは土手にいた知り合いを見つけて、「竹屋のおじさん、大桟橋まで送ってきます」と声をかけます。
すると、「徳さん一人かぁい、大丈夫かぁい」なんてやりとりをする始末。
「なんかあったのかい」と客が訊くと…。
「この間、赤ん坊連れのおかみさんを川に落としてしまったんです」という返事。
川に出たものの船は石垣にぴったりとくっついたまま動きません。
徳さんは客のこうもり傘で石垣を突っつかせます。
船は離れたものの、今度はこうもり傘が石垣の間に挟まってしまいました。

暑くて汗が目に入り前が見えないので「前から船が来たらよけてください」なんて言い出します。
それでもやっと大桟橋の近くまで来たものの、浅瀬に乗り上げてしまいます。
仕方なく客が一人を背負って川の中を歩き出します。
船の方を見ると、徳さんはもう完全にグロッキー。
「おーい、大丈夫か」と声をかけると…
「お客さん、上がりましたら船頭ひとり雇ってください」
これがオチです。
若旦那噺の傑作
どうも落語に出てくる若旦那は世間知らずの代表ばかりのようですね。
代表的な噺の1つがこの「船徳」です。
これ以外には妄想系の噺が多いような気もします。
勝手に自分で夢をみて盛り上がる。
その代表例が「湯屋番」でしょうか。
湯屋に奉公に行ったのはいいのですが、突然番台に乗ることになります。
しかし男湯にしか客はいません。
そのうち、若旦那の妄想が始まります。
いつものやたらともてるというパターンです。
最後は番台から落っこちて終わりです。
他にはもっと深刻な「唐茄子屋政談」。
こちらは人情噺です。
人の苦労がやっとわかるようになる若旦那改心の一幕ものです。
どうぞいろいろな噺を味わってください。
落語はいいですよ。
今回も最後までおつきあいいただきありがとうございました。