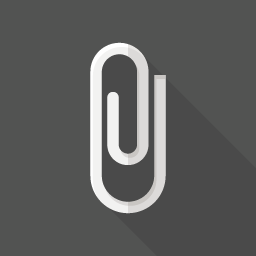 本
本 【俳句・縮み志向の極致】松尾芭蕉の俳句に宿る美の魂を知る【日光】
松尾芭蕉の『奥の細道』は俳句の世界を大きくかえました。旅行記でありながら、そこには創作者の魂が宿っていたのです。多くの人々に今も感銘を与えています。今回は日光の段を扱います。その地で詠んだ俳句を味読してください。
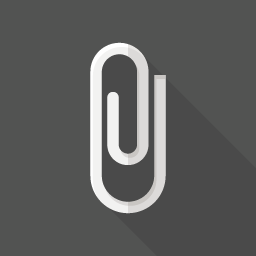 本
本  本
本  本
本 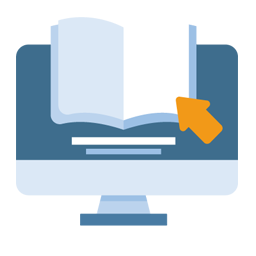 本
本 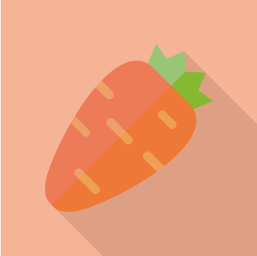 本
本 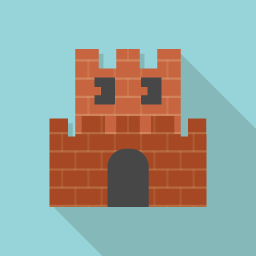 本
本  本
本  本
本  本
本  本
本 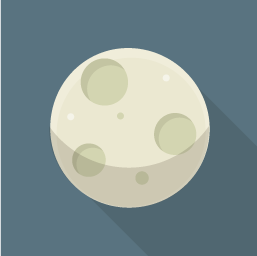 本
本  本
本 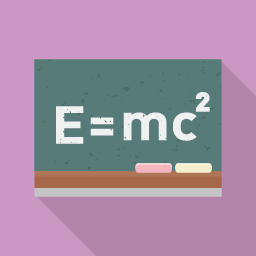 本
本  本
本  本
本  本
本