柳田國男
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は日本民俗学の父と呼ばれている柳田國男について、少し考えてみたいと思います。
昨今はあまり民俗学という言葉を聞かなくなりました。
AIの技術が進み、日本人の生活も大きく変化したからです。
この国が太古以来、農業を中心してきたなどということも、今や忘れ去られつつあるのかもしれません。
第一次産業に携わる人々も高齢化し、農業は法人化の波の中にあります。
機械を導入し、農地を広げて、一気に収穫をめざすというスタイルでないと、外国産のものに打ち勝つことはできません。
自然災害の多いこの国で、農業一本で生き抜くことは至難の業なのです。
民俗学をつくりあげた柳田國男という人の名前も、次第に忘れ去られていくのでしょうか。
あるいはふたたび、取り上げられる日がくるのか。
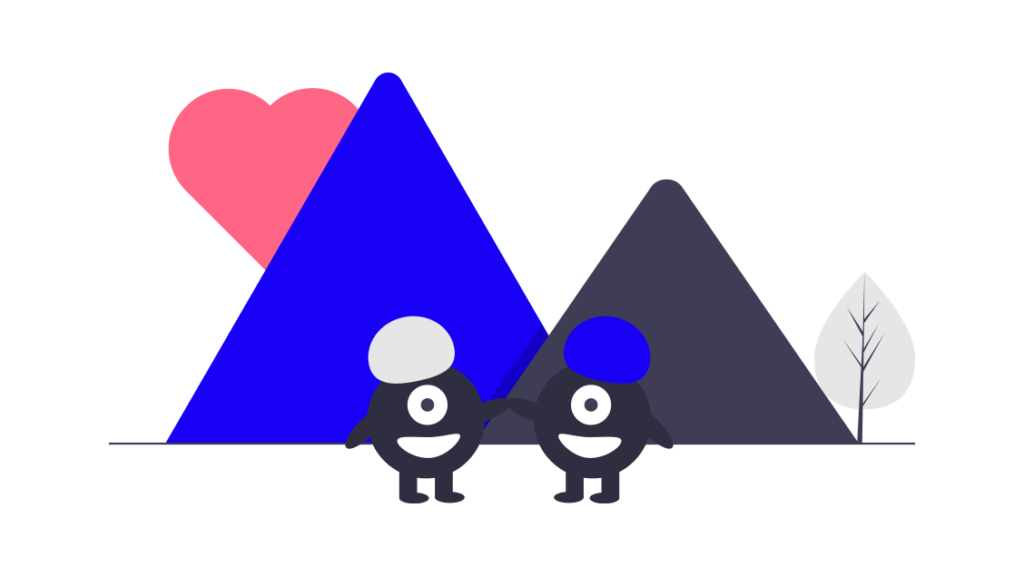
それもこれも、これからの日本の進路に負うところが大きいと思われます。
彼は農政学を学び、農商務省の官僚となった後、講演旅行などで東北を中心に回りました。
そこで見たものは、日本人の根幹に触れる生きざまだったのです。
もっとも有名な著書『遠野物語』は日本の昔話を代表する作品です。
岩手県遠野に古くからある話を、聞き集めて一冊の本にしました。
ここから調査活動に対する勢いが増したのです。
日本各地を歩き、海の道、山の道が日本各地にあることをつきとめました。
多くの研究者が彼の足跡を追い、民俗学は日本が産んだ大切な研究分野になったのです。
日本人はどこから来たのか。
どのような日常を過ごし、何を信じて生きてきたのか。
その中枢にある考え方はどのようなものか。
今も研究は続いています。
しかし時代の流れの中で、次第に現代人の感覚からは遠いものになりつつあるのも事実なのです。
常民の思想
この本も柳田國男の著作としては大変に有名なものです。
『遠野物語』とセットになっていることが多いです。
それだけ象徴的な作品といえるのでしょう。
その最初に載せられているのが「山に埋もれたる人生ある事」です。
今までに何度読んだか覚えていません。
そのたびに新鮮な驚きを感じます。
本当にこのようにして日本人が生きてきたという事実が重いです。
たくさんの人に会い、聞き書きをしてきたことを文章にまとめたものです。
誰も覚えていないだろうから、ここにかきとめておくと前書きがあります。
人間の暮らしは、きっとこのようなことの集大成なのでしょう。
ある事実があったとしても、それを留めておかなければ、なかったことになります。
戦争の記録もそうですね。

『アンネの日記』がなかったなら、ナチス支配下におけるユダヤ人の逃亡生活など、知る由もありませんでした。
あらゆることが歴史の谷間から滑り落ちていきます。
権力者は自分に都合のいい事実を積み重ねて、歴史を作ります。
しかし柳田國男が説いた「常民」という思想はそうではありません。
どこにでもいるごく普通の市井の民はどのように暮らしてきたのか。
そこにこそ、本当の事実があります。
それはけっして形を整えた美しいものではありません。
もっと猥雑なものです。
だからこそ、価値があるともいえるのではありませんか。
『山の人生』は「青空文庫」で読めます。
最初の部分を抜き書きします。
ここに示された現実を読んでみてください。
これが日本人の暮らしだったのです。
山の人生
今では記憶している者が、私の外には一人もあるまい。
三十年あまり前、世間のひどく不景気であった年に、西美濃の山の中で炭を焼く五十ばかりの男が、子供を二人まで、鉞で斫り殺したことがあった。
女房はとくに死んで、あとには十三になる男の子が一人あった。
そこへどうした事情であったか、同じ歳くらいの小娘を貰ってきて、山の炭焼小屋で一緒に育てていた。
その子たちの名前はもう私も忘れてしまった。
何としても炭は売れず、何度里へ降りても、いつも一合の米も手に入らなかった。
最後の日にも空手で戻ってきて、飢えきっている小さい者の顔を見るのがつらさに、すっと小屋の奥へ入って昼寝をしてしまった。
眼がさめて見ると、小屋の口一ぱいに夕日がさしていた。
秋の末の事であったという。
二人の子供がその日当りのところにしゃがんで、頻りに何かしているので、傍へ行って見たら一生懸命に仕事に使う大きな斧を磨いでいた。
阿爺、これでわしたちを殺してくれといったそうである。
そうして入口の材木を枕にして、二人ながら仰向けに寝たそうである。
それを見るとくらくらとして、前後の考えもなく二人の首を打ち落してしまった。
それで自分は死ぬことができなくて、やがて捕えられて牢に入れられた。
この親爺がもう六十近くなってから、特赦を受けて世の中へ出てきたのである。
そうしてそれからどうなったか、すぐにまた分らなくなってしまった。

また同じ頃、美濃とは遙かに隔たった九州の或る町の囚獄に、謀殺罪で十二年の刑に服していた三十あまりの女性が、同じような悲しい運命のもとに活きていた。
ある山奥の村に生まれ、男を持ったが親たちが許さぬので逃げた。
子供ができて後に生活が苦しくなり、恥を忍んで郷里に還ってみると、身寄りの者は知らぬうちに死んでいて、笑い嘲ける人ばかり多かった。
すごすごと再び浮世に出て行こうとしたが、男の方は病身者で、とても働ける見込みはなかった。
大きな滝の上の小路を、親子三人で通るときに、もう死のうじゃないかと、三人の身体を、帯で一つに縛りつけて、高い樹の隙間から、淵を目がけて飛びこんだ。
数時間ののちに、女房が自然と正気に復った時には、夫も死ねなかったものとみえて、濡れた衣服で岸に上って、傍の老樹の枝に首を吊って自ら縊れており、赤ん坊は滝壺の上の梢に引懸って死んでいたという話である。
こうして女一人だけが、意味もなしに生き残ってしまった。
このあわれな女も牢を出てから、すでに年久しく消息が絶えている。
多分はどこかの村の隅に、まだ抜け殻のような存在を続けていることであろう。
現実の重さ
「事実は小説よりも奇なり」とはよく言ったものです。
子供が見た夕陽の色がそこにあるようです。
意味もなく生き残った女性も哀れです。

空想で描いて見る世界よりも、現実は遥かに行き、そして深いのです。
彼は序文のかわりにこの2つのことを書き残して置くと示しています。
現在もこの事件と同じように、人間は日々を生きています。
そこにあらわれる種々のできごとは、その前日と同じように目の前を過ぎていくのです。
ウクライナにおいても然りです。
学ぶということは想像力と無縁ではありません。
たかが想像力、されど想像力なのです。
どこまでいっても終わりがない人の世であるからこそ、柳田國男のような研究者がいたことを重く考えなければないないでしょう。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


