人間関係力
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は教育学者、齋藤孝氏の本を読んだ感想を書きます。
本当にこの人は勉強家ですね。
頭が下がります。
非常にテリトリーが広いのです。
さらにいえば、文章が実に読みやすい。
学者の書く文はとかくかたくて、回りくどいものが殆どです。
しかし彼の文にはそういう臭みが全くありません。
一文一義を実践すれば、このタイプの文章になるという、実験結果のようなものです。
小論文の勉強にもなりますね。
文体をまねしていくと、どこにその秘密があるのかわかるようになります。
図書館でも、彼の本があると、必ず借りることにしています。
著書の中で最も有名なのは『声に出して読みたい日本語』です。

学校の授業の中でも、随分使われているようです。
日本を代表する名文を、古典や近代の文学から集めてアンソロジーにしたものです。
語調の整った文章は、歌舞伎の台詞や、落語の会話などにもあります。
いろいろなところに目配りがきいているため、本当に声に出してみると、いい気持になります。
その筆者が、15年ほど前に上梓したのが、この本です。
人間関係こそがあらゆるストレスの元凶だと彼は言います。
面白い記述があるので、「まえがき」のところを少しだけご紹介しましょう。
人間こそがストレスの原因
人生を泳ぐことに喩えるなら、人間関係は水である。
前へ進む推進力は、水をしっかり捉えて引き寄せることで生まれる。
人生をプラス方向にぐんぐん推し進めていくには、人間関係をしっかり捕まえて自分に引き寄せていくことが必要だ。
しかし、水にはもう1つの側面がある。
それは、水が抵抗になるということだ。
水の抵抗によって、前への推進力が殺される。
人間関係は、人生を生きていく上での最大の抵抗力である。
私たちがストレスを感じる時の多くは、人間関係が絡んでいる。
—————————-
この文章の内容を否定する人は誰もいないでしょう。
どんなに他人がいい職場だと言っても、人間関係がうまくいかなくなると、長くはいられないものです。
人間関係力がまさに必要な所以だとも言えますね。
水が油のように粘りつく時、その抵抗力に誰も逆らえなくなります。
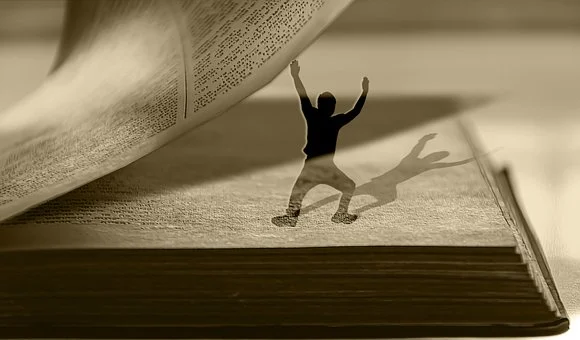
結果として、その場に長くはいられません。
ではどうしたらいいのか。
これが最大の問題です。
登校拒否の生徒をみていると、彼らは人間関係の渦の中で呻いています。
どうしても教室に入れない。
たったの1歩ですが、先に進まないのです。
そこにある人間の渦の中に安心して入ることができません。
それは職場も同じです。
日本はタテ社会の国です。
職制の壁は厚いです。
男女のジェンダーギャップもあります。
コミュニケーションを円滑にとることが、いかに難しいか。
この本はたくさんの賢人たちが、どうやって、人間関係力を高めてきたのかという軌跡を綴っています。
33人の先人たちをいくつかのカテゴリーに分けているのもユニークですね。
「ビジネスに効く人間関係力」「プライベートを円滑にする人間関係力」「他人に頼らない人間関係力」の3つです。
人の話を聞く
33人の中で、ほくが最も苦手とするワザを持つ人の話が身に沁みました。
それが民俗学者、宮本常一(つねいち)のケースです。
代表的な著作は『忘れられた日本人』です。
いい本です。
今までに何度も読みました。
ご存知ですか、この人のことを。
民俗学はフィールドワークをもっとも大切にする学問領域です。
彼は学生時代に柳田國男の研究に没頭しました。
1981年に亡くなるまでの50年間、日本各地の民家に泊めてもらっては、古老たちの話を聞き続けたのです。
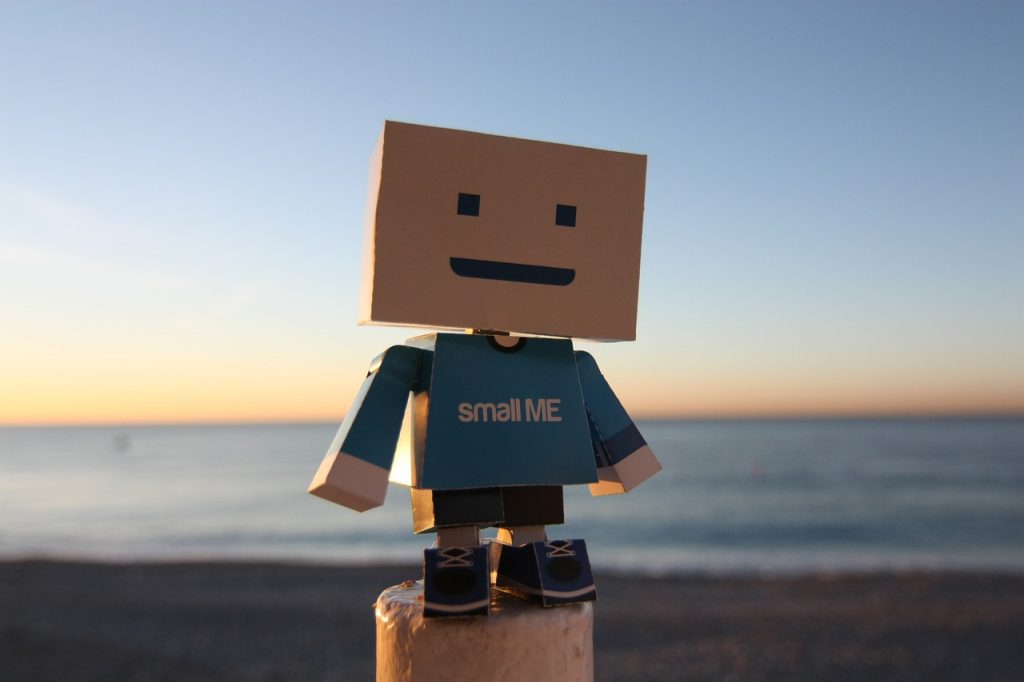
けっして派手な作業ではありません。
それだけに学問の世界では傍流に甘んじたのです。
彼の膨大な資料は、日本人がどのようにして生きてきたのかという生々しい内容に満ちています。
たとえば「対馬にて」という章では衆議一決をはかるための方法が示されています。
どれほど時間がかかっても、全員が納得するまで何日かもかけて話し合う、という途方もない方法がとられていました。
村落共同体の基本的な構図がみごとに描写されています。
人は話したいことを持っている
「聞く力」という言葉は以前からよく耳にしますね。
政治家も教育者も、誰も彼もが同じ表現を使います。
しかし多くの人が、本当に聞く力を持っているのかどうか。
つい疑念をもってしまいます。
宮本常一は名刺を出したりして、人の話を聞くことはありませんでした。
どうやって人には話さないような内容のことを聞きだしたのか。
これが人間関係力のヒントになります。
彼の言によれば、「人はみんな話したいことを持っている」というのです。
「その人が話したいことをその人が話している時は、じっと聞いたらいい」
これが全てです。
そんなことはあたりまえじゃないか。
誰もがそう考えるかもしれません。
しかしこれが実に難しいのです。
余計な質問を一切しない。
ただ頷きながら聞いていくのです。

傾聴という言葉がありますね。
あれに似ています。
この前、動画で面接官が必ず合格点を出す入社試験の話をしていました。
それによれば、面接官の質問にただ答えるのではなく、むしろ逆に彼らが抱く思いを聞きだすことのできる学生は、即合格なのだそうです。
そこまで相手の話を聞きたいとする熱意が伝わるというワケです。
とにかくどこまで相手の話を聞くことができるのか。
相手が気持ちよく語ってくれるほどの相手なら、その人間関係は円滑なのです。
おそらく当人同士の関係は順調で、両者がいつもそばにいて欲しい人になれるはずです。
理屈ではまさにその通りなのです。
しかしそれがなかなか簡単にはできないのです。
うまくいくようになるには、相当の経験が必要でしょうね。
あるいは深みのある人格の形成がなくては、とうてい達しえない境地といえます。
それでも聞く力を養うという根本の目標を忘れてはいけません。
そこにこそ、人間関係を円滑にするヒミツが隠されているのです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


