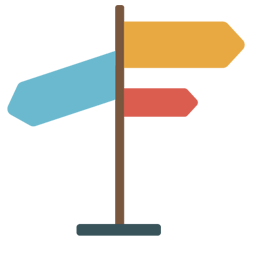蹴鞠と連歌
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は連歌論について学びます。
連歌についてはご存知でしょうね。
短歌の上の句と下の句にあたる表現を、1人または複数で交互に詠み連ねていく詩歌のかたちです。
連歌は万葉集の頃からあります。
鎌倉時代以後は百韻が通常の形になりました。
有名な「水無瀬三吟百韻」は高校でも習います。
すばらしいです。
これは室町時代、宗祇とその高弟、肖柏、宗長の3人が水無瀬神宮に奉納した歌です。
百韻連歌の模範とされています。
最初のところだけ書き抜いておきましょう。
1 雪ながら山もとかすむ夕べかな (宗祇)
2 行く水とほく梅にほふ里 (肖柏)
3 川かぜに一むら柳春みえて (宋長)
4 舟さすおともしるき明けがた (宗祇)
5 月は猶霧わたる夜にのこるらん (肖柏)
6 霜おく野はら秋はくれけり (宋長)
7 なく虫の心ともなく草かれて (宗祇)
8 垣ねをとへばあらはなる道 (肖柏)
室町末期には俳諧の連歌が興り、やがて形が洗練されて、俳諧として枝分かれしていったのです。
『筑波問答』は連歌論の本です。
作者は二条良基(よしもと)。
南北朝時代の公卿で、連歌の大成者でもあります。
『菟玖波集』(つくばしゅう)を編集したことで知られています。
1357年から1372年の間に成立したと言われています。
良基と筑波に住む老翁との問答形式の形をとり、連歌の起源や歴史、読み方や作法などが説かれています。
連歌論とは
内容はどんなものなのでしょうか。
連歌を論じるというのですから、かなり感覚的なのか、あるいは論理的なのかと推察してしまいます。
ところが、この本はなぜか蹴鞠の話から始まるのです。
蹴鞠を教える際の話や仏が教えを説く際の話が、いくつも登場します。
これが連歌論とどのようにつながっていくのかを読み取るのが、この本の主題となります。
登場人物は難波の三位入道、難波宗緒です。
鎌倉時代末から室町時代初めにかけての蹴鞠の名人でした。
その彼がどのように蹴鞠の指導をしたのかというのは、大いに関心のあるところです。
三位入道によれば、蹴鞠も仏が法を説くのも連歌もみな同じだというのです。
人の持ち前の性質に応じて指導することの大切さ、上手な師について学ぶことの大切さを読み取ることがポイントになります。
蹴鞠の具体的な練習の仕方が示してあります。
しかしそれが教える相手によって千差万別なのです。
ここからが、二条良基の真骨頂です。
彼は言います。
連歌の稽古の仕方として、最も大切なのは、上手な人の指導を受けるべきだということです。
指導者は相手の性質を見抜いて、その人にあった方法で稽古をしてくれます。
だからこそ、上手な人につかなくてはいけません。
特に思案をするタイプの人とそうでない人とでは、指導法が全く違うというのです。
本文
昔、難波の三位入道殿、人に鞠を教へ給ひしを問ひを奉りしに、「手持ちはいかほどにも開きたるがよき。」と教へられき。
その次の日、またあらぬ人に会ひて、
「鞠の手持ちやう、いかほどにもすわりたるよき。」と仰せられき。
これはその人の気に対して教へ変へられ侍るにや。
後日に尋ね申し侍りければ、
「そのことに侍り。先の人は手がすわりたりしほどに、広げたるが本にてあると教へ、後の人は手の広ごり足れば、すわりたるが本にてあると申せしなり。」
仏の衆生の気に対してよろづの法を説き給へるも、みなかくのごとし。
連歌も、あまりにどこともなからん人には、案じたるがよきと申すべし。
沈みたらん人には、案ぜぬがよきと教ふべきなり。
ただし、二つに取れば、早くてどこともなき中に、無上の堪能はおのづから出で来べきなり。
沈み果てたらん人は、うるはしき上手にはなるまじきにや。
ただ、上手に初めより添ひて、心・詞を学び給ふべし。
下手に添ひてわろき心の執着しぬれば、すべて直りがたきことなり。
初心のほど、ゆめゆめ万葉以下の古きことを好み給ふべからず。
ただ、あさあさとしたる句のやすやすとしたるを、詞やさしく句軽にし給ふべきなり。
何とがなおもしろからんと案じて給ふこと、ゆめゆめあるべからず。
現代語訳
昔、難波の三位入道殿(難波宗緒)が、人に鞠を教えていらっしゃるところを(私がそばで)うかがっていたところ、
「手の構え方は、できるだけ開いているのがよい。」と教えておられました。
その次の日、(難波入道が)また別の人に会って、
「鞠の手の構え方は、できるだけ閉じたほうがよい。」とおっしゃったのです。
これはその人の個性に合わせて、全く違う教られ方をしたのでしょうか。
後日、(私が難波入道に)お尋ね申しあげたところ、
「その通りですよ。前の人は手が閉じていたので、広げるのが基本だと教え、後の人は手が広がっていたので、閉じるのが基本だと申したのです。」とのことでした。
仏が衆生の個性に合わせて、色々な法をお説きになったのも、みんなこれと同じなのです。
連歌も、あまり深く考えようとしない人には、よく考えるのがいいと言うべきです。
考え込んでしまう人には、あまり考えない方がいいと教えるべきなのです。
ただし、2つ(のタイプのうち)のどちらかを取るとすれば、早く、あまり考え込まずに詠むタイプの中に、この上ない名人が、自然に出て来るものです。
あまりにも深く考え込む人は、立派な名人には なれないのではないでしょうか。
ひたすら、名人に初めからついて、心と表現を学ばれるのがよい方法です。
下手な人について、うまくない心が染み付いてしまったら、すべて直りにくくなってしまうものなのです。
初心のうちは、決して『万葉集』などの古典にある古い言い回しを好んではいけません。
ただ、あっさりとした句でやわらかな感じのするものを、表現をさらにやさしくして心地のよい句にするべきでしょう。
何とかして趣のあるものにしようなどと考え込まれることなどは、あってはならないことなのです。
ユニークな視点
ここに示されている指導法は、ある意味特異ですね。
というのも通常の正攻法とは呼べないものばかりです。
たとえば連歌をつくる際に、具体的に注意すべきことは何かということを考えてみましょう。
➀古歌の言葉を用いない
②無難な句を軽快に詠む
③面白さを狙わない
これを追求していくと、歌を詠むのが早くて特にすぐれた点がない者の中から、達人があらわれてくるということになります。
ここで、歌詠みの道を芸道と同じレベルでは考えてみてはどうでしょうか。
この論点はよく舞台俳優などが口にする「板数」に近いもののような気もします。
最初はそれほどでもなかった人が、急に「化ける」ということはあります。
急に腕が上がるのです。
自分より格上の人に交じっていることが大切なのです。
上手の人の傍らにいることの意味ははかり知れないのです。
そこから心や言葉の使い方を自然に学んでいくのです。
それは無理に学習するというのではなく、むしろ染み込んでいくという実感に近いのではないでしょうか。
詠むのがはやく、特にすぐれた点がない人の中から、達人として評価される人が出てくると二条良基は考えていたようです。
実にユニークな考え方ですね。
仏が生き物の性質に対応していろいろな教えを説いているのも、これと似ているのでしょうか。
これがやがて歌の道につながるのです。
あるいは全ての道につながると考えた方がいいのかもしれません。
結局はその人の殻を破るまで、稽古は永遠に続くと考えるべきなのです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。