芋粥
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は芥川龍之介の短編『芋粥』(いもがゆ)を読みます。
何もすることがない時などに、時々彼の創作を読むことがあります。
どれも短く、警句に満ちていますからね。
ピリッとした読後感がやめられないのです。
初期の芥川は古典に取材した小説が多いです。
彼は特に『今昔物語』を好みました。
説話には、人間臭さがあります。
昔の人がずっと語り継いできた背景には、一種の教訓として、身に沁みているという背景があるのです。
誰もが人生を間違えたくはありません。
やり直しが簡単にきくほど、長くはありませんしね。
しかし、ちょっといい気になっていると、足を掬われます。
そういう意味で説話の中にあるエッセンスは、短編作家にとって恰好のものだったに違いありません。
あなたも子供の頃に、彼の小説を手にとったのではありませんか。
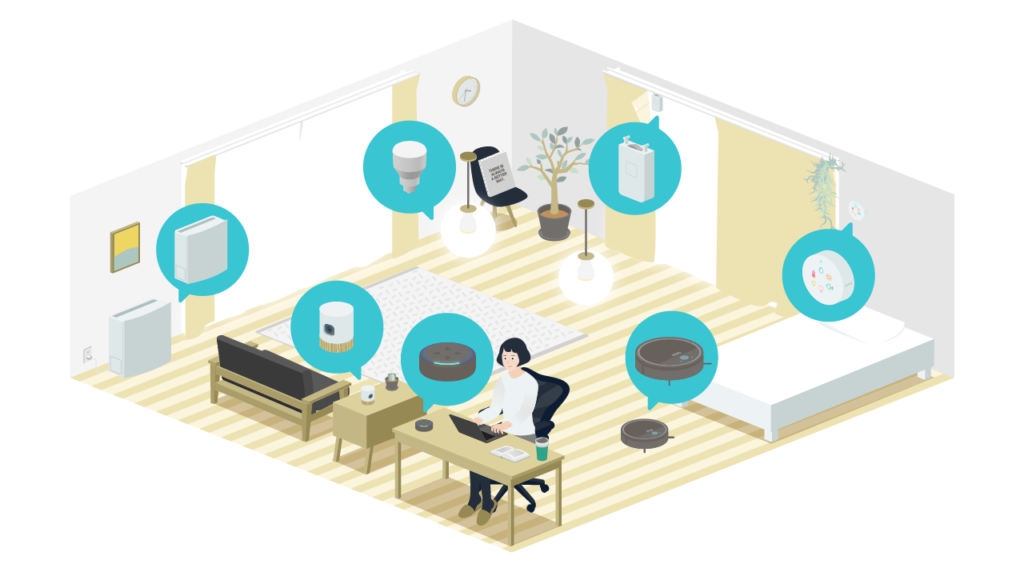
今でも少年少女用の文学全集の中には、芥川の初期の作品がたくさん所収されています。
名作と呼ばれるものも数多いです。
『羅生門』『鼻』『芋粥』『蜘蛛の糸』『河童』などは、誰もが1度は読んでいるはずです。
高校でも『羅生門』は必ず取り扱います。
『地獄変』などは『今昔物語』を題材にしたものの代表です。
こちらは古文の授業で習います。
『絵仏師良秀』というタイトルでよく知られている作品です。
芥川は人間の心理の襞を描くのが非常に得意な作家でした。
『鼻』などはその代表でしょうね。
こういうことは確かにあると、誰もが納得させられてしまうのです。
欲望は無限
人間というのは厄介な生き物だと最近、しみじみ思うようになりました。
本当に何が欲しいのか、よくわかりません。
お金があればなんでも買えるかといえば、そうとばかりも言い切れないところがあります。
健康などはその代表でしょうね。
しかしそれも金銭でなんとかなるという人もいます。
確かに現代は経済で回っています。
やはり目の前に積まれた現金は魅力的です。
さらに名誉も地位も欲しい。
立派な家にも住みたいし、おいしいものもお腹いっぱい食べたい。
高級なお酒も飲みたいし、いい車にも乗りたい。
基本的には金銭があればかなえられることばかりです。

しかし億万長者になったデイトレーダーの動画などをみていても、あまり幸福の絶頂にいるようにはみえません。
人間にとって何が本当に幸せなのか。
時に考え込んでしまいます。
そんな時、ふと立ち止まって周囲を見回してみる必要があるのかもしれません。
芥川が書いたのは、人間の欲望そのものでした。
あれが欲しい、これが欲しいと言っていた段階と、それが手にはいった時点で人間はどう変化するのか。
この小説の設定はそうした欲望の果てには何があるのかという、ある意味シビアなテーマなのです。
短編の名作
『芋粥』は1916年に発表された芥川龍之介の短編小説です。
時代は平安時代の元慶か、仁和年間の頃の話です。
主人公の男は、摂政・藤原基経の役所に勤務する、年齢も40歳を越えた小役人なのです。
見た目も貧相で、日ごろ同僚からも馬鹿にされ、道で遊ぶ子供に罵られても笑ってごまかす、情けない日常を送っています。
しかし彼には夢が1つだけありました。
それは芋粥を、飽きるほど食べてみたいというささやかな願いだったのです。
そんな話をある時、ふと口にしたのがこの話のきっかけです。
たまたま藤原利仁が、ならば私がご馳走しましょうというワケで、彼に連れらて領地の敦賀に出向きます。
その途中であらわれた狐に向かって、藤原利仁はたくさんの芋を集め、屋敷に届けよと言いつけるのです。

家臣たちは領主の伝言を狐が言うのに驚きあきれながら、それでも領地をまわって農民に芋を献上させます。
ついてその時がきました。
利仁の館で用意された、大鍋に用意された芋粥は、とても食べきれる量ではありませんでした。
男はしばらくすると、食欲が失せ、芋粥を2度とみたくもないという心境に変化していったというワケです。
芋粥が欲しくて欲しくてたまらなかった男が、藤原利仁のおかげで芋粥を食べられることになったところまでが前段です。
その後、次第に食べたいという気持ちがみるみる消えていく部分が、後段です。
男にとって、年に1度、客が来た時にだけ出されるのが芋粥だったのです。
それが唯一の楽しみだったのにも関わらず、ここまで変わってしまうのは悲しいですね。
人間は、どこまでいけば満足する生き物なのでしょうか。
自分の欲望のために一生を捧げるのも1つの生き方かもしれません。
しかしどこかに空しさが漂います。
どこまで行けば
この話の面白さは、最初芋粥を腹いっぱい食べさせてやるというので、男が利仁のあとをついていくところです。
男と利仁は馬に乗って東山の近くにある湯を目指していきます。
しかし栗田口を過ぎると、実は山科まで行くと言われ、そのまま三井寺まで来てしまうのです。
ところがどうもそこが目的地ではないようでした。
とうとう、利仁は自分の嫁の父親が住む敦賀に向かっているのだと答えます。
最初はちょっとそこまでという気持ちでしたが、男は大変な旅をせざるを得ないことになりました。
それも腹いっぱい食べられるという、芋粥が目的の旅なのです。
敦賀までの道のりは遠く、盗賊に襲われる可能性もあります。
男は次第に怖くなりました。
ところが利仁は暢気なものです。
とにかくついてこいというだけです。
途中で狐を捕まえると、こんなことを告げます。

わしからの命令だと言って、家来に途中の高島まで馬を二頭連れてくるように言えというのです。
敦賀の者に必ず伝えろと命令をしてから、利仁は再び狐を野に放ちます。
翌日、利仁の命令通り家来が出迎えに出てきました。
ここから芋粥のシーンにすぐ移るのかと思うと、そうではありません。
翌朝、目を覚ますと屋敷の前に、山のように積まれた芋がありました。
農民たちに急遽、納めさせたものなのです。
それが芋粥へと調理されていく様子を想像してください。
大きな鍋に、山のような芋粥がつくられていきます
そのうちに、男は食べる気を失ってしまいました。
食べる前から満腹になってしまったのです。
しばらくすると、利仁が遣わした狐までが現れます。
その狐にも芋粥を食わせてやるのです。
男は敦賀に来る前の自分を懐かしく振り返りました。
芋粥を飽きるまで食べたいと思った以前の自分が、1番の幸福者であったことを知ったのです。
芥川龍之介はこの小説を書きながら、何を思ったのでしょうか。
それが知りたいですね。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


