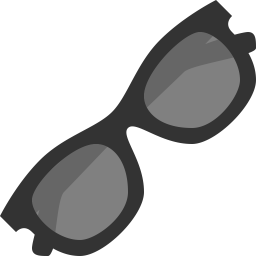演出家ニナガワ
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
演出家、蜷川幸雄が亡くなってから5年の歳月が経ちました。
亡くなった後の時間の流れは早いものですね。
この演出家は最初、俳優として活動の場をひろげていきました。
いわゆる小劇場運動の時代です。
俳優としての演技にダメ出しをしたのは、太地喜和子でした。
彼女は天性の女優ですからね。
その一言一言が胸にささったのです。
自分の進む道を演出一本に決めた瞬間でした。
彼はそれまでのアングラ風の役をすべてご和算にしました。
1970年代半ばから商業演劇に活動の場を移しダイナミックな舞台を次々と作り出していきます。

その中心はなんといってもシェイクスピアとギリシャ悲劇でした。
やはり最後はここに戻るのかもしれません。
人間の持っているあらゆる感情が舞台に表現されていますからね。
彼はアッという間に世界のニナガワの名を欲しいままにしました。
24時間、芝居のことしか頭になかったのでしょう。
他のことには全く神経がいきわたらない才人でした。
気にいらないことがあると、突然そばにあった灰皿を投げつけたりすることがよくあったと言います。
罵倒されることもしばしばだったとか。
しかしそけだけで人はついてきません。
その背後にある芝居を愛する気持ちに人一倍のものがあったのです。
本当に真剣に悩み抜いて、演技に息づまると必ず相談にのってくれました。
それがどれほど若い俳優たちの信用を得たかは、彼らの活躍ぶりをみればよくわかります。
意表をつく演出
蜷川幸雄の『演出術』を読んだのは隋分前のことです。
大変分厚い本でしたが、読み始めたら、止まらなくなりました。
これは彼の苦闘の記録です。
自分でも本当は言いたくなかったことをいつの間にか、誘導尋問にあって話してしまったというのが真相でしょう。
自分の負の部分を語るのは誰にとってもつらいことですが、逆にいえば、そこに創作の秘密が宿っているわけです。
内容は前作の『千のナイフ、千の目』を大きく突き抜けています。
実際一つの芝居を想像力だけでつくりあげていく仕事というのは、厳しいものです。
イメージが枯渇しているのを知っているのも本人です。
失敗した舞台を見続けなければならないのもまさに本人自身なのです。
彼は現代人劇場と櫻社解散の経緯を初めてここで語っています。
しかもそのことを今も引きずって舞台造りの原点にしていることも告白しています。
仲間に裏切り者と罵られ、つらい言葉を浴びたことが終生忘れられないのでしょう。
商業演劇へ行くことは当時の役者たちにとって背信行為そのものだったのです。
石橋蓮司や蟹江敬三などとともに行う芝居の拠点にしていたアートシアター新宿文化は小劇場でした。
劇作家清水邦夫との接点は時代への参加(アンガージュマン)だったのです。
しかしそこから一気に、帝国劇場や日生劇場へ行くのは、彼らにとって何を意味していたか十分に理解できます。

体制に擦り寄った男として、許せないという意識は、現在とは比べものにならなかったでしょう。
精神的には苦しい時代が続きます。
しかしシェイクスピアの『リア王』やソフォクレスの『オイディプス』、エウリピデスの『王女メディア』など活躍の舞台は一気に広がりました。
もう蜷川はいらないという気配が、濃厚に立ちこめた時期もあります。
この窮地を救ったのは唐十郎でした。
『唐版滝の白糸』『下谷万年町物語』という2作で、蜷川は復活の兆しをみせます。
その後は秋元松代の『近松心中物語』や『元禄港歌』、樋口一葉『にごり江』と帝劇での仕事が続きました。
しかし彼はこの頃の芝居をもう見たくないといいます。
自分の中にある様式へのこだわりを突き抜け切れていないと考えているようです。
いずれも再演を重ね、定評のある舞台ですが、今度やるときはもっと無名の役者で試みたいとも語っています。
しかし平幹二郎と太地喜和子との道行きのシーンは圧巻でした。
今も目に焼き付いていて離れません。
歌舞伎につきすぎてはいけないし、しかしそこからなかなか離れられないというのがこの時期の演出の難しさではなかったでしょうか。
それを超えるためには次の世代を待たなければなりませんでした。
ベニサンピット
この後はやはりベニサン・ピットでの公演が大きな意味を持ちました。
その間何度も外国公演をし、「ニナガワ」の名声は自分とは違うところで進んでいきます。
しかし彼が地に足のついた活動を行うために作り出した蜷川カンパニーは精神の拠り所であったと思われます。
ベニサンは地下鉄都営線森下という不思議な場所にありました。
もともと染色工場の跡地です。
芭蕉庵のそばといったらわかるでしょうか。
近くには両国もあります。
相撲部屋がいくつもあるところです。
多くの芝居がここで稽古され、ぼく自身、なんどか訪ねたこともありました。
その一角にあるのがこの小さな劇場です。
彼の芝居で一番多く見たのは『王女メディア』ではないでしょうか。

群衆をコロスとしてうまく使うことを彼は覚えました。
しかし批評家にそのことを言われると、次からは使わないという荒技をしてみせたりもしました。
『マクベス』を仏壇をイメージした舞台でやるとか、『テンペスト』を能舞台の背景の中で公演したりもしました。
そのアイデアはまったくユニークなものです。
しかし彼の根元にあるのはやはり昔の仲間を許せるのかという点につきるのでしょう。
今までほとんどが失敗作だったという彼にとって、絶望しか傍にはないと断言しています。
しかし手を抜かないで一生懸命やっていく中で、その積み重ねが叙情を生み出すというのです。
ある種の清潔感に裏打ちされた叙情がかすかな救済のイメージを作り上げるものなのかもしれません。
希望を語ってもすぐに癒されるわけではないでしょう。
しかし語らずにいても熱望する心があればそれで良しとするのが蜷川幸雄の場所なのです。
高齢者の演劇
もう1つ、どうしてもここにあげておかなくてはならないのが、「さいたまゴールド・シアター」のことです。
耳にしたことがありますか。
彼は長い人生経験を積んだ人々の身体表現や感情表現を舞台に活かそうと考え始めました。
2006年4月に創設した55歳以上限定のプロ劇団の名前なのです。
最高齢80歳、平均年齢66.5歳という前代未聞の劇団でした。
メディアでも相次いで報道されました。
拠点になったのは「彩の国さいたま芸術劇場」です。
新しい演劇の可能性をどこまで伸ばせるのかというのが、その時のコンセプトでした。
彼はその前年、芸術劇場の総監督に就任していたのです。
何か新しいことをしたい。

そのために応募者全員のオーディションをすると発表したのです。
世界のニナガワがとんでもないことを始めるというので、メディアはすぐに飛びつきました。
随分ニュースになりましたね。
ドキュメンタリー番組としても取り上げられました。
団員の募集を開始したらなんと20人程度の募集に1266人の応募がありました。
約束通り、応募者全員への実技オーディションを実施したのです。
実受験者数1011人を78時間かけて選んだのです。
とんでもない話です。
実はその合格者の中にぼくの同僚で退職したばかりのS先生がいらしたのです。
これには本当に驚きましたね。
彼はよく役者に向かってこう話したと言われています。
安心しろ。必ず客席に俺がいるから。じっと見ているから。
まさにこの言葉通り、いつも客席にじっと座っていた姿を何度も見かけています。
本当に芝居のことを考えている時だけが至福だったのでしょう。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。