折々の歌
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師のすい喬です。
今回は光村図書版、中学2年の国語の教科書に載っているエッセイを取り上げます。
筆者は詩人の大岡信です。
3年ほど前に亡くなりました。
『折々の歌』はご存知ですか。
1979年から2007年までずっと朝日新聞の朝刊第1面に連載されたコラムです。
全作品が岩波新書に所収されています。
ちょっと覗いてみてください。
彼のエッセイ『詩への架橋』と並んで岩波新書の中でも異彩を放っています。
とにかく毎日でしたからね。
1度だけ御茶ノ水のお蕎麦屋さんで、彼がこのコラムの原稿を書いているところを見かけたことがあります。
スキマ時間にも仕事をしなければならないくらい多忙だったのでしょう。
その大岡信のエッセイに『言葉の力』があります。
中学生用の教材だからといって侮ってはいけません。

この随筆を読んだのは数年前のことです。
心に残りました。
内容は染色家、志村ふくみさんの話です。
彼女のことはどこかで聞いたことがあるでしょう。
草木染めの世界で知らない人はいません。
もう100歳に近い方です。
人間国宝でもあります。
エッセイストとしても有名です。
代表作は『一色一生』。
いい本です。
是非読んでみてください。
京都での話
本文を少しだけ掲載させてください。
——————————–
京都の嵯峨に住む染色家志村ふくみさんの仕事場で話していたおり、志村さんがなんとも美しい桜色に染まった糸で織った着物を見せてくれた。
そのピンクは、淡いようでいて、しかも燃えるような強さを内に秘め、華やかでしかも深く落ち着いている色だった。
その美しさは目と心を吸い込むように感じられた。
「この色は何から取り出したんですか。」
「桜からです。」
と志村さんは答えた。
素人の気安さで、私はすぐに桜の花びらを煮詰めて色を取り出したものだろうと思った。
実際はこれは桜の皮から取り出した色なのだった。
あの黒っぽいごつごつした桜の皮からこの美しいピンクの色が取れるのだという。
志村さんは続けてこう教えてくれた。
この桜色は、一年中どの季節でもとれるわけではない。
桜の花が咲く直前のころ、山の桜の皮をもらってきて染めると、こんな、上気したようなえもいわれぬ色が取り出せるのだ、と。

私はその話を聞いて、体が一瞬揺らぐような不思議な感じに襲われた。
春先、もうまもなく花となって咲き出でようとしている桜の木が、花びらだけでなく、木全体で懸命になって最上のピンクの色になろうとしている姿が、私の脳裏に揺らめいたからである。
花びらのピンクは、幹のピンクであり、樹皮のピンクであり、樹液のピンクであった。
桜は全身で春のピンクに色づいて、花びらはいわばそれらのピンクが、ほんの尖端だけ姿を出したものにすぎなかった。
考えてみればこれはまさにそのとおりで、木全体の一刻も休むことない活動の精髄が、春という時期に桜の花びらという一つの現象になるにすぎないのだった。
しかし我々の限られた視野の中では、桜の花びらに現れ出たピンクしか見えない。
たまたま志村さんのような人がそれを樹木全身の色として見せてくれると、はっと驚く。
桜の花びら
この話題は『一色一生』の中にも出てきます。
最初に読んだ時、いい話だなと思いました。
花が咲く少し前、桜の皮を剥いでぐつぐつと煮るのです。
するとあのピンク色のエッセンスが滲み出てくる。
咲いた後の桜の枝にはもう色の要素がなくなっているのです。
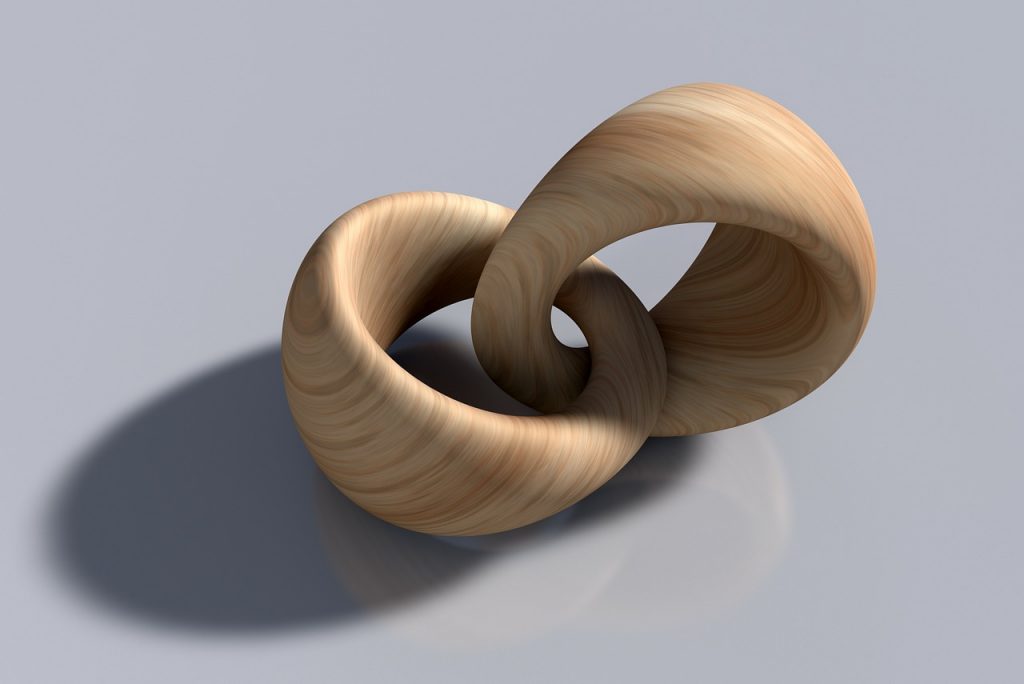
じっと冬の間我慢し続けた桜はエネルギーのすべてを花びらの中に絞り出す。
目に見えるようです。
どれくらい耐えたのかという時間が、花びらの色になって外に現れる。
現代は我慢することを潔しとしない時代です。
待つことも許さない時代です。
全てが短時間で効率よく進めば、それが最善だというのが今という時代そのものなのです。
しかし花はそうではない。
長い時間の中で次第にエネルギーを貯め、それがやがて色づく。
人々を異空間に運ぶのです。
まさに死人がその下に埋められているのではないかというくらい、非日常の世界を創り出します。
言葉の力
大岡信は志村さんの話を聞きながら、ことばの力を感じたと言います。
まさに詩の世界と同じだったのです。
たった1つの言葉を発するのにも実は長い時間が必要です。
我慢も大切です。
大きな幹や枝に言葉のエッセンスを少しずつ貯めていく。
そのエネルギーを本当に必要なところで外にあらわす。
花びらの1枚1枚はあまりにもささやかです。
本当に悲しいくらいのものでしょう。
しかしそれが集まり1つの形になった時、他者を感動させるのです。
ぼくはこの話を読みながら、つい自分に言い聞かせていたのかもしれません。
美しい言葉というものは、その幹が美しくなければ出てこないものなんですね、
どんなにその時だけうまく言い繕ってみても、人には見えてしまう。

怖ろしいことです。
人間そのものがことばの世界を背負っているといっても過言ではないでしょう。
その人が使う言葉にどんな力があるのか。
それは幹であるその人の内側にある力と比例しているのです。
美辞麗句ではダメなんでしょう。
心から出てくる響きには、それだけの鍛錬が必要なのです。
厳しいですね。
自然がここまで教えてくれるのです。
大岡信の詩魂が揺れたに違いありません。
志村ふくみのこころの造形が仄見えたのでしょう。
本当にいいエッセイだと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。


