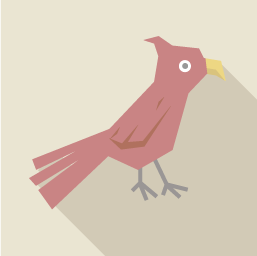壮大な歴史物語
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、ブロガーのすい喬です。
今回は有名な『大鏡』をとりあげましょう。
歴史の授業で鏡ものという言葉をならったと思います。
大鏡、今鏡、水鏡、増鏡がその代表です。
いずれも歴史物語です。
その中でも1番スケールの大きいのが今回取り上げる『大鏡』です。
高校の授業でもやります。
騙されて出家した花山院の話とか、道長の豪胆ぶりを示す逸話など、数話にわたって学びます。
覚えていますか。
作者はよくわかっていません。

成立は平安時代後期。
文徳天皇から後一条天皇までの176年間のことを記録しています。
歴史物語の中でも異彩を放つ存在です。
司馬遷の『史記』をかなり意識し、個人の歴史の集成という形で全体をまとめています。
こういう方式の書き方を紀伝体と呼んでいます。
藤原摂関政治の中でも道長の豪胆ぶりと人心掌握術はみごとなものでした。
彼の日記、『御堂関白記』を国立博物館で見たことがあります。
非常に細かな字で書きこんである様子には、神経の研ぎ澄まされた人だなという印象を持ちました。
チャンスがあったら、1度はご覧になってもいいのではないでしょうか。
大鏡はけっして藤原氏を礼賛したものではなく、その批判も大胆にしています。
その点がすぐれた魅力でもあるのです。
平安時代というと、貴族社会中心の女性の世界をイメージしがちです。
ことに紫式部と清少納言の存在が大きいですね。
しかしその一方で、男性を中心とした熾烈な権力闘争があったということを忘れてはいけません。
ここでは中納言を目前にした兄・誠信と弟・斉信の戦いが示されています。
兄は弟を説き伏せますが、権力者道長は人格、評判の点で弟を登用します。
人間力を判断する道長の冷徹さにも着目してください。
大鏡本文
男君、太郎は左衛門督と聞えさせし、悪心起して失せ給ひにし有様は、いとあさましかりしことぞかし。
人に越えられ、辛いめみることは、さのみこそ御座しあるわざなるを、さるべきにこそはありけめ。
同じ宰相に御座すれど、弟殿には人柄・世覚えの劣り給へればにや、中納言あくきはに、われもならむ、など思して、わざと対面し給ひて、「このたびの中納言望みまうし給ふな。
ここに申し侍るべきなり」と聞え給ひければ、「いかでか殿の御先にはまかりなり侍らむ。ましてかく仰せられむには、あるべきことならず」
と申し給ひければ、御心ゆきて、しか思して、いみじう申し給ふにおよばぬほどにや御座しけむ、入道殿、この弟殿に、「そこは申されぬか」と宣はせければ、「左衛門督の申さるれば、いかがは」と、しぶしぶげに申し給ひけるに、
「かの左衛門督はえなられじ。また、そこにさられば、こと人こそはなるべかなれ」
とのたまはせければ、「かの左衛門督まかりなるまじくは、由なし。なし賜ぶべきなり」
と申し給へば、またかくあらむには、こと人はいかでかとて、なり給ひにしを、いかでわれに向かひて、あるまじきよしを謀りけるぞ、と思すに、
いとど悪心を起して、除目のあしたより、手をつよくにぎりて、「斉信・道長にわれははまれぬるぞ」といひいりて、

物もつゆ参らで、うつぶしうつぶし給へるほどに、病づきて七日といふに失せ給ひにしは。
にぎり給ひたりける指は、あまりつよくて、上にこそ通りて出でて侍りけれ。
意味がわかりましたか。
最後のところからは、人間の怖ろしさだけしか伝わってきません。
現代語訳を次にまとめましょう。
あらすじと現代語訳
男子のうち、御長男は左衛門督と申し上げた方です。
人を憎む心を起こされ、亡くなられた時のご様子は、じつになんとも言いようがなく驚きあきれる次第でございました。
他人に官位を越えられて、辛い思いをされることは、誰にでもよくあることです。
なにかそうなる巡りあわせでもあったのでしょうか。
同じ参議の位についていらしても、自分の弟にお人柄や世間での評判も劣っていらっしゃったので、中納言の位に欠員ができたならば、ぜひ御自分がなろうとお思いになっておりました。
改まって弟殿にご対面なさり、「今回の中納言の位を希望なさらないでくださいよ。私が昇進の希望を出すつもりでおりますから」と申し上げなさいました。
「一体どうして兄上を差し置いて先に中納言になったりいたしましょうか。まして、そのようにわざわざいらして申されることですから、中納言の位を賜れと申請するなど、とんでもないことです」と申しあげたのです。
それで心中も納得がゆき、満足におもわれ、一生懸命任官運動など申しあげないでおりました。
ところが道長殿が、この御弟に「あなたは中納言の任官を申請されないのか」とおっしゃられたので、「左衛門督が申請されるおつもりですから、どうして」と、いかにも不承不承にお答え申しあげなさったのでございます。
すると「いや、あの左衛門督はとても中納言にはなれまい。それに、あなたが辞退なさるならば、当然他の人が任官することになろう。」とおっしゃられるのです。

「そういうことになりそうならば、別の人よりは自分がなろうと思われました。
弟君が中納言におなりになったのを、兄である左衛門督は「私には決して昇進を申請しないと言っていたではないか、陰で裏切ってだましたのだな」とお思いになって、たいそう憎む心を起こされたのでございます。
除目の翌日から、手をつよくにぎりしめて「私は斉信と道長に騙されてしまったのだ」
と言い続けて、食事も全く召し上がらないで、ただただ、打ち伏せなさっていらっしゃいました。
そのうち病気になられ、七日ばかりでお亡くなりになってしまわれたのです。
その時握りしめられた指は、握る力があまりにも強かったため、手の甲にまで抜けていたそうでございます。
道長の冷徹さ
人間にはそれぞれの持つ人徳や器量というものがあります。
これだけは後からなんとかしたいと思っても、どうにもならないのかもしれません。
人が数人集まれば、そこにリーダーが生まれ、部下が生まれます。
どれほど権力を手に入れようと思っても、時が満ちなければ手に入れられるものではありません。
会社も団体も然りです。
男性にとって地位は魅力です。
もちろん、金銭的な裏付けもあります。
しかしそれだけではありません。
自分の采配で部下に仕事を割り振っていくということの醍醐味は、それを味わったものにしかわからないものなのでしょう。
よく言いますが、人事と予算です。
これを手に入れることは実に不思議な魅力に満ちています。
よく退職した会社の上司が元の部下につい命令口調でものを言ってしまうなどという話を聞きますね。
人間は1度手にした地位からなかなか離れられないもののようです。
今回の話も兄と弟の盟約が崩れるというよくあるテーマです。
古来から兄弟というのは実に厄介な存在です。
なまじ血が繋がっているだけに、最大の敵になりうる可能性を持っているのです。

いつの間にか、それぞれの部下に担ぎ上げられてしまいます。
彼らもあわよくばうまい汁を吸おうと考えているのです。
いわゆる派閥の形成です。
歴史を俯瞰してみると、まさに兄弟の争いは壮絶そのものです。
ここではその戦いの中に、道長が1枚加わっているだけに、話が複雑です。
兄・誠信が中納言になりたいと言明していると話す弟に、それは無理だと否定する道長。
あなたが辞退するのなら他の人にすると言われてしまえば、もともと出世したかった弟・斉信もすぐに籠絡されてしまいます。
このあたりの人間心理の操り方はさすがですね。
怖いのは最後の記述です。
悔しさのあまり兄がかたく握りしめていた指は、手の甲にまで突き抜けていたのです。
いかに悔しかったのかということを形容するには、これ以上の表現はないかもしれません。
平安時代だから男女が恋だけをしていたなどと考えてはなりません。
人の世はいつの時代も権力闘争の歴史なのです。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。