池井戸潤のドラマツルギー
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
今日はぼくの大好きな池井戸潤の小説の話をまとめてみたいと思います。
いつの頃からか、この作家の本を片っ端から読むようになりました。
テレビでさかんに銀行ものが放送されていた時期と重なります。
ぼくは生来の活字中毒なので、どうしても文字が優先してしまいます。
銀行を舞台にした多くの作品はほぼ読みました。
半沢直樹ものはむしろ、その本来のミステリーからのスピンアウトといった性格が強いように思います。
この作家はいつもテレビ番組と一緒にセットで語られてきました。
時に映画化されるものはあっても、基本はテレビです。
TBSの日曜劇場は彼をけっして手放そうとはしません。
中年の男性が見るにたえる番組として登場したのが、彼の原作ドラマです。
なんの特技もない、真面目だけが取り柄の男達が、大企業の理不尽な仕打ちに耐え、最後は勝負に勝つというパターンのドラマは、お父さん達の溜飲を下げました。
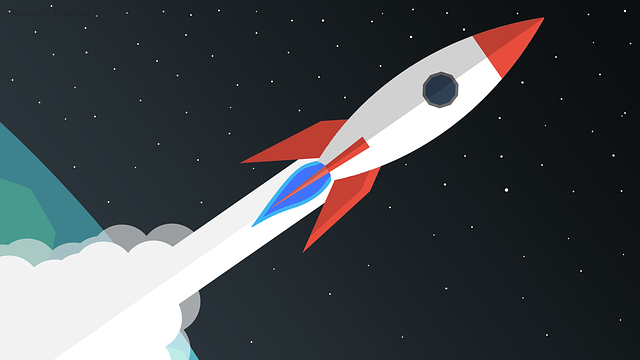
そうだ、人間誠実が一番だと思いながら、納得してテレビを見ていた人たちが多いはずです。
全て奮闘ものといっていいのです。
『下町ロケットシリーズ』も、『陸王』も 『空飛ぶタイヤ』『ようこそ、わが家へ』なども同じ構造のドラマです。
長いつらい忍従の時を経て、最後は必ず巨悪に勝つ。
そのための道のりはそれぞれ違いますが、パターンとしてはまさにこれです。
この小説のポイントは特許です。
大田区の町工場が取得した最先端特許をめぐる大企業と中小企業の戦いです。
かつて研究者としてロケット開発に携わっていた佃航平は打ち上げ失敗の責任を取って研究者を退き、親の経営していた従業員200人ほどの佃製作所を経営しています。
そこへ日本を代表する大企業帝国重工がバルブの特許をめぐって法廷闘争をしかけてくるのです。
モノ作りに情熱を燃やし続ける男たちの戦いがここから始まります。
大企業の持つ非情なやり口に、読んでいる人は怒りを覚えるに違いありません。
作家はそうなるよう、この部分の描写をしつこいほど悪辣に書きます。
やがて特許技術(知財)を巡る駆け引きの中で、社長の佃航平がみたものはなんであったのか。
さいごに大きなドンデン返しが待っているというのが彼の小説作法です。
このパターンは『下町ロケット』シリーズの全ての作品に共通しているパターンです。
信頼していた部下が相手企業に特許にからむ重要な秘密を教えていたとか。
一度トランスミッションに関わる研究をやめ、大学に戻ろうとした女性が、どうしてもまた開発に携わりたいと、佃の経営する会社に入社するという劇的な展開など。
『下町ロケットヤタガラス』ではこの日本を代表するトランスミッションの開発研究者が全ての話の根幹をつくりあげています。
彼女が入社し、研究陣に加わってくれなかったら、佃製作所が復活する道はなかったと思われます。
このように劇的なところで重要な人物が登場するというパターンは、池井戸潤の小説によく見られます。
陸王のあらすじ
『陸王』でもストーリーは似た形で進行します。

老舗の足袋屋「こはぜ屋」から脱却したい主人公は新しい靴の底にあたる材料を探します。
偶然銀行員から倒産した会社が持っていた特殊技術のことを知ります。
それがソールの素材「シルクレイ」でした。
容易に技術を手放そうとしない倒産した会社の社長を「こはぜ屋」に招きます。
そこで「陸王」にかける想いを熱心に語りました。
技術屋として熱い情熱を持つ社長は職人時代の自分を思い出し、シルクレイの使用を許可。
しかも契約料はいらないかわりに陸王の開発に参加したいと望みます。
さらに大企業がここにも登場し、彼らの行く手を阻むのです。
アメリカに本社を置くアウトドアメーカー「フェリックス」の社長が陸王のソール素材「シルクレイ」に目を留め「こはぜ屋」ごと買収する計画が浮上します。
フェリックスがほしかったのはシルクレイの特許だけでした。
これらの難関を「こはぜ屋」はどのように突破していったのか。
最後は人間の本当の「まごころ」とはなにかという熱いテーマになります。
このあたりが見ているお父さん世代にはたまらないのかもしれません。
最後はこの作品もハッピーエンドになります。
ハッピーエンド
池井戸潤の小説は、そのどれもが最後はみなうまくいきます。
暗く陰惨なエンディングで、気分が落ち込むということがありません。
それがまた読者を獲得していく高等テクニックとも呼べるのではないでしょうか。
彼の作品を読んでいて感じるのは、まるで勧善懲悪の時代小説そのものだということです。

苦しんで苦しみぬいた主人公が、最後に必ずいい結果を迎えます。
真面目に、これといって派手なところもなく、ただ日々を誠実に生きてきた者にとって、そこに繰り広げられる不条理はあまりにもつらいものです。
その苦しさを自分の身にひきつけて、なんとかともに戦いたい。
そして勝利したい。
しかしそれはなかなかにかなわないものです。
そのつらさをこの小説家がかわりにぶつけてくれる。
そして勝利をもぎとってくる。
その痛快さがたまらないのではないでしょうか。
半沢直樹の決まり文句「倍返し」もまさにその重みを持っています。
努力は必ず報われる。
どん底まで墜ちた主人公が必ず復活する。
勧善懲悪の持つ心地よさはあの痛快時代劇「水戸黄門」と同じです。
大袈裟にいってしまえば、最後の印籠にあたるものが、それぞれのストーリーによって違うということでしょう。
池井戸ミステリーの魅力
池井戸潤は子供の頃から、ミステリ-好きだったようです。
特に江戸川乱歩賞受賞作は必ず読んだといいます。
慶應義塾大学文学部、法学部卒業後、1988年に三菱銀行(当時)に入行したことで銀行の内側をみたことが、後の作家生活にとってどれほど重要であったか。
想像するのは容易です。
2010年、『鉄の骨』で第31回吉川英治文学新人賞を受賞。
2011年、『下町ロケット』で第145回直木賞受賞。
彼の企業小説は一度読めば、それで十分ですが、銀行小説は何度読んでも面白いです。
ぼく自身が銀行の裏側を知らないということもあるでしょう。
しかしここに出てくる銀行は外側の冷たさとは違って、実に人間くさい場所です。
出世、欲望、金、名誉。
あらゆるものが一線に並んでいます。
地位にしがみつく人間の醜悪な側面をいやというほど見せられるのが、この作家の銀行ミステリーです。
どこからこの小説家の作品を読めばいいのかという問いを投げかけられたら、ぼくは即座に銀行ものから進めといいます。
それくらい面白い。
内部にいた人間でなければ描けないことばかりです。
特に営業にからむ人間の異常な泥臭さには、少々辟易します。
出世したい人間が底辺から這い上がっていく時のすごい執念。
それを目の当たりにするのはつらいものがあります。
執筆生活をはじめた頃に書きためた小説は、ほぼ銀行ミステリーです。
『銀行総務特命』2002年
『架空通貨』2003年
『仇敵』2003年
『株価暴落』2004年
『銀行狐』2004年
『オレたちバブル入行組』2004年
『オレたち花のバブル組』2008年
『不祥事・花崎舞は黙ってない』2011年
どの作品も2度読めます。
前回に気づかなかったところにめぐりあえれば、面白みも倍加するでしょう。

銀行特有の専門用語がかなり飛び出てくるので、それも楽しみです。
信用調査が銀行にとっての生命線であることもよくわかります。
また銀行員にとって辞令が全てだということも。
これはサラリーマンを経験している人にとってはごく当たり前のことです。
しかしどうしてもこの秘密だけは外へ出せないとなると、人間は死を選ぶこともあります。
最後は地位だけに連綿としがみつく人間と、それを越えたある境地に達する人がいるということもあわせて理解できます。
ガラスの天井があると言われている銀行内部で、女性がどのように扱われていたのか、あるいは今も扱われているのかということもわかります。
三菱銀行(現在の三菱UFJ銀行)に6年間勤めた経験はさまざまなところに生きています。
どれを読んでもガッカリさせられるということがありません。
一言でいえば、読者を引っ張るのがうまい。
逆にいえば、あちこちに伏線がはってあります。
それを探しながらいくのもまた楽しいのではないでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


