 本
本 【泉鏡花・外科室】坂東玉三郎監督・吉永小百合主演の幻想世界【美】
泉鏡花は幻想的な作風の小説家として知られています。その彼の作品「外科室」が映画化されたのは今から20年前。女形として有名な坂東玉三郎が初めて監督をしました。主演は吉永小百合です。是非、特異な作品に触れてみてください。原作は青空文庫で読めます。
 本
本 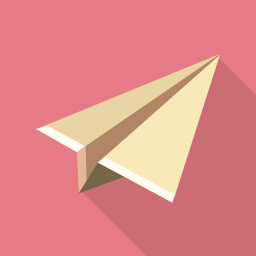 本
本 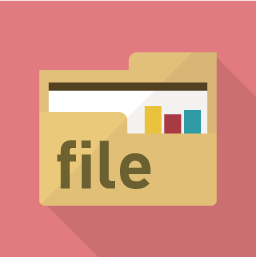 本
本 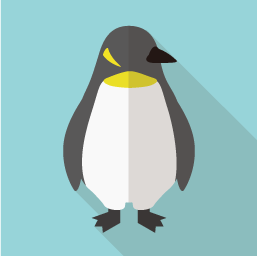 本
本  本
本  本
本  本
本  本
本 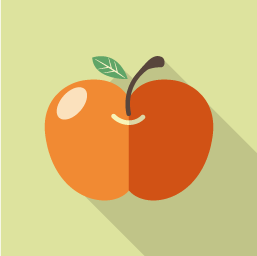 本
本  本
本 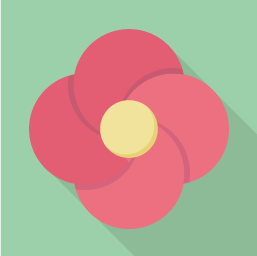 本
本  本
本  本
本  本
本 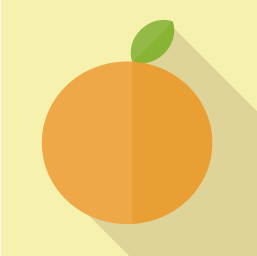 本
本 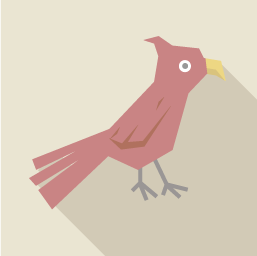 本
本