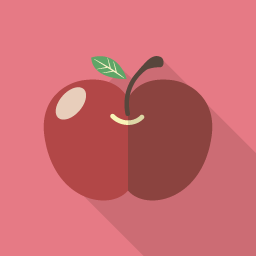ロングセラー
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
先日、図書館でなんとなく手にとった本の話を書きます。
結局最後までその場で読んでしまいました。
奥付をみると、2002年発行とあります。
タイトルは『社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった』というもの。
著者は香取貴信という人でした。
もちろん、名前なんか聞いたこともありません。
感動サービスコンサルタントと肩書が書いてあります。
なんとも怪しそうなネーミングですね。
随分と版を重ねてるんだなあというのが、その時の率直な感想でした。
その後調べてみると、ものすごいロングセラーなんだということを知りました。
文庫本にまでなってます。
もちろんKindleでも読めます。
内容はヤンキー高校生がディズニーランドへバイトに行き、失敗ばかりを重ねる話です。
よくぞ、こんなミスをするもんだというのが、最初の印象でした。
おそらく、ヤンキー高校生なら、きっとこんな感じなんでしょう。
彼女のために自分がミッキーになって写真を撮れると思ったというのですから、かなりのもんです。

MacGyverNRW / Pixabay
常識がないといったほうがいいでしょう。
朝寝坊して怒られたりするのも、十分に想定内です。
その時に上司のとった態度がまた驚きです。
机の引き出しの中から3つのタイプの目覚まし時計を引っ張り出して選ばせたとか。
著者の失敗談はひとまず脇に置いておくとして、一番ユニ-クだったのは、「さん」づけでアルバイトたちを1人の人格として最初から扱ったということです。
アルバイトはどうしても、正社員と同格の扱いではないことの方が多いです。
それをきちんと正対して人として扱うということは、なかなかできないことです。
現在でもアルバイトがいなければ動かないといわれているディズニーランド。
けっして待遇がいいわけではありません。
それでもそこで働きたいという若者がいるのはなぜか。
その秘密の一番の秘密が、ここにあるような気がしてなりません。
ディズニーランドを知った頃
20代の頃、実はディズニーランドの計画に関わったことがあります。
ぼくがある広告代理店にフリーライターとして関わっていた時のことです。
現場をみてくださいというので、当時の浦安市役所へ行きました。
そこで見せられた青写真が今日のディズニーランドそのものだったのです。
千葉県浦安市、京成電鉄、三井不動産の連合体がオリエンタルランドを設立し、始業に向けていました。
浦安といえば、山本周五郎の小説『青べか物語』にでてくる海苔を主体とした漁村です。
海岸までも歩きました。
青写真を見せてもらった後で、こんなものがこの海岸線沿いにできるとはとても信じられませんでした。
まだ潮の匂いがする静かな漁村だったのです。

twigaconseils / Pixabay
広い敷地を全て使い、その周囲にホテルを立地するなどということは、まさに夢のまた夢でした。
それから数年後、できあがった頃にも何度か訪れました。
まだ今の舞浜駅がなく、浦安からバスで行きました。
これ以外の交通手段は、車に限られていたと記憶しています。
それ以後の発展は、ただ目を見張るばかり。
経済学の観点から何冊かの本を読みましたが、それは中で働く人たちの様子を伝えたものではありませんでした。
サービスはかけ算
今回、この本を読んでいて一番感じたのは、上司の魅力です。
1人のヤンキー高校生をプロ意識を持ったスタッフに仕上げることは並々のことではなかったと思います。
非常にすばらしい上司が、今のディズニーランドを作りあげたということだけはよくわかりました。
ゲスト(お客)が一番ということはどの業種でもいわれることです。
しかしそれを身体に染みこむほどまで実践しているところはそう多くはありません。
その1つのスローガンが、「サービスはかけ算」という表現です。
たまたまスタッフの1人が退職することになりました。
著者は交通事故を起こし、用意していたバラの花束を届けられません。
会社に電話します。
その後しばらくして事故処理も終了。
車にのせたままのバラの花束40本をなんとかしなくてはと焦ります。

Pexels / Pixabay
そこでもう一度上司へ電話。
注意して会社へでてこいとのことです。
その時の上司の言葉。
「心のコンディション…」
「そう、たぶん、今は大丈夫なふりをしていると思うけど、けっこう香取の心の動揺はあると思うんだ。だからその心のコンディションではお客さんの前に立っちゃいけないと思うんだよ」
ここで上司はサービスは掛け算という言葉を使います。
「ゲストがエントランスから入ってくるでしょ。そこでエントランスのスタッフに気持ちのいい笑顔で対応されるとするじゃない。その後、アトラクションでスタッフに一生懸命にサービスされると、(中略)ゲストの楽しかった思い出は倍に倍になってくるでしょ」
「でもね、掛け算だからどこかでゼロを掛けるとどうなる」
「今の香取のコンディションは通常とは違うんじゃないかと思ってね」
「だから香取は終礼の時間までオフィスにいて、パーク閉園後に一緒にお城へ行ってTさんにバラを届けよう」
この台詞はなかなか言えるものではありません。
実際一緒に働いて、スタッフの心の内側をじっと見つめている人だけに可能なものです。
こうした上司に恵まれたということが、著者を成長させました。
馴れが一番怖い
シンデレラ城のミステリーツアー案内をした時の様子も心にしみます。
念願のアトラクションスタッフになれた頃は新鮮だった気持ちも、だんだんマンネリ化していきます。
アドリブが許されないナレーションの中に、自分だけ笑いをとりたいという欲が出始めました。
しかしゲストは面白いと思うことを言っても笑いません。

mohamed_hassan / Pixabay
うまくやろうとすればするほど、すべっていきます。
そんな時、上司の1人は新人と彼をペアにしました。
新人の案内ツアーが終わると、すぐに上司がやってきてこう言いました。
「はあ、ぼくの最初の頃よりは」
「違うよ、今の君よりもずっとうまかったでしょ」
その夜、オフィスを出ようとした時、上司が呼び止めます。
「別に怒ってないです」
「あのな、さっき言ったことは本心だよ」
「このアトラクションに必要なのはうまさなのかな。本当にうまいやつが必要なら、素人にはやらせないんだよ」
「ヘタでもいいんだ。このアトラクションに必要なのはどんなにヘタでもいいから、一生懸命にやることなんだよ」
「新人は確かにへタだった。このアトラクションは全部つくりものだ。ゲストもみんなわかってる。そのつくりものを本物として一生懸命にやっている姿がゲストにとって面白いし、価値を生むんじゃないか」
「今のおまえは手を抜くところを自然と身につけてしまった。だから面白くない。ただうまくごまかそうとしているガイドなんだよ」
この忠告をしてくれた上司も見事です。
本当によく見ていると感心します。
こういうささいな日常を重ねて、今日のディズニーランドが形成されたということなんでしょう。
近年あった訴訟問題などをみるにつけ、内情が変質しつつあるのかもしれません。
あるいはほんの一部なのか。
少なくとも創業時にこのディズニーランドを夢の国にしようとした人達の熱い思いは十分に伝わってきます。
彼らのような筋金入りの上司が1人ずつ去っていったとき、それをきちんと継承できる人がいなければなりません。
サービス業はどこまでいっても機械には任せられない質を持っています。
ぼくはこの本を読みながら、「教えること」の難しさと楽しさを同時に知りました。

geralt / Pixabay
著者が今日コンサルタントとして生きていけるのは、まさにここにあるような環境を築いてくれた上司の存在に負うところが大きいと感じます。
失敗はたくさんあります。
しかしそれと同じくらいの喜びを得たことが、著者の人生にとってどれほどの財産になったのか。
いまだにこの本が埋もれずにあるということが、なによりの証拠です。
働くことの意味や、本当のサービスとは何かについてもたくさん考えさせられました。
教え過ぎてはいけない。
必ず自分で考える時間をとらせること。
これもまた大切な教訓です。
最後までお読みいただきありがとうございました。