最初は末廣亭から
みなさん、こんにちは。
アマチュア落語家でブロガーのすい喬です。
さあ、寄席へ行きましょう。
一人でもいいし、ご夫婦でも、仲のいい友達とでも。
楽しみだなあ。
とはいえ、寄席はどこにあるの。
東京には1年中休みなく開いている定席(じょうせき)の寄席が5軒あります。
浅草「浅草演芸ホール」
新宿「新宿末廣亭」
池袋「池袋演芸場」
永田町「国立演芸場」
国立演芸場だけが、その名前の通り、国立なのです。
すごいですね。
国が寄席を作っちゃったというのは…。
これには落語家たちの長い長い苦闘の歴史があるのです。
でもここではそんなの全部省略。
その他にも、いつも公演しているわけではないものの、上野広小路亭による「しのばず寄席」、お江戸日本橋亭による「日本橋お江戸寄席」などもあります。
さらに五代目円楽一門会の「両国寄席」などもあります。

まずは定席の寄席に行きましょう。
それが今回のミッションです。
さてどこから攻略したらいいものか。
寄席の由来
と、ここまできたものの、ところでなんで寄席っていうのかな。
今まで当たり前に使ってきましたけど、よく考えるとヘンな言葉です。
字を見てください。
寄席は寄る席と書きます。
その名の通り落語,講談,音曲などを上演する演芸場のことなのです。
「よせせき」の略称で呼ばれ、「ひとよせせき」「よせば」などども言われました。
なるほど漢字にするとよくわかりますね。
現在,東京の寄席では落語が主です。
一人の持ち時間が約15分前後。一番最後に演ずる人のことをトリと呼びます。
これは紅白歌合戦などでもみんなが使うので、有名な言葉ですね。
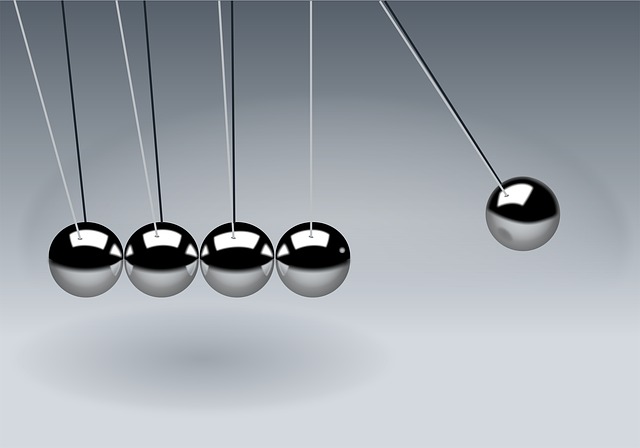
トリをとる落語家だけは30分くらいの長い噺をすることが許されるのです。
トリで座席をいっぱいにしたい。
トリをとると、大きな文字で書かれた一枚看板が寄席の入り口に掲げられます。
全ての芸人の夢なのです。
落語の間には講談,漫才,曲芸など色物 (いろもの)が挟まります。
落語だけだと飽きちゃうからね。
江戸で一番最初に行われた寄席興行は、1633年(寛永10年)に最古の職業噺家・初代三笑亭可楽(さんしょうていからく)によって行われた下谷稲荷での寄席と言われています。
現在ご存命の可楽師匠は九代目。そのお弟子さんの可龍師匠、可風師匠とは随分と長くお付き合いをさせてもらっています。
その話はいずれまた…。(これは脱線です)
一番盛んだったのは、江戸中期から後期にかけて。江戸中に130件ほどあったと言われています。
その後減ったり増えたりで、一時は数百件もありました。
それが今はたったの5軒。
なんといっても娯楽がたくさんありますからね。
昔はテレビがなかったので、町内に一軒くらいはあり、夕食を終えると、寄席に出かけたのだとか。
さて寄席見物の第一歩はまず雰囲気を味わうことから…。
どこがいいのかな。
一番寄席らしいのはなんといっても新宿末廣亭です。
ここはぼくの故郷。
子供の頃からずっと行ってます。
ちかくにあった鉱泉湯にも通ったのです。
懐かしいな。
寄席の風情
どうしてそんなに寄席らしい風情があるのか。
末廣亭の歴史をここで少しだけご説明しましょう。
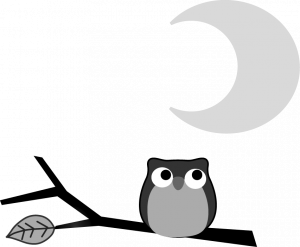
この名前を覚えておいてください。
落語界発展のために尽力してくれた、神様のような人です。
聞き書きをしてまとめた本まで出版されています。
タイトルはズバリ、『寄席末広亭』です。
末廣亭の歴史は明治30年まで遡ります。
当時は、明治通りに面した繁華街の一角に位置していましたが、戦争で焼失。
昭和21年、今の場所に再建されました。
今年で創業72年目。現存する最古の木造建築の寄席なんです。
北村銀太郎は焼け野原に本格的な寄席をどうしても建てたくて、お金を工面して再建したのです。
木材も厳選しました。とにかく風情がありますよ。
提灯がぶら下がっている場内のあの懐かしい風景は、ただそれを見にいくだけでも十分に価値があります。
年中無休
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-6-12
交通アクセス 地下鉄丸ノ内線・新宿線新宿三丁目駅より徒歩1分
新宿駅から歩くと10分くらい。
伊勢丹を越えて、次の通りに入ったところです。
飲み屋さんの一角を曲がると、もうそこは不思議なラビリンスへの入り口。
噺家の名前を大きく染め抜いた幟が何本も立ち、木戸口には噺家の名前がズラリと書かれています。
チケットはすぐに買えます。
安心してください。
何時からやってるの。
大事なことですね。
もう一度書きましょう。
なんと入れ替えがありません。
常連さんは昼から夜の9時までずっといます。
体力勝負です。
ところで初心者の心配は「服装」のこと。
寄席に行くなら、普段着。
あんまりおしゃれをしていく必要なんかありません。
聞いたことのない言葉に「テケツ」というのがあります。
これはチケットをもじった言葉。
昔はチケットがテケツと聞こえたんでしょうね。
寄席に入るには、国立演芸場以外、前もって予約する必要はありません。
当日、お目当ての寄席に行って、お金を払うだけでOK。
そして、入退場に関するルールはゆるゆる。
上演中ならいつでも入ることができます。
もちろん出るのも自由です。

場内での飲食もOK。
ただし餃子のように匂いの強いものはご勘弁。
末廣亭では売店でお弁当が売られていて、飲食OKです。
ただしアルコールは基本的になしね。
気軽にご飯を食べたり飲み物を飲んだりしながら楽しめるのも寄席のいいところかな。
1度入ったら数時間は楽しめますよ。
体力のある人は、最高は9時間。頑張ってください。
1回の寄席はだいたい3~4時間。
映画やコンサートに比べるとかなり長い感じもしますね。
休憩が入り、入れ替わり立ち替わり噺家が高座に上がります。
落語だけじゃありません。
講談、漫談、漫才に奇術、紙切りなど様々な演目が用意されています。
その日一番最初に出てくるのが「開口一番」。
前座さんが出てきて、いよいよ始まりです。
演目は決まってない
実はなんの噺をするのか、あらかじめ決まっているわけではありません。
お客さんの顔色をみてから、決めます。
同じ系統の噺はしません。
だから後半に出る噺家は、たくさんの落語を知っていなくてはならないわけです。
前座は全ての演目を綴じた紙に書いていきます。
噺家はそれを出番の前に見て、噺が重ならないようにします。
この綴じ本のことを根多帳と言います。
ネタがつくのは避けなければなりません。
足の不自由なお客さんがいれば、ホワイトボードにその旨、注意書きが書かれます。
そういう時は、足の悪い登場人物が出てくる噺は避けなければなりません。
泥棒がいる時は…。
まさかそんなことはないかな。
たくさんの魅力に富んだ空間、それが新宿末廣亭です。
ところで友の会に入ると、ものすごく得なんです。
落語家の名前の入った湯飲みや、扇子、手拭いなどもらえちゃいますよ。
その他に深夜寄席というのもあります。
21時チケット販売開始。
21時半から開演。
だいたい21時前から並び始めます。
若手のための勉強会です。
やっぱりここから始めないとね。
さあ、今度のお休みは新宿へGO…。
最後までお読みいただきありがとうございました。



