 小論文
小論文 「自信とプライド」枠の中に押し込められず日本で個性的に生きる道
誰でも自信とプライドを持って生きています。しかし日本型社会では、あまりにそれが目立ちすぎると、いじめに発展してしまうのです。どうやったら、うまく他者と調和しつつ、自分の個性を発揮できるのでしょうか。
 小論文
小論文  小論文
小論文 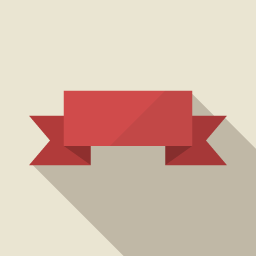 学び
学び  本
本  学び
学び 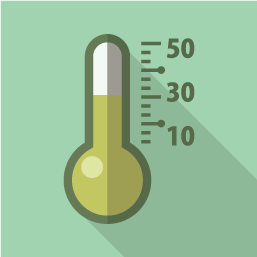 ノート
ノート  本
本  本
本  本
本  ノート
ノート  ノート
ノート 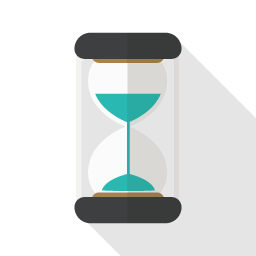 ノート
ノート  本
本 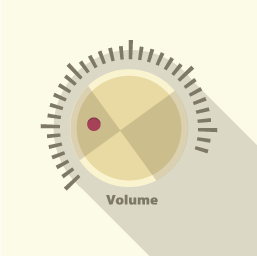 本
本  ノート
ノート 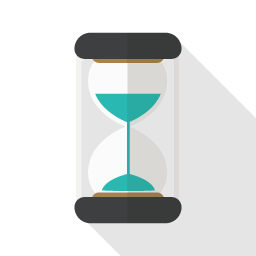 ノート
ノート