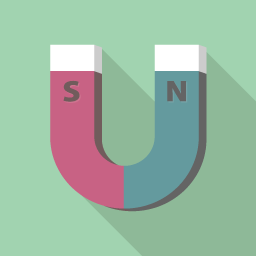 学び
学び 【日本人の序列意識】目的を見失う子どもと学校との関係【登校拒否】
日本人の持つ序列意識はかなり強烈です。つねに優劣をつけることで、自分の位置を探ろうとします。しかし優位に立てないものは、コンプレックスを強く持つこともあります。実社会に出ても、十分に力を発揮できないケースも多いのです。
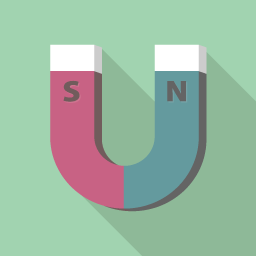 学び
学び  学び
学び  学び
学び 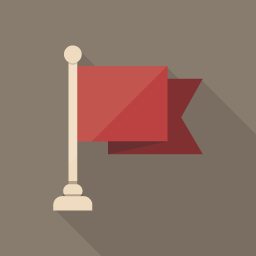 学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び 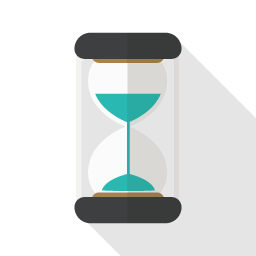 学び
学び  学び
学び 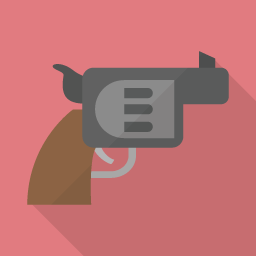 学び
学び 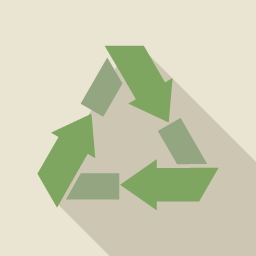 学び
学び  学び
学び 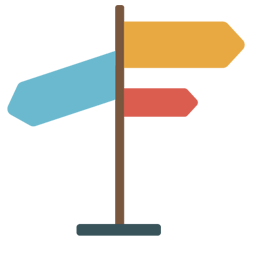 学び
学び  学び
学び 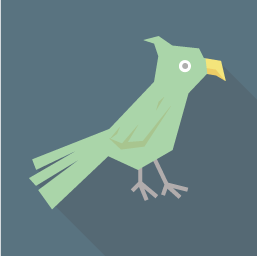 学び
学び 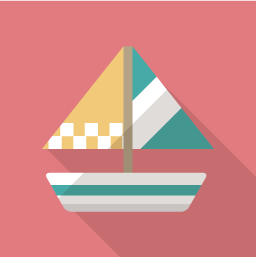 学び
学び