 本
本 【源氏物語・須磨】栄達への転機となった光源氏の歴史絵巻【貴種流離】
『源氏物語』は日本が誇る世界に通用する文学です。その12段に「須磨」の巻があります。ここで光源氏は今までにない流離の生活をします。そこからの復活にはかなりの時間がかかりました。しかしここでの成長が、それ以後の出世を約束したのです。
 本
本  本
本  本
本  本
本  本
本 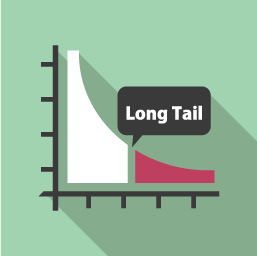 本
本  本
本  本
本 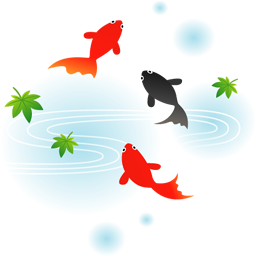 本
本  本
本 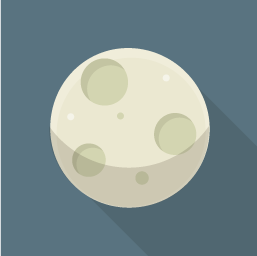 本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本