想像し物語ること
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は今年(2023年)に亡くなった作家、大江健三郎の話をします。
ぼく自身、かなりの小説とエッセイを読破してきたというのが実感です。
追い立てられるように、読んできた記憶があります。
友人が当時、出版できなかった『政治少年死す』のコピーまでくれました。
1961年、まだ高校生だった頃の話です。
文芸雑誌「文學界」に『セブンティーン』の第2部として掲載されたものでした。
当時の浅沼稲次郎社会党委員長を刺殺した、右翼の少年をモデルにした小説だったのです。
第1部は単行本になったものの、2部はその後60年にわたって世に出ませんでした。
大江健三郎はさまざまな意味で、昭和から平成を支えた小説家です。
難解な内容の作品が多かったですね。
かなり苦しみながら、読んだ記憶があります。
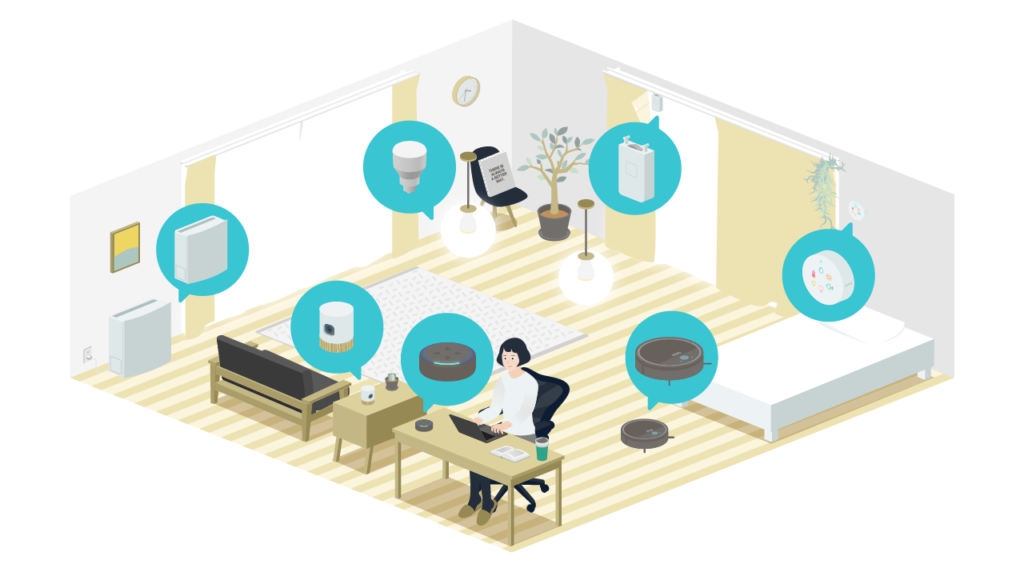
『奇妙な仕事』などという、戦慄的な小説も記憶に強く残っています。
その後は『飼育』『芽むしり仔撃ち』『死者の奢り』『ヒロシマ・ノート』『万延元年のフットボール』『個人的な体験』『新しい人よ眼ざめよ』など、次々と話題作を書き続けました。
読みたいというより、ぼくの中では課題図書のような位置づけでしたね。
彼は1994年にノーベル文学賞も受賞しました
日本文学という従来の枠組みから、大きく外にはじけ出ていたと感じます。
「核時代の想像力」というグローバルな視点が、世界中に翻訳された小説とともに評価されたのです。
川端康成の受賞から26年後のことでした。
安倍公房や三島由紀夫などと並んで、まぎれもなく日本を代表する小説家の1人です。
今回、彼が1998年に発表した『小説の経験』というエッセイを教科書で見つけました。
非常に内容の濃いものなので、部分的に再録してみます。
人間という生き物が持っている自己表現への欲求について、語っている随筆です。
だれもがなるほどと納得してしまうだけの、リアリティを持っています。
本文
人間とは、誰でもどこかで自己表現をしたいと願っている生き物だとつくづく思います。
障害を持っている私の息子も、この15年ほどの間にピアノを教えられるうち、自分で作曲するようになりました。
ある人に表現する手段を与え、それをやるように励まし、そして表現されたものを受け止めてやる。
そうすれば、自力では自己表現する道が断たれているような人も、あらためて表現を始めるようになる。
デイケアセンターに通って、お習字をしている老年の義母を見てもそう思います。
文学の一番の基本には、こうしたかたちの、人間とは自己表現をしたいと願っている生き物だということが、 まずあると思います。
しかもそれを言葉、文字を通じてやる。
言葉を書きつけると、それまで意識にはっきりとはとどめていなかったもの、できごとが、手ごたえのある対象、情景として浮かび上がってくるということがあります。
またどういうかたちでか文章にその書き手の「声」が響きだして、独特の文体を作り出すことにもなります。

このようにして文学が生まれてくるといって、基本的に誤りではないだろうと思います。(中略)
広島の原爆病院でお会いした老婦人が、私に彼女の被爆体験を話される。
その最初の時、彼女はむしろ記憶をしるしておいた本を静かに読み上げてゆく、というふうであったのです。
これまでに書かれている広島の記録は私の体験したものとは違うときっぱり言ってから話し始められたのではありましたが。
ところが翌日になって、私の聴き書きの原稿を前において、次々にその上を指で押さえてゆきながら、こうではなかった、もっと恐ろしかったですよ、と言って話しなおされてゆく、その語り口はうってかわって生き生きとした、激しいほどのものなのでした。
青ざめていられた頬があざやかに血色を浮かべるほど、そしてあらめて録音をとった私がおいとまする時、彼女は、この数年、こんなに興奮して面白い時を過ごしたことはありませんでした、と言われたのでした。(中略)
自分が先に話した内容を叩き台に、それに新しいきっかけをあたえられて、次々に色濃く思い出された情景を話されてゆく、その想像力のはたらきと、そのように物語をしたことそれ自体が、彼女を元気づけていたのだと思います。
自己表現とは
おそらく人間という生き物は、どこまでいっても自分を表現したいという欲求を持ち続けて生きるのだと思います。
それなしに生きる意味はないといってもいいのではないでしょうか。
もちろん、表現の手段は人によって千差万別です。
芸術のような比較的自由な表現も当然あるでしょう。
あるいは、細かな技術を駆使した機械の設計や、プログラムの開発などという仕事を通じてということもあります。
考えてみれば、人間が行うあらゆる営為は、全て自己表現の方法だといえます。
このエッセイに出てくる原爆病院で出会った老婦人は、自分の体験を語ることが、1つの自己表現でした。
ここには実にユニークな語り部としての行為が示されています。
前日に話したことを聞き取り、それを文字に起こし読んだ時、そうではない、現実はもって怖く悲惨だったということを、自分の言葉で伝えようとしたのです。

話しなおすことそのものが、その時間を生きていた証しであり、自己表現だったのです。
最後に語った言葉にも真実が宿っていますね。
この数年でこんな昂奮して話をしたことがないという発言です。
そこには想像力が限りなく飛躍していくことの可能性が、満ち溢れています。
本当はそれが人間にとって、1番楽しく有意義なことに違いないのです。
どのような人間にとっても、創造することが魅力的なことだという真実が、見て取れます。
哲学者・バシュラール
このエッセイには最後のところに哲学者、ガストン・バシュラールの話が載っています。
想像力とは何かという時、与えられたイメージをそのまま受け取ることではなく、むしろ、それを作りかえていくことだと定義したのは、彼でした。
1つのイメージが次々と新しいイメージを湧きあがらせる。
はじけるように、イメージの群れが爆発していくというのです。

それがきっと感情を豊かにし、自分にとって最も親密な時をつくりあげることなのでしょう。
すぐれた小説もそうしたものなのに、違いありません。
いままで経験したこともないような異空間へ、自分をつれていってくれるもの。
もちろん、それは文学だけではありません。
演劇にも音楽にもそうした根源的な力があります。
だからこそ、それを創り出そうとする人間は、自分の内側をえぐるようにして、豊かなイメージをふくらませようと努力するのでしょう。
大江健三郎もそうした作家の1人であったということができます。
おそらくこれからも、つらい時代が続く中で、彼の作品は読みつづけられることと思います。
それはなぜかといえば、そこに豊かな想像力が宿っているからです。
読者がはじめて知る道の領域に、踏み込んだ印を見せてくるからです。
その時の驚きと気づきが快いものでなければ、誰にも読まれることはなくなるはずなのです。
それもこれも、どこまで作家が自分のイメージを広げ続けたのかという戦いと同じレベルで語られるはずです。
秀れた小説とはどのようなものなのか。
大江健三郎はそれを考えるための試金石となる作家の1人です。
これからも大切にしていかなければなりません。
今年は大きな作家をまた1人、失いました。
機会をみつけて、彼の著作を読んでみてください。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


