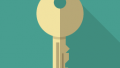筑紫道記(つくしみちのき)
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は連歌の大成者、宗祇を扱います。
彼が山口から九州に赴き、その帰路、今の福岡県蘆屋のあたりを通りかかったときの記録です。
摂津の灘に見られる塩焼きの煙が、筑前の蘆屋では見えないことを詠みました。
芭蕉などにも大きな影響を与えた紀行文です。
作者は飯尾宗祇(そうぎ)です。
『筑紫道記』は1480年、筑前守護の大内政弘の誘いを受けて、周防山口に下った宗祇が、
九州に渡り、大宰府、博多などをめぐって山口に帰省するまでの36日間の紀行文なのです。
宗祇は室町中期の連歌師です。
初め仏門に入り連歌を心敬などに学びました。

諸国を遍歴し、全国に連歌を広めたのです。
最も有名な著作は『新撰菟玖波集』(つくばしゅう)です。
文学史の授業で習いませんでしたか。
連歌という歌の型はあまり馴染みがないかもしれません。
5・7・5の発句と7・7の脇句を何人もで、続けて詠んでいきます。
原型は奈良時代に始まったといわれています。
鎌倉から室町時代にかけて、最も隆盛しました。
次第に長くなる傾向がうまれ、最も有名なのは「水無瀬三吟百韻」と呼ばれています。
1488年1月に行われました。
当時を代表する連歌師、宗祇、肖柏(しょうはく)、宗長による三人が順に詠んだものです。
大変に美しく内容の深い作品で、高校の教科書には必ず載っています。
やがてここから発句だけが独立し、俳諧と呼ばれる形になりました。
つまり俳句の原型と考えればいいのではないでしょうか。
本文
旅の空はいつとなく、世のことわりのもの憂きながら、世々のふるごとなどにも
思ひ慰め侍るを、相ひ具したる者どもの、ひとへに浪風の愁へをのみうち嘆くを
聞きても、我ゆゑにこそと思ふもあぢきなし。
松原遠く連なりて、箱崎にもいかで劣り侍らんなど見ゆるは比ひなけれど、名所ならねば、強ひて心とまらず。

やまと言の葉の道も、その家の人、または大家などにあらずば、かひなかるべし。
しかるを、このたび所々にして瓦礫を連ぬること、二十首に及べり。
あるは敬信の心、あるはこの道の願ひ、あるは我が身の思ひを述べ、
あるは古のなき世の跡をあはれび、または所につけておもかげ忘れがたきにも催さるるなるべし。
俊成卿の筆跡にも、「この国に来たりと来たれる者は、この歌をながめ、
かくのごとき国に生まれと生まるる者は、この歌をよめり」と言ヘリ。
また「生きとし生けるものいづれか歌を」と言へること侍れば、強ひて身の賤しきを恥づべきにあらず侍らん。
かくてほどもなく、蘆屋になりぬ。
真砂高うして山のごとくなるに、松ただ群れ立ちて、寺々あまた見え渡る。
民の家居あまの苫家数ならず。
川の向かひは山連なりて、さまざま見捨てがたき折から、時雨いささかうちそそき、
夕月夜さやかにさし昇りたるなど、作り合はせたるやうなり。
灘の塩焼きといへる辺りよりは、立ち代はりてあはれ勝れり。
塩焼かぬ蘆屋の秋ぞあはれなる月や煙を厭ひ初めけん
神無月を秋と言へること、源氏物語にも侍るにや。
ここにて麻生兵部大輔設けして、色々の心ざし、来し方に変はらず。
発句をと侍れば、
追い風も待たぬ木の葉の舟出かな
現代語訳
旅の道中はいつでも世の道理として辛く思えるものですが、昔からの言い伝えなどを聞いては旅の憂さを慰めています。
同行人がひたすら、波風の心配ばかりを嘆くのを聞くにつけても自分のために
苦しい思いをさせると思うとあまり愉快ではありません。
この地には松原がはるかに続いています。
有名な箱崎の松原にどうして劣っているでしょうか。
見える景色は本当に美しいけれど、名所でもないので、特に心に残るということもありませんでした。
歌をたしなむ家の人でなければいくら和歌を読んでも、何の意味もないのかもしれません。
それなのに私は今度の旅の道中、 所々で駄作を詠み連ねることが、20首にもなりました。
あるものは神仏を敬い、またあるものは歌道についての願い、またあるものは
自分自身の思いを述べ、あるものは古いものや、昔の跡をしみじみと懐かしんだ歌です。
また場所によって風物の美しさが忘れがたく、何かにつけても歌心が喚起されました。
俊成卿の書いたものにもこの国にやってきたものは、皆和歌を詠むとあります。
またこの国に生まれたものは、誰も彼もが、和歌というものを詠んできたとも述べています。
また貫之は生きているもののうち誰が歌を詠まないものがあろうかと、『古今集』の序に述べているのです。

私もそんなところから、歌を詠もうという気になりました。
こうしてほどもなく、芦屋に到着したのです。
細かい砂が高く積もって山のように見えるところに、松がただ群生していて、寺が数多く一面に見えます。
民家や粗末な家もたくさんあります。
川の向こうは山々が連なって、その景色が見捨てがたく思われました。
時雨がさっと降ってきて、夕月が明るく清らかでした。
登ってきた情景などをわざわざこしらえ上げたかのように、自然の風情が出来上がっているのです。
灘の塩焼きと伊勢物語にあるように、摂津の芦屋のありさまとはまた異なって情緒がありました。
塩焼かぬ蘆屋の秋ぞあはれなる月や煙を厭ひ初めけん
神無月を秋と言っていることは『源氏物語』にもあるのでしょうが、ここで麻生兵部大輔がもてなしの支度をしてくれました。
様々な配慮を昔に変わらずしてくれます。
ぜひ一句をとございましたので、この発句を詠んだのです。
追い風も待たぬ木の葉の舟出かな
歌を詠むということ
宗祇はこの紀行文の中に、いくつか自分の信念を書き込んでいます。
そのために引用されたのが、俊成と貫之の言葉です。
俊成の言葉は『古来風体抄』にみてとれます。
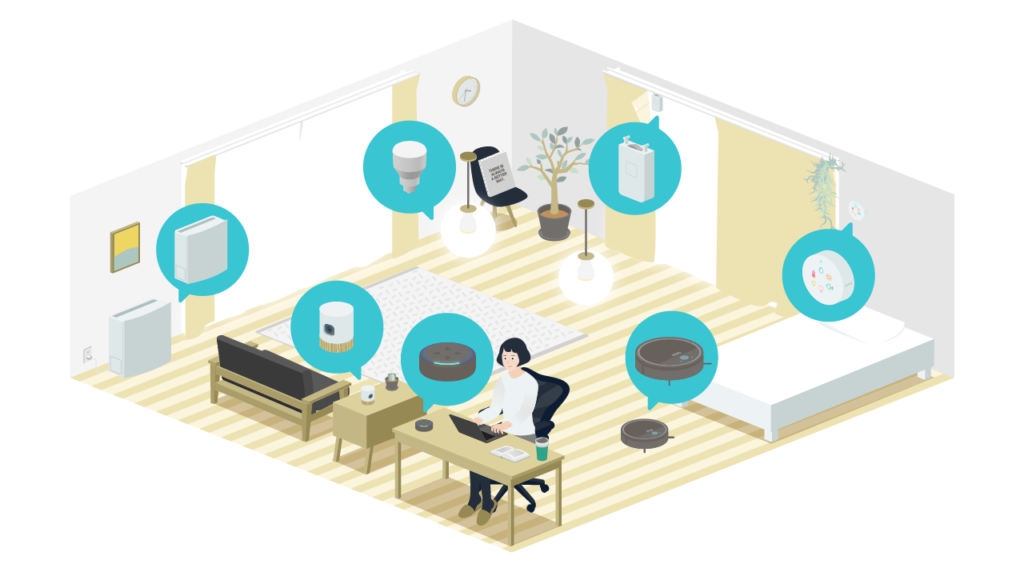
貫之の言葉は『古今集仮名序』です。
この2つの文章の引用の後に、宗祇が胸をはって綴った文章が目を引きますね。
それは何か。
「強いて身の賤しきを恥づべきにあらずや侍らん」という表現です。
歌を詠むにあたっては我が身の卑賎を恥じる道理はないということです。
諸国を遍歴し、連歌のすばらしさを広めるということが、彼の目標でした。
すばらしい歌をつくるためには、身分などは全く関係がないと断言しているのです。
この考えは、芭蕉と通じていますね。
むしろそうした貴賤の感情を全て捨て去り、自然の中に没入することで得られた心境が、歌の命だと彼は信じたのです。
今日、あまり連歌に親しむチャンスはないかもしれません。
これを機会に少し調べてみてはいかがでしょうか。
「水無瀬三吟百韻」は不世出の趣きに満ちています。
一読をお勧めする次第です。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。