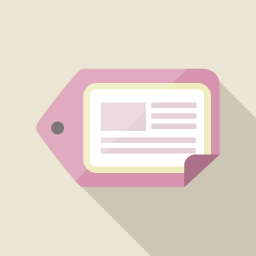玉勝間
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は本居宣長の随筆集『玉勝間』(たまかつま)を読みましょう。
不思議なタイトルですね。
本居宣長(1730~1801年)は江戸時代の国学者です。
国学とは文献学、言語学をさします。
彼は約35年を費やして『古事記』研究の集大成である注釈書『古事記伝』を著しました。
『古事記』の価値がこの時から一気に高まったのです。
それまであった史書としての評価が、これ以降独自のものになりました。
学問に対する認識がかわるにつれて、内容は日々変化していくものです。
それが自然です。
いつまでも同じところに佇んでいてはいけないのです。
その変化が怖いのなら、学問を続けることの意味はないに違いありません。
本居宣長がすごいのはその時代の最先端にいながら、つねに成長し続けたことです。
彼はそれを避けようとはしませんでした。
普通なら、権威になってしまうと、動きが極端に鈍くなるものです。
しかし彼にはそれがなかったのです。

この当時の国学は、本居宣長の言うとおり、人が変わり、時代が変わる中で、発展を遂げ続けていました。
「人を経、年を経てこそ、次々に明らかにはなりゆく」ものであったのです。
当然、彼の学説も変化しました。
国学関係の書物もどんどん出版され、多くの人の目に触れることとなりました。
これが同一人物の著書か、と思われるようなこともあったのです。
それをいけないことだと忌避するのは、学問の道を目指す人間として、あってはならないことです。
彼が自分の世界をいつも高い位置から客観的にみていたという事実が、この『玉勝間』と随筆にはよくあらわれています。
独自の観点
玉勝間は随筆集だと言いました。
「かつま」というのは編み目の細かい竹籠の意味です。
籠にものがたまっていくように、エッセイを書き続け、心の遊びとしたい、といった念願がタイトルにはこめられているのです。
『徒然草』の冒頭を連想してしまいますね。
寛政5年(1793)に起稿し、没するまで書き続けられました。

ここには本居宣長という人間の考え方のすべてが記されています。
彼が学問や芸術や人生をどのようなものとして捉えたのかを知るには、最良の本です。
今回、その中から代表的な一節を取り上げて、読んでいきます。
宣長の著作は高校でも少しだけ取り上げます。
このブログにも記事があるので、時間がありましたら、あわせて読んでみてください。
国学の研究が、賀茂真淵の時代から本居宣長の時代になってから、研究に携わる人も増えていきました。
それだけ興味深い学問の分野になりえたワケです。
その頃に纏められたのが、この一節なのです。
本文
同じ人の説の、こことかしことゆきちがひて、ひとしからざるは、いづれによるべきぞと、まどはしくて、おほかたその人の説、すべてうきたる心地のせらるる。
そはひとわたりはさることなれども、なほさしもあらず。
初めより終はりまで、説の変はれることなきは、なかなかにをかしからぬ方もあるぞかし。
初めに定めおきつることの、ほど経て後に、また異なるよき考への出で来るは、つねにあることなれば、初めと変はれることあるこそよけれ、
年を経て学問すすみゆけば、説は必ず変はらでかなはず、またおのが初めの誤リを、後に知りながら、つつみ隠さで、きよく改めたるも、いとよきことなり。

ことにわが古学の道は、近きほどより開けそめつることなれば、すみやかにことごとくは考へ尽くすべきにあらず。
人を経、年を経てこそ、次々に明らかにはなリゆくべきわざなれば、一人の説の中にも、前なると後なると異なることは、もとよりあらではえあらぬわざなり。
そは、一人の生の限りのほどにも、次々に明らかになりゆくなり。
されば、その前のと後のとの中には、後の方をぞ、その人の定まれる説とはすべかりける。
ただしまた、みづからこそ、初めのをばわろしと思ひて改めつれ、またのちに人の見るには、なほ初めの方よろしくて、
後のはなかなかにわろきもなきにあらざれば、とにかくに選びは、見ん人の心になん。
現代語訳
同じ人の説であるのに、あちらこちらに食い違いがあって考えが等しくないのは何によるのだろうかと、惑わされてしまうものです。
その人の主張すること一切合財が気に食わなく思えることがあるものです。
それも確かにもっともではありますけれども、それが、そうとも言い切れないのです。
初めから終わりまで、その人の考えが変わらないというのは、かえって趣きがないという見方といえるのではないでしょうか。
初めに、こうだと決めてかかっていたことなのに、年月を経てみると、また別のよい考えが出て来ることは、つねにあることです。
だからこそ、初めと変わることがあって良いとも言えるのです。
年を経て学問が進んでいけば、考えも必ず変わらずにはいられないものなのでしょう。
また自分が初めは誤って考えていたことを、後になって知りながら包み隠すようなことをしてはいけません。
潔く改めるということも、大変良いことです。
特に私が提唱する古学の道は、身近なところから開き始めていくものです。

それだけに、当初からすべてのことを考え尽くすことはできません。
人との触れあいを経験し、年月を経ていくうちに、次々に明らかになっていくのが学びというものです。
それだけに、1人の主張する考えの中にも、前の考えと後の考えとでは異なることは、もとよりなくてはならないことです。
それは1人の人生に限ってみただけでも、次々に明らかになっていくものです。
そうなると、前の考えと後の考えとの中では、後の方をその人の定まった説ととらえることができるでしょう。
しかし本人としては、初めの考えの方を良くないと思って改めたわけです。
ところが、また後の別の人が見たときには、かえって初めの考えの方が良くて、後の方がむしろ悪いということもなくもないのです。
それだけに、とにもかくにも、どちらが良いかを選ぶのは、見る人の心次第であると言えるのではないでしょうか。
謙虚であるということ
これが国学を高い位置にまで引き上げた偉大な学者の言葉です。
読んでいてどんな感想をお持ちですか。
こんなことを言ってしまっていいのだろうか、と思いませんでしたか。
ある意味、自信がなさそうにも感じます。
しかし、非常に謙虚ですね。
偉ぶったところが少しもありません。
本当なら、もうここから自分の考えは変えないと主張してもおかしくはないのです。

それなのに、ひとつの思想に凝り固まらず自由に変化を遂げていくのが、本来の学問の道だと主張しているのです。
それだけで頭が下がります。
真理を極めることに対して、どこまでも真っすぐに突き進んでいきたいとする考え方です。
本当にほんのわずかでも先へ進みたいなら、真面目で謙虚でなければなりません。
これは学問だけの話ではないのです。
人生のあらゆることに繋がる、大切な考え方ではないでしょうか。
本居宣長という人の心の中が透けてみえるような、いい文章だと感じます。
あなたも、少し考えてみてください。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。