20世紀を代表する小説家
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は安部公房の書き下ろし小説『箱男』を取り上げます。
発表されたのは1973年。
50年前の作品です。
『砂の女』という小説が好きでした。
大江健三郎と並んで、新しい文学の騎手だという予感がありました。
もう少し長く生きていれば、ノーベル賞に近かったと言われています。
作品はほぼ無国籍性をキープしていました。
どこで起こっても不思議ではない、20世紀の不条理な世界を表現したのです。
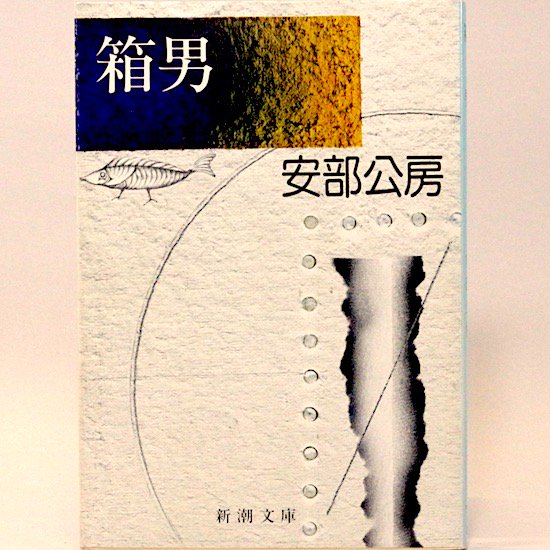
このブログでも、いくつか彼の小説を記事にしています。
最後のところにリンクを貼っておきます。
時間がありましたら、ご一読ください。
教科書にも短編が隋分所収されています。
『赤い繭』『鞄』などは不思議な読後感の作品です。
生徒の感想も好意的なものが多かったです。
20世紀はある意味、不条理全盛の時代でした。
カミュ、カフカ、サルトルなどの作品が次々と発表され、演劇にも大きな影響を与えました。
ベケットやイオネスコの戯曲も多くの人に受け入れられたのです。
発表当時、すぐに『箱男』を読んだ記憶があります。
しかしあまりにも難解で、何を言おうとしているのかよくわかりませんでした。
実験的な小説だといえば、まさにその通りです。
奇抜なタイトル
タイトルからして奇抜ですね。
ダンボール箱を頭から腰までかぶり、覗き窓から外の世界を見つめて都市を彷徨う男の手記という体裁は、それだけでもう全く非日常そのものです。
電信柱の陰に隠れて、他人の部屋を覗いている人間の存在を想像してください。
不気味そのものです。
今風に言えばストーカーでしょう。
当時から言われだした、「アイデンティティ」喪失の危機感が如実に浮かび上がってきます。
無名性という言葉もよく使われました。
いずれにせよ、道具立てから、ストーリーに至るまで、全てが破格だったのです。
アンチロマンという言葉がはやった時代です。
これが小説だといった概念が全て突き崩された後に、何が残るのかというのが主なポイントです。
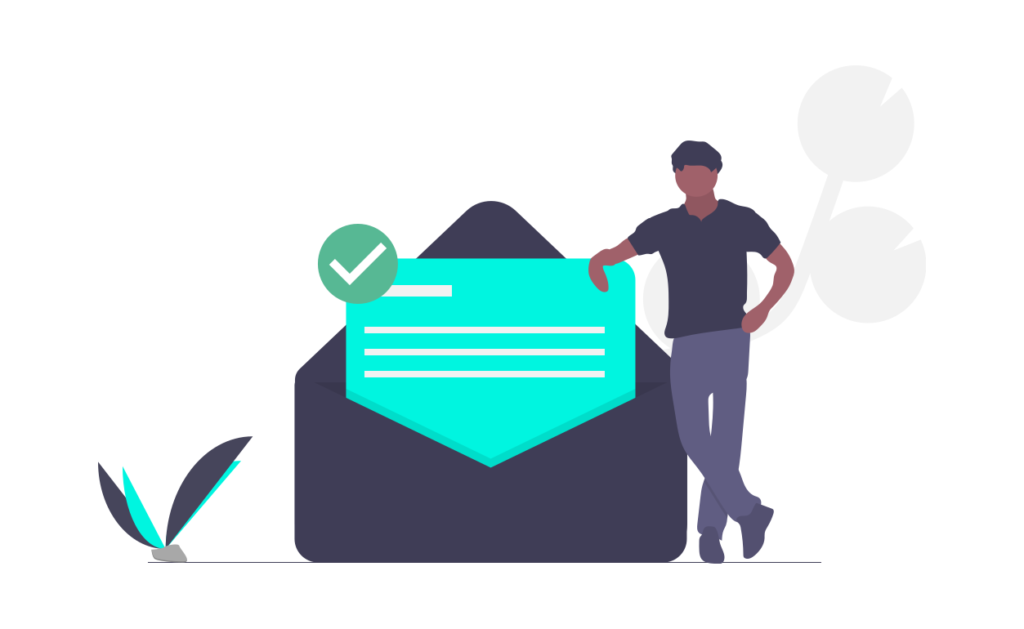
表立って特異な物語があるワケではありません。
しかし通常の感覚で読んでも、理解はできないと思われます。
作者はむしろ、そういう迷路に読者を導くために、この小説を書いたのではないかと思うほど、全てが通常の表現ではなかったのです。
一言でいえば、ラビリンスへ誘うということでしょうか。
箱男の書いた手記は、この小説の軸として確かに存在します。
しかしその周辺に他の人物が書いたとみられる文章が散りばめられ、新聞記事や写真までが追加されます。
まさに実験小説と呼ぶにふさわしいパラメーターを備えた作品ということが言えるのです。
何のために、これほど難解な小説を書いたのか。
『砂の女』の持っているザラザラした触感とは、全く違う類いの感覚です。
無機質とでも呼べばいいのかもしれません。
無国籍で無機質な小説という表現が1番ピッタリでしょう。
映画化
この小説がなぜ再び日を浴びつつあるのかについては、ついに実写化され、今年公開されるということにつきます。
2月にドイツで開催された第74回ベルリン国際映画祭で、「箱男」が上映されたのです。
この作品は1997年にドイツとの合作で製作が決まったものの、結局中止しました。
今回、27年後に完成したというワケです。
監督は石井岳龍、主演は永瀬正敏です。
長い間、実写化への執念を燃やし続けるには、それなりの思惑があったに違いありません
どうしてそこまでの熱意があったのか。
監督のインタビューによれば「情報化社会がどうなるか予言したこと」につきるということです。
つまり現代を生きる人間は、何重にも囲われた自分なりの情報、妄想の世界に生きているのだというのです。
現代の不確かさを追い求めていったら、「箱男」にぶちあたったのです。
かつて、作家本人から映画化の許諾を得ていたそうです。
しかし資金がショートし、ドイツ・ハンブルクでの撮影前日に中止されたという経緯がありました。
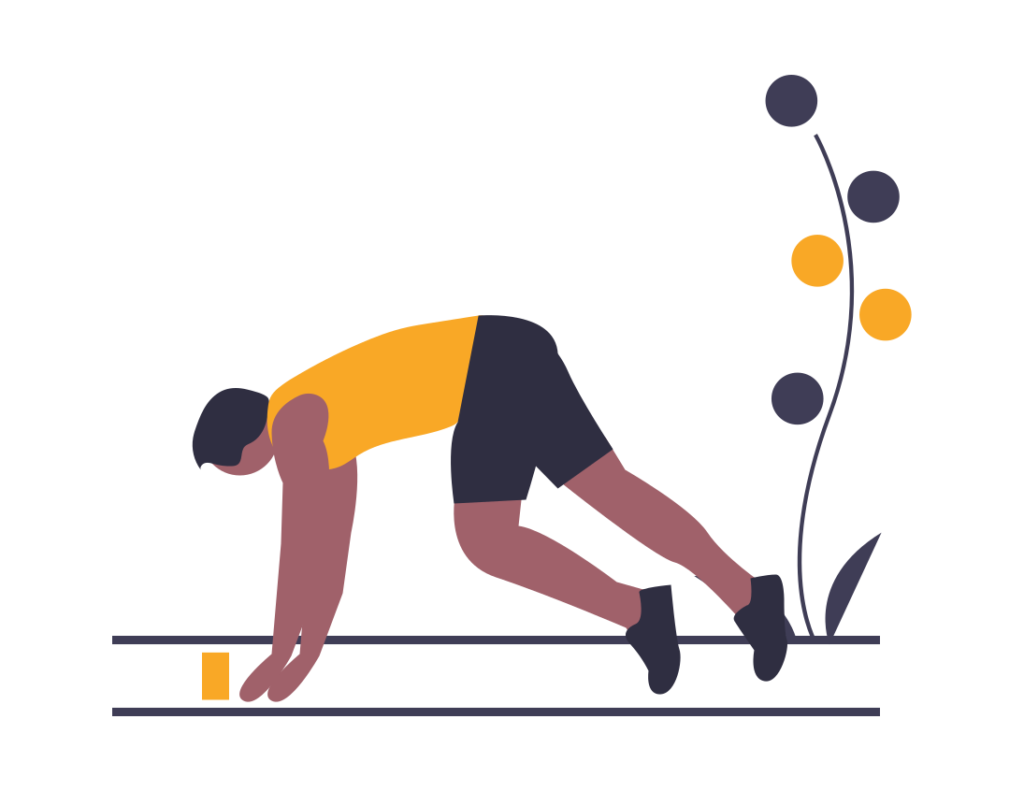
箱の中から何が見えるのか。
それは映画の封切り予定日が決まってからの楽しみにしておけばいいのかもしれません。
かつて『砂の女』を見たことがあります。
岸田今日子の持つ不思議なまでのおどろおどろしさが、砂丘の中に住む女の横顔をみごとに捉えていました。
勅使河原宏監督、武満徹音楽のコラボレーションが記憶に強く刻まれています。
あれを超える作品であることを強く期待したいです。
今回、せっかくのチャンスなので、もう1度読み直そうと考えました。
しかし実際に空気銃で箱男を撃とうとする男の様子を読んでいるうちに、疲れ果ててしまったというのが正直なところです。
この小説はいったい何なのでしょうか。
これが現代そのものの予兆だったのかどうか。
それさえも、今ははっきりとわかりません。
あらすじ
箱男は希望の最終形態を意味します。
あらゆる桎梏から完全に解き放たれた存在なのです。
ダンボールを頭からかぶり、小さなのぞき窓から一方的に世界を覗いて、うろつきまわります。
箱男に魅せられてしまったカメラマンのわたしは、自らもダンボールをかぶります。
そこにのぞき窓を開けて徘徊を試みるのです。
しかし本物になる道は簡単ではありませんでした。
さまざまな試練が襲いかかってくるのです。
わたしを追い、箱男の存在をそこから奪おうとするニセモノの医者や、箱男を完全犯罪に利用しようと企む軍医が登場します。
さらにはわたしを誘惑しようとする謎の女が現れ、わたしは完全に幻惑されます。
わたしのアイデンティティはどこにあるのか。
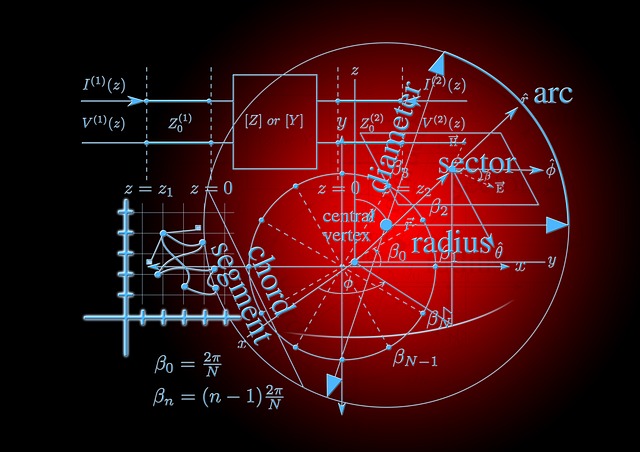
それが次第に見えなくなっていくのです。
しまいには、本物の箱男とは何かが見えなくなっていきます。
そんなものが存在したのかどうか。
それさえもあやふやになっていくのです。
謎の女も葉子とは何者なのか。
それも明らかにされません。
ストーリーを追いながら、小説を読もうとすると、途中で疲れ果ててしまいます。
登場人物としては他に医者の妻、愛人の看護士、過去の思い出の中に生きるピアノ教師が出てきます。
本当にこれが別人格なのかどうかもはっきりとはわかりません。
全てが同じ人間の断面なのかもしれないのです。
舞台は都市です。
さまよい歩く男は、小さな箱の覗き窓から何を見つめたのか。
そのすべてに答えはありません。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。



