野分の垣間見
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は野分(台風)の後、父親(光源氏)の邸宅、六条院を見舞った長男、夕霧の心の動揺を書きこんだ情景を読みます。
光源氏が35歳の時、六条の院が完成しました。
六条院は4つの町に分かれています。
太政大臣となった光源氏は紫の上、女三宮、明石の姫君とともに東南の春の町に住みます。
西南の秋の町は冷泉帝の秋好中宮、西北の冬の町には明石の君、北東の夏の町には花散里、玉鬘がそれぞれ住みました。
六条院は平安時代前期に実在した、源融(とおる)の河原院がモデルだといわれています。
総面積は約6万3500平米の巨大な邸宅でした。
東京ドームの1、5倍もあるのです。
それだけで、当時の権力の大きさがよくわかりますね。
ちなみに紫の上、28歳、明石の君、27歳、夕霧、15歳、明石の姫君が8歳です。
六条院では秋の草花が見事に咲き、庭いっぱいの見頃でした。

秋好中宮も里帰りしていて、源氏は管弦の遊びなどを催しかったのですが、中宮の亡き父親の命日にあたる月なので控えていたのです。
そこへ野分(台風)が近づいてきました。
せっかく咲いた花が散り、枝が折れるのではなかろうかと誰しもが心配していたのが、この話の発端です。
それまで長男(夕霧)は継母、紫の上の姿をみたことがありませんでした。
母親の顔さえ知らないという情景を現在、想像することはできませんね。
しかしいわゆる「垣間見」(かいまみ)を怖れ、間違いを怖れた源氏は、けっして継母、紫の上を子供に会わせることはありませんでした。
自分がたどった道を痛いくらいに、よく知っていたからです。
本文
南の御殿にも、前栽つくろはせたまひける折にしも、かく吹き出でて、もとあらの小萩、はしたなく待ちえたる風のけしきなり。
折れ返り、露もとまるまじく吹き散らすを、すこし端近くて見たまふ。
大臣は、姫君の御方におはしますほどに、中将の君参りたまひて、東の渡殿の小障子の上より、妻戸の開きたる隙を、
何心もなく見入れたまへるに、女房のあまた見ゆれば、立ちとまりて、音もせで見る。
御屏風も、風のいたく吹きければ、押し畳み寄せたるに、見通しあらはなる廂の御座にゐたまへる人、
ものに紛るべくもあらず、気高くきよらに、さとにほふ心地して、春の曙の霞の間より、おもしろき樺桜の咲き乱れたるを見る心地す。
あぢきなく、見たてまつるわが顔にも移り来るやうに、愛敬はにほひ散りて、またなくめづらしき人の御さまなり。
御簾の吹き上げらるるを、人びと押へて、いかにしたるにかあらむ、うち笑ひたまへる、いといみじく見ゆ。
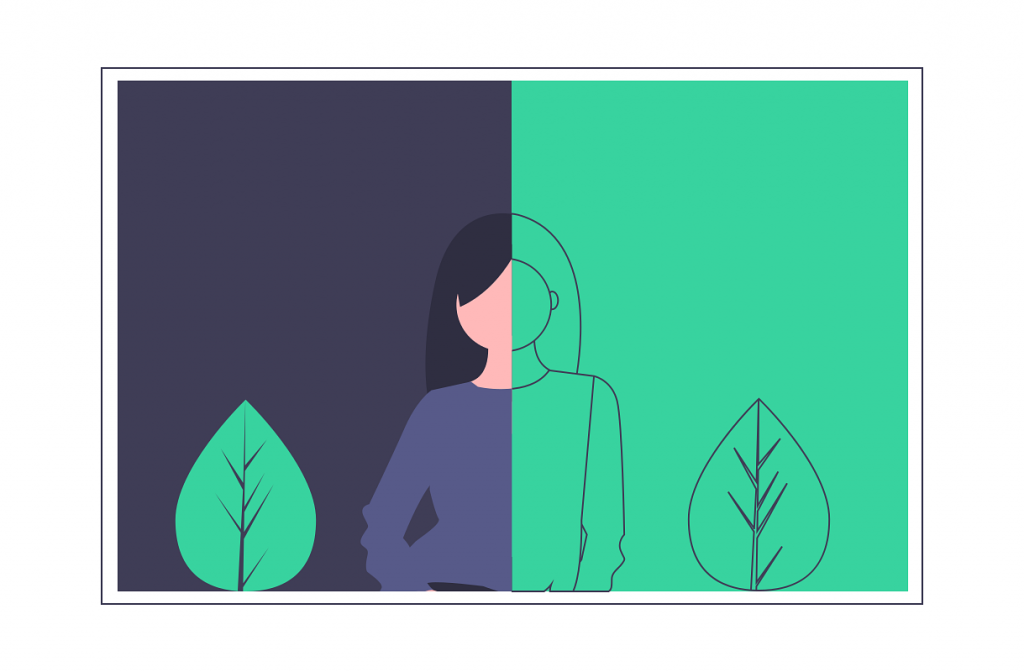
花どもを心苦しがりて、え見捨てて入りたまはず。
御前なる人びとも、さまざまにものきよげなる姿どもは見わたさるれど、目移るべくもあらず。
「大臣のいと気遠くはるかにもてなしたまへるは、かく見る人ただにはえ思ふまじき御ありさまを、いたり深き御心にて、もし、かかることもやと思すなりけり」
と思ふに、けはひ恐ろしうて、立ち去るにぞ、西の御方より、内の御障子引き開けて渡りたまふ。
「いとうたて、あわたたしき風なめり。御格子下ろしてよ。男どもあるらむを、あらはにもこそあれ」
と聞こえたまふを、また寄りて見れば、もの聞こえて、大臣もほほ笑みて見たてまつりたまふ。親ともおぼえず、若くきよげになまめきて、いみじき御容貌の盛りなり。
女もねびととのひ、飽かぬことなき御さまどもなるを、身にしむばかりおぼゆれど、この渡殿の格子も吹き放ちて、立てる所のあらはになれば、恐ろしうて立ち退きぬ。
今参れるやうにうち声づくりて、簀子の方に歩み出でたまへれば、
「さればよ。あらはなりつらむ」
とて、「かの妻戸の開きたりけるよ」と、今ぞ見咎めたまふ。
「年ごろかかることのつゆなかりつるを。風こそ、げに巌も吹き上げつべきものなりけれ。さばかりの御心どもを騒がして。めづらしくうれしき目を見つるかな」とおぼゆ。
現代語訳
紫の上の御殿でも、ちょうど庭先に植えた草木を手入れさせなさった時のことです。
今のように野分が吹き始めて、歌にあるように、根元の葉がまばらな小萩が露を落とすために、待ち迎えたにしては、激しすぎる風の吹く様子でした。
枝も折れてひっくり返り、まったく露もとどまることができないほど吹き散らすのを、紫の上は部屋の少し端近で御覧なさいました。
源氏の君が明石の姫君のお部屋にいらっしゃる時に、夕霧(源氏の長男)が参りなさって、東の渡殿の背の低いついたての上から、
妻戸が開いている隙間を何気なくのぞきなさったところ、女房がたくさん見えるので、立ち止まって音もたてないで見てしまったのです。
屏風も、風がひどく吹いたので、押し畳んで寄せているので、全てが丸見えです。
廂の間の御座所に座りなさっている紫の上は、他の女房にまじってわからなくなるはずもなく、気高く清らかで、
さっと照り映える感じがして、春のあけぼのの霞の間から、美しく樺桜が咲き乱れているのを見る気持ちがしました。
どうしようもなく、見申し上げる自分の顔にも移って来るように、魅力的な愛らしさは照り映え広がって、この上なくすばらしいご様子です。
御簾が引き上げられるの女房たちは押さえて、どうしたのだろうか、紫の上が笑いなさっているのが、たいそうすばらしく見えました。
花々が気がかりで、見捨てて入ることがおできになりません。
御前の人々の、さまざまにお姿がありのままに見渡されるので、目移りするはずもありませんでした。
父上である源氏の君が、自分(夕霧)を紫の上に全く近づけず、隔ててお扱いになっているのは、深い思慮があるのでしょうか。

見る人が普通には思うはずもない紫の上のすばらしく美しいご様子を、考え深い父上の心で、もしかするととご憂慮なさったのかもしれません。
そう思うと、何となく恐ろしくて立ち去る時、西のお部屋から、源氏の君が内の御障子を引き開けてお渡りなさったのです。
「とてもひどい、あわただしい風であるようだ。御格子を下ろしてしまいなさい。殿方たちがいるであろうに、丸見えだと困るよ。」
と源氏の君は紫の上に申し上げなさるのを、夕霧が再び近寄ってみると、紫の上が何か申し上げて、源氏も微笑んで見申し上げなさっておいでです。
源氏の君は親とも思われなくて、若々しく美しく優美で、すばらしい容貌の男の盛りそのものです。
紫の上は女盛りで、足りないことのない二人のご様子であるのを、夕霧は身にしみるほどに感じました。
さらに、この渡殿の格子も風が吹き開けて、自分が立っている所が丸見えになるので、恐ろしくなって立ち去ったのです。
参上した時のように咳払いをしてから、すのこの方に歩き出しなさったところ、
「思ったとおりだ。きっと丸見えになっていただろう。」
と源氏は言って、この妻戸が開いていたのだなあと、今初めて見て気づきなさいます。
「長年、紫の上を垣間見ることなどは全く無かったのに、風が本当に大きな岩も吹き上げてしまうはずのものだな。
それほど二人の御心を騒がして、めったにない嬉しい目を見たなあ。」と夕霧は思わずにはいられませんでした。
端近という表現
古典には端近(はしぢか)という表現がよく出てきます。
中世において、貴い位にいる姫たちは、男性に姿形を見られてしまうということを最も恐れたからです。
「若紫」の段では、紫の上も軒先から光源氏に覗き見られています。
その後、彼女は光源氏に奪い去られてしまうという展開になるのです。
はじめて継母の姿を自分の目で見た夕霧は、その美しさに驚きました。
父親がなぜ紫の上のそばに、他の男性を近づけないのかを実感として知りました。
その日の夜、継母の姿を垣間見た夕霧は心穏やかではありません。
それまで恋しく思っていた雲居の雁の存在が急にしぼみ、紫の上のことばかりが頭の中を駆け巡りました。
『源氏物語』には垣間見によって間違いがおこり、その後の展開が複雑化していくケースが幾つも出てきます。
猫が駆け抜けたはずみに、御簾が引き上げられてしまうシーンも有名ですね。
中にいた源氏の正妻・女三宮の姿がその瞬間、あらわになります。

その姿を頭中将(内大臣)の長男柏木がたまたま見てしまうのです。
ここから話は大きく展開し、その結果2人の間に生まれた子供が薫です。
源氏は自分が藤壺との間にしたのとおなじことを、次の世代の柏木にされるという皮肉な結果を迎えます。
因果応報といえば、それまでですが、このあと源氏物語が『宇治十帖』に進む1つの契機となりました。
今回はここまでで終わりにしましょう。
『源氏物語』くらい果てしない物語はありませんね。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました


