世間知らず
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は今まで読んだ古文の中でも、図抜けて愉快な話をご紹介しましょう。
『徒然草』は兼好法師の筆のままに書かれた傑作ばかりです。
その内容は実に多岐に渡っています。
つい先日、このサイトでも記事にしたものなどは王朝物語そのものでした。
そうかと思うと有職故実に関するものや、趣味の好き嫌いまで、本当にユニークな内容のものが多いです。
数ある段の中で、ことに面白いのが仁和寺のお坊さんの話です。
このお寺を訪問したことはありますか。

石庭で有名な龍安寺のすぐ近くにあります。
本当に立派な寺院です。
徒然草には仁和寺を扱った話がいくつも出てきます。
御室の仁和寺と呼ばれ、真言宗御室派の総本山です。
888年に創建された皇室とゆかりの深い門跡寺院で、出家後の宇多法皇がお住まいになっていました。
有名なのは御室桜です。
少し遅咲きですがみごとなものです。
これほどにありがたいお寺をどうして兼好法師は次々と滑稽話の話題にしたのでしょうか。
本当に不思議です。
1つの理由としては、彼が仁和寺近くの「双ケ丘」に住んでいたということも大きな要因だと思われます。
よほど親近感があったのでしょうね。
あるいは仁和寺が由緒あるお寺で学問の最高学府ということで、少しバカにする対象だったと考えることもできます。
兼好法師は権威を嫌う人でしたからね。
ということで、現代風に考えるといわゆる学者バカを揶揄し、世間知らずで非常識な連中だとコケにするという心理的な側面があったのかもしれません。
滑稽な話の原文
これも仁和寺の法師、童の法師にならむとする名残とて、おのおの遊ぶことありけるに、酔ひて興に入るあまり、傍らなる足鼎を取りて、頭にかづきたれば、つまるやうにするを、鼻を押し平めて、顔をさし入れて舞ひ出でたるに、満座興に入ること限りなし。
しばしかなでてのち、抜かむとするに、おほかた抜かれず。酒宴ことさめて、いかがはせむと惑ひけり。
とかくすれば、首のまはり欠けて、血垂り、ただ腫れに腫れみちて、息もつまりければ、打ち割らむとすれど、たやすく割れず。
響きて堪へがたかりければ、かなはで、すべきやうなくて、三つ足なる角の上に帷子をうちかけて、手を引き杖をつかせて、京なる医師のがり、率て行きける道すがら、人のあやしみ見ること限りなし。

医師のもとにさし入りて、向かひゐたりけむありさま、さこそ異様なりけめ。
ものを言ふも、くぐもり声に響きて聞こえず。
「かかることは、文にも見えず、伝へたる教へもなし。」
と言へば、また仁和寺へ帰りて、親しき者、老いたる母など、枕上に寄りゐて泣き悲しめども、聞くらむともおぼえず。
かかるほどに、ある者の言ふやう、
「たとひ耳鼻こそ切れ失すとも、命ばかりはなどか生きざらむ。ただ力を立てて引きたまへ。」
とて、藁のしべをまはりにさし入れて、かねを隔てて、首もちぎるばかり引きたるに、耳鼻欠けうげながら抜けにけり。
からき命まうけて、久しく病みゐたりけり。
————————-
どうでしょうか。
意味がわかりましたか。
比較的に理解しやすい言葉で書いてありますね。
高校時代に古文の授業で習った記憶はありませんか。
ぼくも何度扱ったかわかりません。
その度にこのお坊さんの姿が目に浮かんでしょうがありませんでした。
あらすじと意味
これも仁和寺の法師の話です。
子どもが法師になろうとする別れということで、それぞれが音楽や詩歌、
舞などを楽しんだことがあったのですが、酔って面白がるあまり、傍らにある足鼎をとって、頭にかぶったところ、つかえるように感じたのに、鼻を押して平らにして、顔を差し入れて舞い出たところ、その場にいる者全員が面白がることこの上ありませんでした。
しばらく舞を舞ったのちに、頭にかぶっていた足鼎を抜こうとすると、まったく抜くことができません。
宴も興ざめして、どうしたらよいだろうかとうろたえました。
なんとか抜こうとあれこれとすると、首の周りは傷ついて、血が垂れ、
ひたすら腫れに腫れ、息も詰まってきたので、足鼎をたたき割ろうとしましたが、簡単には割れませんでした。
鼎をたたいたときの音が頭に響いて我慢できなかったので、打ち割ることができず、手の施しようがありません。
そこで足鼎の3つの足の上に帷子をかけて、手を引き杖をつかせて、
都の医者のもとに、連れて行った道中ずっと、人が不思議に見ることこの上ありませんでした。
医者のところへいって医者に向かって座った有様は、さぞかし風変わりであったことでしょう。
ものを言うにも、鼎の内にこもってはっきりしないし、響くので周りの人には聞こえません。
「このようなことは書物にも見られないし、受け継いでいる教えもない。」
と医者が言いますので、法師たちはまた仁和寺に帰って、近親の者、老いた母親らが、枕元に集まり座って泣き悲しむものの、本人は聞いているだろうとも思えませんでした。
こうしているうちにある者が言うことには、
「例え耳や鼻が切れてなくなるとしても、命だけはどうして助からないことがあろうか。ひたすら精一杯引っぱりなさい。」
というわけで、わらの芯を首の周りにさし入れて、足鼎と首との間を離して、首もちぎれてしまうぐらい引っ張ったところ、耳や鼻は欠けて穴が開いたものの足鼎はなんとか頭から抜けたのでした。
その法師は危うい命を拾いましたが、長い間患い続けたということです。
足鼎というのがなんだかわかりませんね。
鼎という文字は「かなえ」と読みます。
元々、中国などで肉や魚などを煮炊きする土器だったものが、次第に青銅などでつくられるようになり、古代の祭礼などに使われるようになったと言われています。
博物館などで見たことがありませんか。
飾り物としてお寺などにおかれていたのかもしれません。

それを酒の勢いでかぶって踊ったところまでは、実に愉快じゃないですか。
お祝いの席だっただけに、遊び心がたっぷりあったものと思われます。
やっと一人前になれるという祝いの宴席です。
本来なら、お酒はご法度ですが、こういう時は別なんでしょう。
しかしそれが抜けなくなったあたりから、話は急速に調子がかわります。
医者も困ったでしょうね。
親戚も親も悲しんだことでしょう。
まさか、一生、この化け物みたいな鼎を頭にかぶっているワケにはいきません。
おそらく青銅製だったのではないでしょうか。
たたき割ることもできず、首はどんどん腫れてきます。
似たような話
現代ならなんでしょうか。
似たようなケースだったら指輪ですかね。
よく抜けなくなっちゃったという話を聞きます。
今なら電動のカッターでやるところですが、昔はそんなものもないし。
藁を首のまわりに入れ、少し滑りをよくしてそれで一気に引き抜いたのです。
命あってのものだねですから。
その後、このお坊さんはしばらく寝込んじゃったみたいです。
この話を読むたびに思い出すのが、ぼくの娘のことです。

食事をするテーブルに座る前、椅子で遊んでいたんでしょうね。
なんとなく、椅子の背もたれのある桟のところに首をつっこんじゃったのです。
子供の頭は想像以上に柔らかいです。
するっと入ってしまったんですね。
泣いた、泣いた。
泣きました。
しかしいくら泣いてももう抜けません。
今度は耳がひっかかってダメなのです。
まさか一生、椅子と暮らすワケにもいきませんので、ノコギリを持ち出し、立派な椅子の背もたれを切りました。
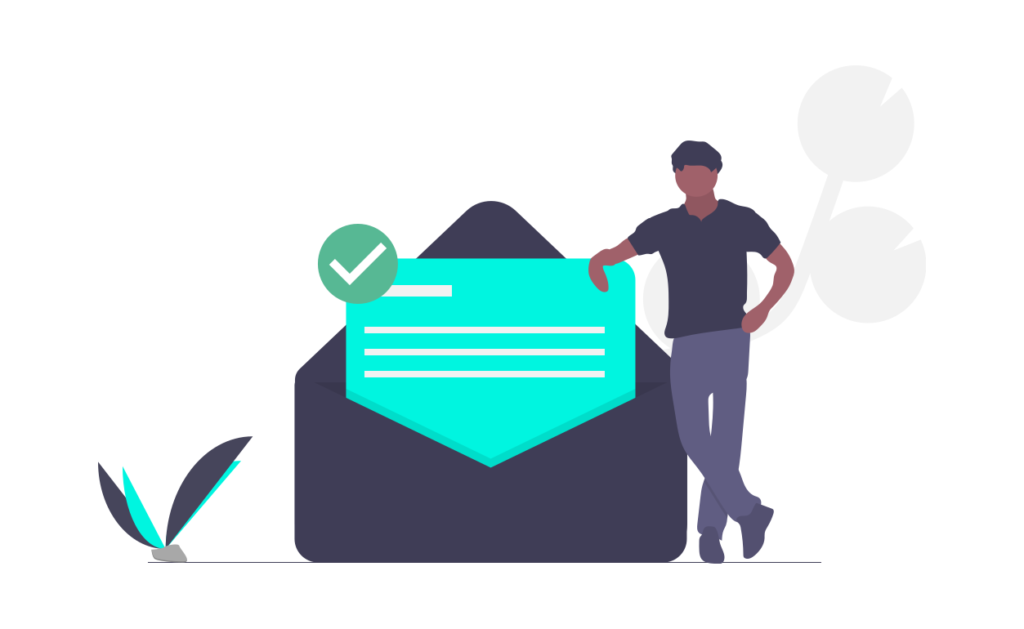
その間も泣いてましたね。
とうとう一脚は使い物にならなくなってしまったのです。
どうしてもこの話を読むと、あの時のことを思い出しちゃいます。
3~4歳の頃のことです。
今となっては懐かしいです。
兼好法師はどこでお坊さんの話を耳にしたんでしょう。
しめしめというので、ネタ帖に書いておいたのかもしれません。
本当に面白い人です。
近所にいそうなオジサンみたいです。
是非、もう一度この段を読み返してみてください。
人間は昔から大して進歩をしてないとしみじみ思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。


