 小論文
小論文
【2022年度小論文入試予想】ジェンダー・環境・SDGsがカギ
 小論文
小論文 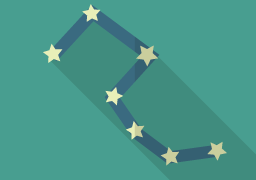 本
本 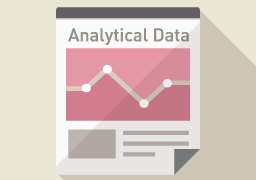 小論文
小論文 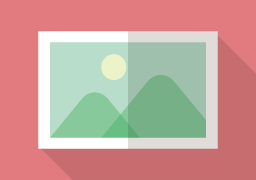 小論文
小論文  小論文
小論文  小論文
小論文  学び
学び  小論文
小論文 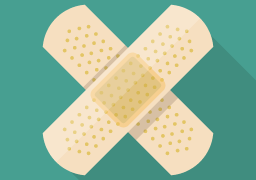 ノート
ノート  ノート
ノート  小論文
小論文  ノート
ノート  小論文
小論文  小論文
小論文 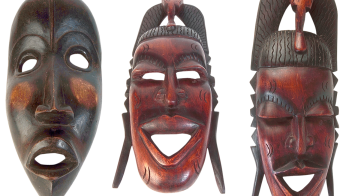 本
本  ノート
ノート  ノート
ノート  小論文
小論文