わかるとは何か
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
誰もがよく使う言葉に「常識」というのがありますね。
毎日の暮らしの中で、私たちは無意識によく使っています。
ここではその常識という言葉の中身を深掘りしてみようと思います。
何気なく口にはするものの、どこまで本当に皆知っていることなのかと考えると少し不安になります。
だれもが「わかる」ということばを簡単に使いすぎているのです。
「きみの気持ちはよくわかる。」
よく耳にする表現です。
しかし本当に相手のことを理解して発言しているのでしょうか。
かなり怪しいような気もします。
誰もが何気なく頻繁に使っているからこそ、かえって怖いのです。
今回の文章は解剖学者、養老孟司氏の『バカの壁』から引用したものです。
現代人のものの見方には根本的な問題があるのではないかという視点から、テーマを大きく広げた本です。
大ベストセラーになりました。
誰もがこの本のタイトルを知っているはずです。

しかしその内容に潜んでいる怖さについて本当に理解している人は、あまり多くなかったのではないでしょうか。
むしろ、それくらいのことはわかっているという軽いレベルで終わった気さえします。
実はこの認識こそがいちばん怖いのです。
特に日本人は、1つのテーマを突き詰めるということが苦手です。
本来理解不能なものをわかったような気になって、ついそのままにしてしまうという傾向があります。
理解することの難しさ
この著書の論点は、「理解」することの難しさを再認識しようということです。
自分の世界をも含めて、他者の内面まで理解するのは、不可能に近いのではないかというのが彼の基本的な考え方です。
もっといえば、他者の肉体の痛みや、心の痛みを理解するとはどういうことなのかという問題です。
この世に「客観的な真実」というものが本当に存在するのかどうか。
それを理解するとはどういうことなのか。

考えれば考えるほど、内容が複雑になります。
日本人はもしかすると、ある程度考えれば、必ず答えはあるはずだと簡単に信じすぎているのかもしれません。
それが一番厄介な体質だともいえます。
いったい「わかる」とはどういうことなのか。
筆者の文章の一部をここに掲載しましょう。
本文
現実のディテールを「わかる」というのは、そんなに簡単な話でしょうか。
実際には、そうではありません。
だからこそ人間は、何か確かなものが欲しくなる。
そこで心の平安を得るため、宗教を作り出してきたわけです。
キリスト教、ユダヤ教、イスラム教といった一神教は、現実というものは極めてあやふやである、という前提の下で成立したものだと私は思っています。
つまり、本来、人間にはわからない現実のディテールを完全に把握している存在が、世界中でひとりだけいる。
それが「神」である。
この前提があるからこそ、正しい答えも存在しているという前提ができる。
それゆえに、彼らは科学にしても他の何の分野にしても、正しい答えというものを徹底的に追求できるのです。

唯一絶対的な存在があってこそ「正解」は存在する、ということなのです。
ところが私たち日本人の住むのは本来、八百万の神の世界です。
ここには、本質的に真実は何か、事実は何か、と追求する癖がない。
それは当然のことで、「絶対的真実」が存在していないのですから。
これは、一神教の世界と自然宗教の世界、すなわち世界の大多数である欧米やイスラム社会と日本との大きな違いです。
私自身は、「客観的事実が存在する」というのはやはり最終的には信仰の領域だと思っています。
なぜなら、突き詰めていけば、そんなことは誰にも確かめられないのですから、今の日本で一番怖いのは、それが信仰だと知らぬままに、そんなものが存在する、と信じている人が非常に多いことなのです。
誰にもわからない
筆者の文章に次のような表現があります。
ここが一番のポイントかもしれません。
ーーーーーーーーーーー
もちろん、私は言葉による説明、コミュニケーションを否定するわけではない。
しかしそれだけでは伝えられないこと、理解されないことがあるというのがわかっていない。
そこがわかっていないから、「聞けばわかる」「話せばわかる」と思っているのです。
ーーーーーーーーーーー
それでは私たちはどうすればいいというのでしょうか。
その具体的な方法について考えられることを具体的に示し、その理由を説明して下さいという問題があったとしたら、あなたはどう解答しますか。
例として、彼の文章に陣痛の痛みというのが登場しています。
男子と女子では同じ話をしても全く反応が違うのだそうです。
女子は自分のこととして、非常に熱心に聞くのに対して、男子はどこまでも他人事というレベルに陥りやすいのだとか。
実際に出産シーンに立ち会ってみれば、また別の感情が沸き上がるかもしれません。
いずれにしても、あらゆる事件や事実を目の前で体験するなどということは不可能です。
その時の悲しみや不安を「わかる」というのは、どういう意味を持つのか。
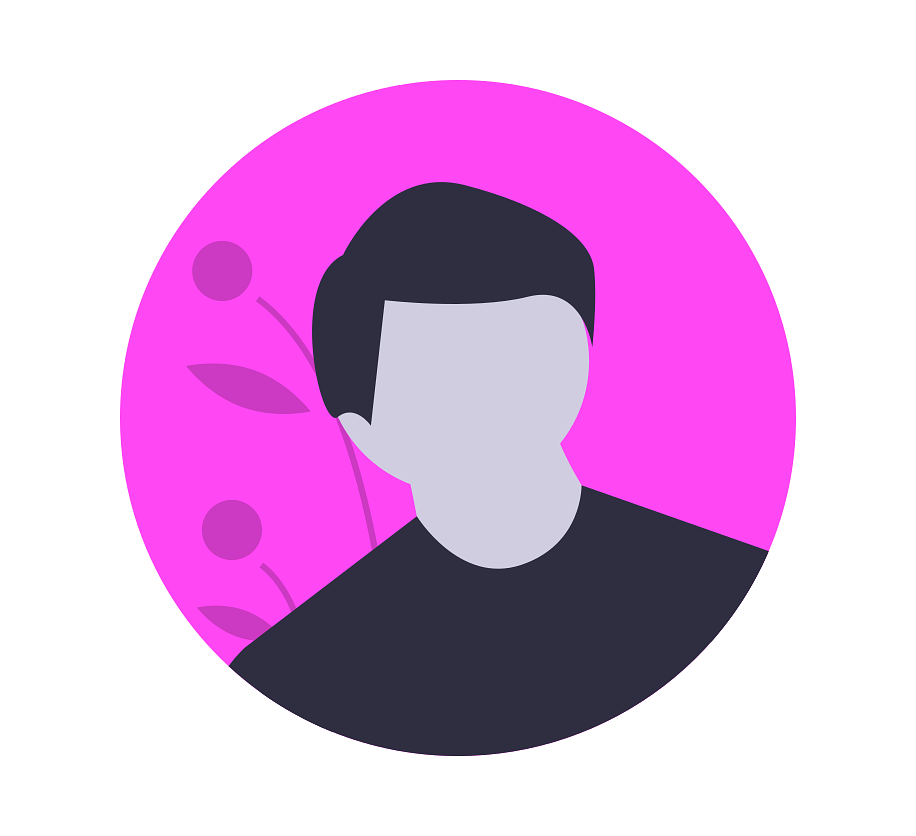
ますます話の筋がみえなくなっていきますね。
筆者の文章の最後のところにある内容は大きな示唆に富んでいるといえます。
ーーーーーーーーーーー
世界というのはそんなものだ、つかみどころのないものだ、ということを昔の人は誰もが知っていたのではないか。
その曖昧さ、あやふやさが芥川龍之介の小説「藪の中」や黒澤明監督の「羅生門」のテーマだった。
ところが現代においては、そこまで自分たちがものを知らないということを疑う人がどんどんいなくなってしまった。
ーーーーーーーーーーー
人間は確かなものが欲しいのです。
だから最後は「神」に頼るのかもしれません。
特に一神教の人びとは、そこにすがることで、なんとか窮地を脱することが可能になるに違いありません。
そうでなければ、あれほど熱心にメッカへの巡礼などを行うことなどないはずです。
一神教は現実がいかにあやふやなものであるかという前提にたって出来上がっているといいます。
だからこそ、人間にはわからないものを完全に把握している存在への信仰が深いのです。
ところが本来わからないものがそこにある事実を認められずに、日本人はそれが理解できると考えてしまう性癖を持っています。
客観的事実が存在していると考えている日本人が多いのです。
だから知識さえあれば、「わかる」のではないかと錯覚するのです。
知識と理解は別
日本人は多く学問をした人間は、世界の本質をわかっているのではないかと考えがちです。
実はここが一番怖いのです。
知識をもっているだけでは本当はダメなのです。
物知りな人間が世界を理解しているということにはなりません。
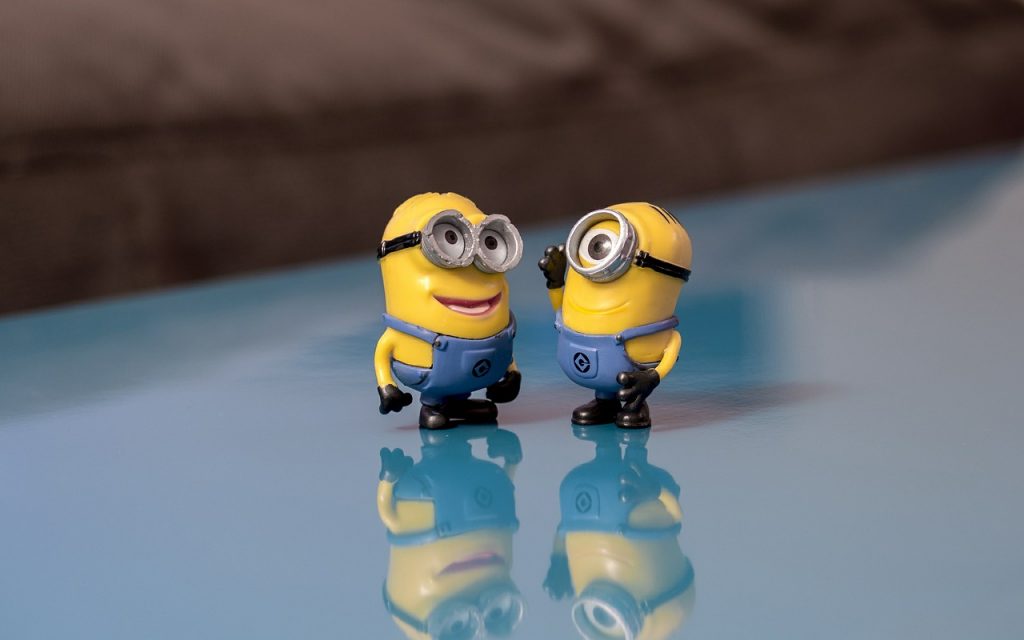
ものがわかっているというのは、知識があることとは全く別物なのです。
しかし多くの人はそうは考えていないようです。
学問を修めた人ほど客観的な事実を認識し、世界の構造を知っていると思いがちなのです。
これが大きな誤りであることを、どれほどのことが知っていることか。
そこがこの文章のポイントです。
日本人の精神構造
日本人の精神構造がこの文章の中に色濃く示されています。
示唆に富んだ指摘です。
この過誤はどこから出てくるのか。
基本は日本人の思考プロセスにあると思われます。
つまり知ろうと思えば、なんでも知ることができるという一種の信仰を持っているという事実です。
科学万能といえばいえるかもしれません。

もしかすると、この考えは世界に共通しているともいえます。
ネット社会は全ての事項について、短時間で正解を出すことに慣れ過ぎています。
ある意味で解答がないということを許さないのです。
それが人間の驕りにつながらないことを祈るしかありません。
自然への畏怖を忘れてしまったことで、ますます厄介なことになっています。
宗教との関係についてあなたも考えてみてください。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


