ネット時代
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回はネット時代の現実をどう認識するかについて考えます。
これから人間はどう生き、それをどう文章にまとめればいいのかという、厄介なテーマです。
大変難しい主題ですが、参考になるものがありました。
哲学者、吉岡洋氏の「ネット論」です。
彼の専門は美学、芸術学、現代思想など多岐にわたります。
ここに示してあることは、多くの人がすでに気づいていることばかりです。
ある意味、既読感に満ちています。

しかしそれならば、あなたはその状況の中でどうするのかという問いを突き付けられたとき、二の句が出ません。
本当はなんとかしなくてはならないと誰もが思っているはずなのです。
ところがそこから抜け出すための方法が全くみえない。
あるいは見たくないといった方が妥当なのでしょうか。
現実はここに示された以上に先に進んでいます。
生成AIの出現が人間の能力を遥かに超えつつあるからです。
何も考えなくても、問いに対する最適な回答をAIは短時間でひねり出してくれます。
ただしそれが本当に的確であるかどうかの検証は置き去りにされたままです。
当面の危機はそれで回避できるというレベルでしょうか。
人間はますます観客席に座ったまま、無気力になっていかざるを得ません。
いわば、傍観者の立場を余儀なくされています。
その状況をどう文章にまとめればいいのでしょうか。
筆者は吉岡洋、タイトルは『ネットで世界は狭く情報は身体を離れる』です。
この文章で論じていることを理解し、あなたにとってネット時代に生きる覚悟を示す文章を800字程度で書いてみてください。
現在の立ち位置がよく見えてくるはずです。
課題文
世界がとても狭くなってしまった。
ここには2つの意味が含まれている。
第一にメディアの発達によって、世界のさまざまな場所で起こっている出来事を、簡単に知ることができるようになった。
新聞、写真、電話、映画、テレビ、そしてインターネットのおかげで、空間的距離や時間的遅れはどんどん縮小されてゆき、その結果、世界はたしかに「狭く」なった。
メディアの中では、自爆テロもオリンピックも国会での証人喚問も、あたかも目の前で繰り広げられている一連のショーのようだ。
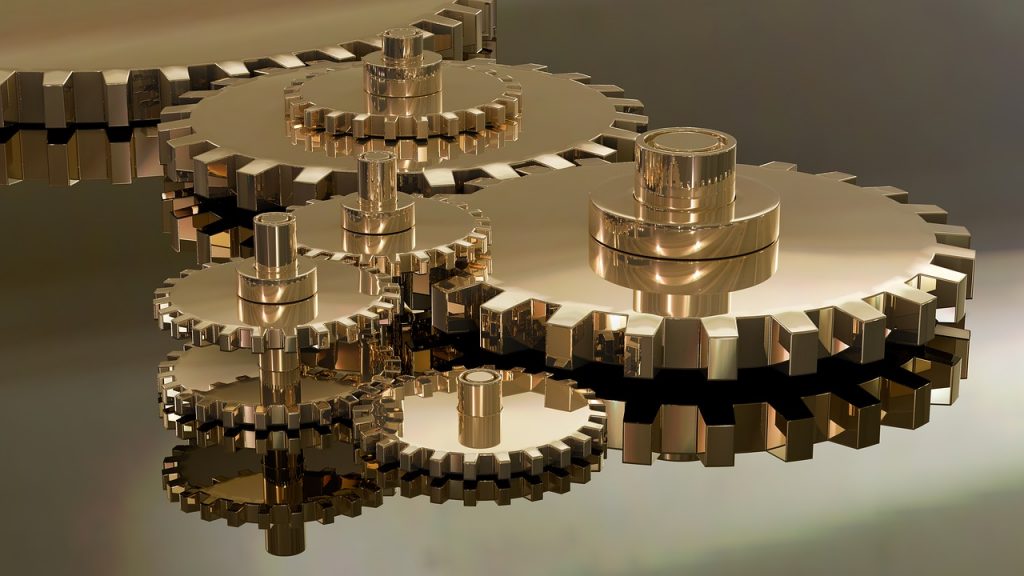
それらは悲しみや怒りや喜びといった強い感情を引き起こすけれど、自分自身は日常生活という「観客席」にすわったままなのである。(中略)
かつては、わずかな情報を手に入れるために、図書館に通って片っ端から資料を調べたり、注文した外国雑誌を何カ月も待ったりしなければならなかった。
それはたしかに、とても不便なことであった。
けれどその「不便さ」がある意味では、情報の意味をゆっくり考える猶予を与えてくれていたとも言える。
また、ある種の情報が手に入りにくいことは、それを獲得し自分のものにしようとする強い動機づけになってもいた。
逆説的に聞こえるかもしれないが、そうした「効率の悪さ」が、とても複雑な意味の場を形づくっていたのである。
長い時間のかかる作業は人にいろいろなことを考えさせたし、その途中で思いがけないものがみつかったりした。
それに対し、探しているものがすぐ見つかる情報空間とは、裏をかえせば「単に探しているものしか見つからない」退屈な場所だともいえる。
こんなふうに言ったからといって、昔を懐かしんでいるわけではけっしてない。
そうではなく、人間がつねに身体をともなった存在であること、情報に意味を与えるのはこの身体を通してしかありえないことを、今一度思い出そうと言っているだけだ。
インターネットにどっぷりと浸りきるのも、逆にそれを拒絶するのも得策とは思えない。
大切なのはむしろ意識の中で「頻繁にスイッチを切る」習慣かもしれない。
世界をオープンにする
情報が簡単に手に入ってしまうので、目的のもの以外のことを調べたり考えたりすることがないという源現実は重いです。
情報がたくさんありすぎるので、それをどう利用すればいいのかわからなくなってしまいがちなのです。
確実に情報過多な現象と呼べます。
暇な時間があると、すぐにスマホを手にしてしまうという生活も垣間見えます。
SNS全盛の時代の持つ一番厄介な現象です。

僅かな時間があっという間に求めていない情報で埋め尽くされてしまうのです。
情報が手に入りにくいことが、情報を自分のものにすることにつながることを忘れてしまう現代の悲劇と呼んでもいいのではないでしょうか。
筆者の論点は大変わかりやすいですね。
世界がとても狭くなってしまい、その結果として知識と身体を切り離すという、生き物としての無理を強いられるようになっているのです。
本来、知識は身体に結びついていなければなりません。
つねに実感をもって、自分自身の掌の感覚や、目視を通じて理解に至るのです。
しかしネットはそれを一瞬でおこなってしまいます。
その結果、「わかったつもり」「経験したつもり」の疑似体験だけがうずたかくなります。
ところが元々、身体に根差した知識や経験ではないため、忘れるのも早いのです。
自分の芯に深く根差した事実にはなりません。
身体の最深部に届いていないのです。
知識が狭い世界の中に安住するようになり、身体と切り離されるようになってしまいます。
うわべだけの知識に偏ってしまいがちです。
筆者の述べる通り、人間はつねに身体を伴なった存在であり、情報に意味を与えるのは身体を通してしかありえません。
それがなされずに、コスパとタイパだけを追求していった結果が悲しいものになるのは、ある意味当然のことなのです。
生成AI時代の知識
さらにいえば、生成AIが登場して以来、答えを知ったつもりになる時間が以前よりも増えたのではないでしょうか。
正しい回答かどうかを身体で確認する作業をしないまま、すぐ次の作業に入ってしまうのです。
受験生にとって、小論文の書き方などにも通じます。
自分の身体に深く根差していない知識などを、ある意味「知ったかぶり」で書いてしまうことによって、内容が浅薄になる可能性もあるのです。
通常、小論文はそう単純には書けないのが普通です。
どのレベルに自分が達しているのかを、判断するのが非常に難しいからです。
採点基準もどこにあるのか、はっきりしません。
もちろん、構成力、表現力、語彙力、論理性などの基本的な要素をチェックされるのはあたりまえのことです。
しかしそれ以上に、書き手がそのテーマをどの程度自分のものとして考えたのかということをどう判断されるのかも不明です。
つまり生成AIなどが書くような文章だけでは、高い評価を得ることはできません。

テーマさえ与えれば、ChatGPTなどは非常に短い時間で、いかにも小論文らしい文章を作りあげます。
しかしこうした文章は採点者の心に響きません。
全体に一般論が網羅してあり、基本的な内容は整えられているのですが、読後感がよくないのです。
判断の論拠があくまでも一般的なものに偏り、受験生の芯に根差していないからです。
つまり誰でも書ける、ごくありきたりの文章になってしまっています。
誰がどの視点で書いたのかもはっきりしません。
そこに身体に根差す知識や経験がないのです。
生成AIは賛成の立場で書けといえば、すぐにその路線にのっとった文章をつくります。
その反対も短時間で可能です。
しかしそれでは意味がありません。
小論文で必要なのは、多様な「問い」に答えられる受験生の能力そのものです。
書き手の経験や知識をどう組み立てるのかという基本的なセンスの他に、自分の言葉でまとめる力がどの程度あるのかというところがポイントなのです。
逆にいえば、自分の体験をきちんと把握するための時間が必要です。
意識的に情報を遮断する習慣を身につけるべきではないかということも考えなくてはいけません。
何も考えずにいると、情報の中にうずもれてしまい、何も言えない状態になってしまいます。
自分自身が世界の中でどういう位置にいるのかという意味付けのないまま、知識を無暗と外に求めては意味がありません。
インターネットによって情報と身体が切り離されてしまったわれわれは、時に自らを情報から遮断することが必要なのです。
ある意味、頼るものがない場所に自分をさらし、そこから出てくる言葉に頼って文章を書いていく作業が大切なのです。
確かに800字で文章をまとめるのは難しいかもしれません。
しかしそれをしなくては意味がないのです。
ここにある論点を参考にして、あなたの考え方を書き込んでみてください。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


