阿弥衆の役割
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回はデザイナーという職業の起源と、存在意義について考えてみます。
課題文は日本を代表するデザイナーの1人、原研哉氏です。
彼は「阿弥衆」がなぜ日本で生まれたのかという背景を、著書で分析しています。
岩波新書『日本のデザイン』がそれです。
「阿弥」とは何でしょうか。
能の観阿弥、世阿弥を筆頭に、立花の立阿弥、作庭の善阿弥などの名前を聞いたことがある人もいるはずです。
考えてみると、不思議なネーミングですね。
阿弥とは元々、浄土宗の一派である時宗の僧の法名につけられていたものだそうです。

戦さに同道し、亡くなった人の念仏を唱えることもありました。
それがやがて負傷者の手当てや日常の世話にまで及びます。
その中で芸道に秀でた者が、やがて「阿弥」を名乗るようになりました。
阿弥という表現には、「美」の意識がついて回るということを覚えておいてください。
それが能、作庭、生け花、茶の湯、建築などの世界に広がっていったのです。
いずれにしても日常の生活から、少し外れた生き方であることは明らかです。
『日本のデザイン』の中から「阿弥衆とデザイン」の部分を抜き書きします。
このテーマは大学入試にかなり多く出題されました。
小論文のテーマとしても十分に成立する内容を持っています。
原研哉氏文章の前半の部分を書き抜きます。
本文
阿弥とは、やや乱暴にたとえるなら、優れた技能や目利きの名称に付す「拡張子」のようなものだ。
最近は、そのデータがどのソフトウェアでできたかを表記する目的でデータの名称の最後に「.doc」などと付す。
意味や機能は異なるが、ニュアンスとしてはこれに似ている気がする。
だから室町以降の人の名前に「阿弥」と付されていたなら、「.ami」、なるほどその筋のソフトウエアを共有するアーティストか、と考えればだいたい遠からずの素性を理解できる。(中略)
文化というものは常に、時を制する力とつながり、また拮抗して呼吸している。
それは武力であったり、経済力であったり、政治力であったり、ポピュリズムであったりするが、そういう力が、力であるゆえの穢れや毒を拭うように、感覚的な洗練としての美を欲するのである。
このような欲求を文化の端緒というべきかどうかはともかく、倦まずたゆまずその要望に応え、美を供給していく役割を担う人々がいる。
美に触れ続けるということは、時代の趨勢を作るパワーとは異なる位相に、人間の感覚のときめきを生み出すもうひとつの中心があることを意識し続けるということである。(中略)
阿弥衆の仕事に、自分が感じるそこはかとない共感は、この過度なる感覚のやり場に起因する微かなる葛藤と放蕩をそこに感じるからである。
足利幕府であれ、資本主義のもとで君臨する企業であれ、力を洗練されたイメージへと変容させて用いたいという希求に、半ば応え、半ばあらがうという状況を共有しうる立場として、僕はこれらの技能集団に直感的なシンパシーを感じるのである。(中略)
阿弥衆とはすなわち、固有名詞で室町文化のクライアント筋から、指名され頼りにされた才能なのである。
純粋芸術とは異なる文化諸般のアクティビティを担うという性格上、僕は日本におけるデザイナーの始原をここに感じるのだ。
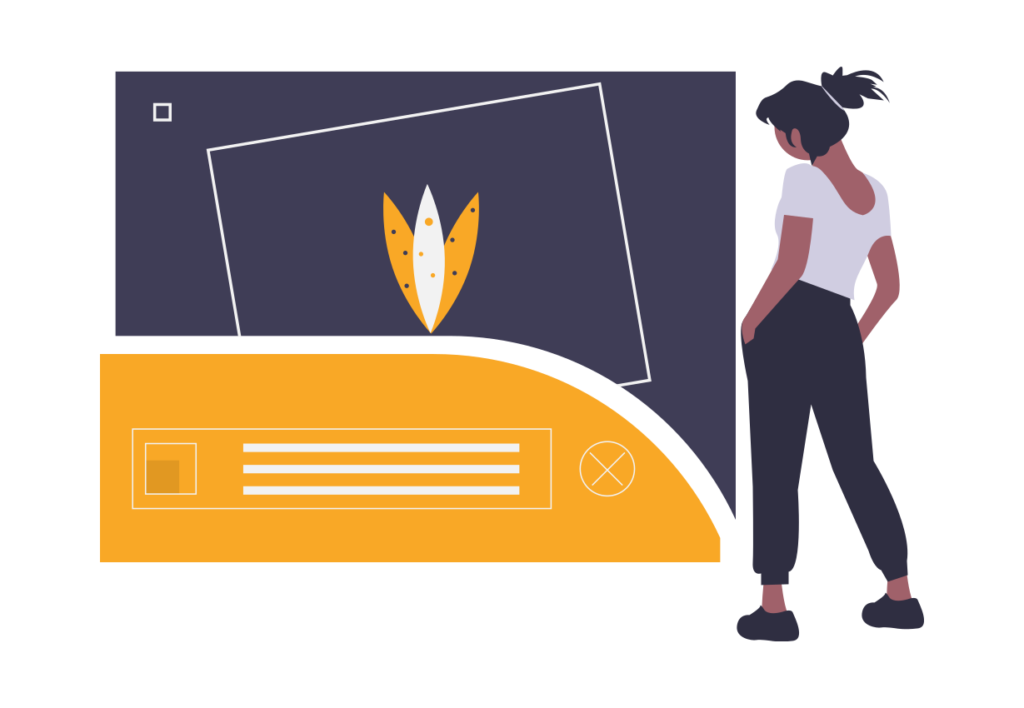
東山文化とは、阿弥衆と、義政のような文化のディレクターとの、ダイナミックな美意識の交感によって生み出されたものだと考えていいかもしれない。
阿弥衆との積極的な交流を介して、義政を筆頭とする有力な文化リーダーたちの感覚もどんどん豊かになっていったのだろう。
このあたりは今日のクライアントとデザイナーの関係にも似ている。
出自に関係なく才能を有する者たちは、「阿弥」の付された名前を与えられ、文化の最前線にかり出される一方で、連歌の会などにも高貴な身分の人々に交じって出席を許されたりしている。
善阿弥と観阿弥の場合
銀閣寺に代表される東山文化をつくったのは、足利義政です。
彼が重用した庭師は善阿弥と言われています。
しかしその出身は低い階級でした。
河原者という呼ばれる被差別の出身だったのです。
後の時代、歌舞伎役者のことを河原乞食と呼んだこともあります。
出雲の阿国に代表される芸人たちも、こちら側の人間ではありませんでした。
みな彼岸に近い河原で暮らしているものと蔑視されたのです。
それでも善阿弥は人並みはずれた美意識の持ち主でした。
善阿弥作と言われている相国寺蔭涼軒、高倉御所泉水、相国寺山内睡隠軒などがあります
応仁の乱の最中には奈良に移り、興福寺大乗院なども手掛けたといわれています。
義政にとって、出自はあまり意味をもちませんでした。
純粋に彼の技能が評価されたのです。
庭を「美」の世界にまで昇華する表現力を持っていさえすれば、たとえどのような生まれの人間であってもよかったのです。

そのことは観阿弥、世阿弥にも言えます。
観阿弥が下層の芸能者であったことは間違いありません。
その出自もはっきりとはわかっていないのです。
40歳を過ぎた頃、やっと世に出られました。
彼の舞が他の演者のものとは明らかに違っていたからです。
夢幻能と呼ばれるこの世とあの世との境を行き来する作劇術も、多くの人に受け入れられました。
やがて今熊野において将軍義満に認められるようになり、観阿弥の大和猿楽は、一地方の芸能から、天下の芸能へと昇華したのです。
その背景に義満の庇護があったことは間違いありません。
世阿弥も父のそばで、舞の本質を学びました。
後に佐渡に流されたことを御存知でしょうか。
三代将軍足利義満の寵愛を受けていた時代はよかったのです。
しかし六代将軍足利義教の怒りにふれ、1434年に佐渡に流されました。
これが芸能者の宿命だという鏡のような人生だともいえますね。
葛藤と放蕩
原研哉氏の文章を少し読み込んでみましょう。
ポイントになる部分の文章をもう1度書きます。
阿弥衆の仕事に、自分が感じるそこはかとない共感は、この過度なる感覚のやり場に起因する微かなる葛藤と放蕩をそこに感じるからである。
この文の意味がわかりますか。
これを自分の言葉で書きなさいという問題が考えられます。
小論文の問題の前段として、設定することが可能です。
ここにこの文章全体のキーワードが潜んでいます。
内容を整理しましょう。
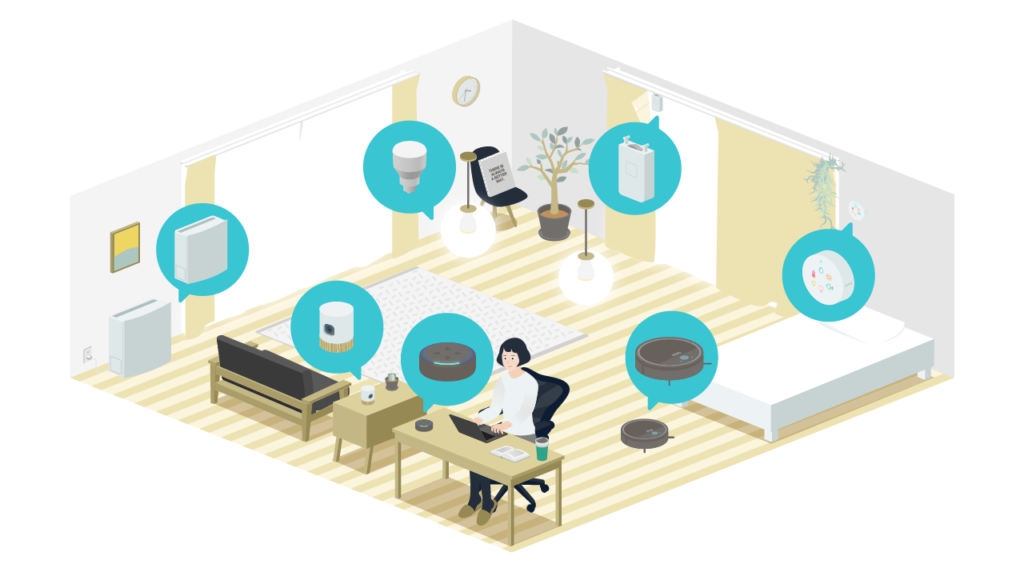
つまり美を供給する役割を担う人々の感覚は、クライアントの思惑を超えるということです。
美的感覚が自然に溢れ、要求を超えた仕事をすることがあるのです。
またそうでなければ、時代を超越するような人間にはなれません。
そこまでする必要はないと言われると、彼らは苦しいのです。
美を具体化する能力は、地位や生まれには関係ありません。
むしろもっと個人的な修練によるのです。
ではなぜ彼らはネクタイをつけようとしないのでしょうか。
自分が正業から逸脱している存在であるという自覚を持っています。
さらにいえば、その才能だけで、この世界を切り取り生き抜けるという自信の裏付けがどこかにあるのです。
それが誤った自信だということも可能でしょう。
しかし同時にだからこそ、ネクタイをせずに生き抜けるワケです。
体制に依存しない。
まさにアンデパンダンな生き方というのが、最も適当なのかもしれません。
筆者の文章を読んだ感想を、ぜひ800字にまとめてみてください。
新しい視点がひらけると思います。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


