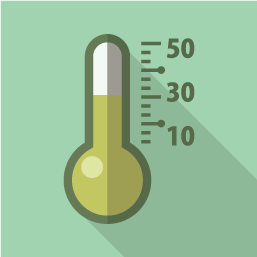紀州の路地
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は小説家、中上健次について語らせてもらいます。
もう彼の存在も随分と遠いものになりました。
彗星のようにあらわれて、あっという間にこの世を去ったのです。
今でも小説は読まれているのでしょうか。
そんな作家は知らないと言われてしまうかもしれません。
しかし厳然としたファンはいます。
彼の持つ荒くれた力はまさに紀州新宮の路地が作り出したものです。
46歳で亡くなってしまいました。
ほとばしる力を文字に託した人でした。
むさぼるように本を読んだ記憶があります。

次々と衝撃的な世界を形作っていったのです。
戦後生まれでは初の芥川賞作家でした。
1976年、『岬』で受賞しました。
和歌山県新宮市生まれ。
羽田空港などで肉体労働に従事したのち、執筆に専念します。
紀伊半島を舞台にした数々の小説を描きました。
「血族」と「路地」が彼のキーワードです。
自分の生まれた部落を「路地」と名付け、そこに広がる共同体を中心にした世界を造形していったのです。
路地は彼の内部世界にできあがった、いわば仮想的な空間です。
紀州熊野の持つ神話と路地を繋ぎ合わせて、自分だけの幻想世界をつくりあげました。
最もインパクトがあった小説は『枯木灘』です。
この小説で彼の世界は完結しました。
枯木灘
主人公は竹原秋幸。
26歳です。
土方の現場監督というところがいかにも中上健次の世界だなと思わせます。
額に汗して働く主人公を日本の作家はあまり好みません。
プロレタリア文学は別格として、それ以外の作家たちはどちらかといえば、肉体労働者を主人公にはしませんでした。
同時代の立松和平などは、そのことを中上によく指摘されたと言います。
立松和平の代表作『遠雷』はトマトハウスの栽培農家が舞台です。
しかしその労働の仕方が自分のものとは全く違うと中上は批判し続けたそうです。
枯木灘の家族関係は複雑です。
ドストエフスキーやフォークナーを連想させます。
主人公秋幸の母親フサの2番目の夫は、フサが秋幸を妊娠中に刑務所行きとなります。
ほぼ同時期に2人の女性と関係を持ち、それぞれに子をなしていたのです。
それを知ったフサは夫と絶縁。

最初の夫とのあいだにできた3人の子どもたちを置いて秋幸だけを連れ3番目の夫となる竹原繁蔵のもとに身を寄せます。
父親違いの兄はこのことを恨み続け、24歳という若さで自殺。
秋幸は自分のせいで兄が死んだという罪悪感に苛まれ続けます。
今の父親は母親の3人目の男であり、秋幸自身は2番目の男の子供なのです。
これだけで、この小説がかつて日本にあったどのジャンルにもかさならないことがわかるでしょう。
秋幸にとって最も大切なものは血です。
父親の血を嫌いながらも、その意味を問い続けます。
母の血の中には自殺者や狂人もいました。
自殺した兄と自分を重ねることもよくありました。
このようにして彼は自分自身を探し続けます。
紀州の路地に暮らすことの意味は何か。
現在の小説ではちょっと考えもつかない設定です。
逆にいえば、そこに自分の世界を設定しなければ、生にリアリティを持たせることができなかったのでしょう。
ある意味で中上が活躍した時期、多くの作家たちは完全に打ちのめされたのです。
風景の変化
日本の風景はこの数10年で大きく変わりました。
特に都市と呼ばれるところの激変ぶりはどうでしょうか。
まず駅がかわりましたね。
少し前まで、駅はどこかうさんくさいところでした。
改札口を出て、少し歩けばすぐに飲み屋街があります。
ガード下からは疲れた男達の叫び声も聞こえました。
駅そのものも汚かったです。
新宿や上野の駅はよく知っています。
現在の風景とは似ても似つかない、人を不安な気持ちにさせる場所でした。
ところが最近の劇的な変化はどうでしょう。
目を見張るものがあります。
駅そのものがファッションビルになり、さらには圧倒的な商圏になりました。
今ではだいたいのものが駅の中にあります。
それに驚くほど美しくなりました。
きれいな内装に彩られた店が軒を並べています。

おしゃれな飲食店が地下鉄の駅の中にも次から次へと出現しました。
都会の全てが覆われて、リニューアルされたのです。
日本はかわりましたね。
古いものが全て消えていきました。
路地も完全に消えました。
散歩をしようとしても古いヨーロッパのような町並みを維持してこなかったこの国には、懐かしいものがなくなりつつあります。
下町と呼ばれる場所を年老いた人々の集団が、必死に歩いている姿をよく見かけます。
浅草もかわりました。
この国にはいったい何が残ったのだろうと考えることさえあるのです。
かつてある詩人は、アスファルトを一枚めくれば、そこには赤土が堆積していることを忘れてはならないと呟きました。
しかしそんなことはもう過去の話です。
舗装された道路
土という土は全て舗装され、道路が実に快適になりました。
雨が降ってもまったく濡れずに会社までたどりつける人も多いのです。
都心へ行くと、全て地下道でつながっているところがたくさんあります。
つまり日本はそういう国になったということです。
その結果、路地を歩く楽しみは半減しました。
中上健次のような小説を書く人間は、もう出てこないでしょう。
土の匂いを身体から発散させる文学があったとしても、それが共感を覚えるものになるのかどうか。
今ではかなり疑問です。
アンダルシアやトスカーナの古い街を歩いていると感じることがたくさんあります。
とにかく彼らは道の全てをアスファルトで覆わなかったのです。
全てを覆い尽くして過去を現在にしてしまったのは、もしかしたら日本だけだったのかもしれません。
現在、どこの地方でも必死になって文化財を守ろうとしています。
それが唯一の観光資源であることに気づいたからでしょう。
京都も奈良も倉敷も、そういう努力の果てにあるのです。

路地での生活を書き続けたのは、たった1人の作家でした。
しかし彼のイメージに浮かぶような路地はありません。
あるとすれば、それはもっと整然とした、それでもないよりはいいというレベルでの場所でしょう。
それでもあるだけまだましなのかもしれません。
消えていく懐かしいスポットを、慌ててガイドブックを頼りに探さなくてはならないのです。
それがはたして幸せなことなのでしょうか。
ひりひりとした感覚で肉体に迫ってくる中上健次の持つ路地と同じものを今日探そうとしたら、それは徒労に終わるだろうと思います。
なにかもがオブラートに包まれ、実感のない日々を過ごす現代人。
死までもが今は遠ざけられつつあります。
それでも人間が生きるという営みは止まることがありません。
叫びも悲しみも当然存在するのです。
現代の路地の真実はどこにあるのでしょうか。
みなさんも少し考えてみてください。
今回も最後までおつきあいくださりありがとうございました。