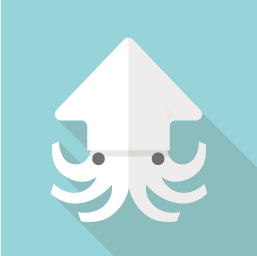板数が命
みなさん、こんにちは。
アマチュア落語家でブロガーのすい喬です。
コロナ禍で再び高座に出られなくなりました。
1月末と2月中旬の分がキャンセルになったのです。
実に残念です。
アマチュアですから生活に響くというワケじゃありません。
しかし落語をやるのが、心の張りに通じているのです。
お客様に喜んでいただき、その後で反省会と称して1杯やる。
これがなによりの楽しみでした。
それが全部消えてしまったのです。

実につまらないですね。
しかし世の中には生活に困っている人もたくさんいます。
暢気な話をしてるんじゃないよと言われれば、全くその通りです。
だからこそ静かにはしています。
しかし家の中で壁に向かって稽古をしているだけでは面白くありませんしね。
鼻から息をするものを相手にやらなくちゃいけません。
俗に板数といいます。
高座に何度あがったかが勝負なのです。
その場でお客様との間を覚えるのです。
怖い芸です。
なんていってると、幇間(たいこもち)相手に鍼の稽古をした若旦那の噺みたいで、ちょっとやりきれません。
太鼓腹という噺
ご存知ですか。
太鼓腹という落語です。
退屈でなんにも楽しみがない若旦那。
なんとか暇をつぶしたいと考えています。
たいていの遊びはやってしまったのです。
そこでふっと思い出したのが鍼。
あれを覚えてみんなを喜ばせてやろうと思ったまではいいのです。
高い道具を買い込んではみたものの、きちんと勉強するなどいう気は元々ありません。
最初は壁、次は枕。
やっぱり鼻から息をするものにしてみたい。
そばにいた猫に試みると、ひっかかれる始末です。
そこで思い出したのが幇間(ほうかん)の一八です。
男芸者のことです。

浅草にはまだ数人いるそうな。
さっそくお金の力で治療のまねごとを始めます。
そこが幇間の哀しさです。
どんなに嫌な客でも、客は客。
喜ばせてお金をもらわなくちゃ食べてはいけません。
自分を殺すのです。
若旦那、いい気になって治療を始めてはみたものの鍼が何本も折れ、幇間のお腹は血だらけになってしまいます。
とうとう若旦那は怖くなって逃げる始末。
びっくりしてお茶屋の女将が部屋を覗くと、そこには唸ってべそをかいている太鼓持ちの姿がありました。
おまえさんだってちっとはならした太鼓持ちだよ。
いくらかにはなったんだろうねと訊きます。
すると、幇間は皮が破れて鳴りませんでしたと呟くのがこの噺のオチです。
聞いたことがありますか。
太鼓持ちは女性を相手に接待するホストとはちょっと違います。
あくまでも旦那衆を相手にする芸人なのです。
そこだけはお間違いのないように。
話芸は深い
話芸といえば、講談、浪曲、落語、さらには香具師の啖呵売までとジャンルが広いです。
しかし風俗の変化で生き残るのは並大抵のことではないようです。
少し以前にはテレビでも随分寄席中継がありました。
今では「笑点」を筆頭にいくつかを残すのみです。
NHKには「日本の話芸]があります。
ちゃんとやっているのはこの番組くらいですかね。
MIグランプリなんかに比べると、実に長閑で地味な印象です。
長屋の噺も貧乏の噺も今ではメルヘンそのものなんです。

だからいいんだという考え方も当然あります。
「百川」「棒鱈」のように地方人を軽く扱った噺が生き残れるのかどうか。
「芝浜」や「子別れ」のような人情噺、あるいは遊郭を舞台にした作品、若旦那を扱ったものはどうでしょうか。
「明烏」の持つ上品な色気や、「船徳」のとぼけた味ももちろん捨てがたいです。
しかしこれからの時代にどこまで通用するでしょう。
もしかすると古典と呼ばれるジャンルの噺は次第に消えていくかもしれません。
ではその代わりに新作が残るのか。
これも全くわかりません。
亡くなった立川談志はどんな落語が現代にも受け入れられるのか、1人で悩み苦しみました。
彼の『現代落語論』を読むとよく理解できます。
本当に息苦しいほどです。
面白いと言われる落語ですら、このような状況なのです。
ましてや義理、人情が主体の講談、浪曲はもっとつらいです。
そういう意味で、神田伯山の襲名は大イベントでした。
女性の講談師の活躍も待たれるところです。
浪曲も玉川太福と玉川奈々福に頼っているだけでは先が見えません。
古今亭志ん生と小林秀雄
亡くなった小沢昭一が苦労して集めた仕事の1つに日本の放浪芸があります。
多くの音源を聞いていると、とても懐かしいですね。
しかしやはり古さを感じます。
バナナのたたき売りや、山伏や行者の恰好をしてものを売る話芸などは確かに絶品です。
しかし残念ながら今の時代には不向きです。
時間の進み方がすっかり変わってしまいました。
話の間が現在のものではありません。
話芸にじっと耳を傾けるだけの心のゆとりがなくなったのかもしれないのです。
かつては噺の巧拙を瞬時に判断する好事家がたくさんいました。
どんなに面白くてもニコリともしない常連の客の前で、噺家は鍛えられたのです。
どの寄席にも「通」と呼ばれる人がいました。
彼らは芸にはとても厳しい反面、落語家をあたたかく育て上げました。
結城昌治の『志ん生一代』を読んでいると、そうした時代のぬくもりを感じます。
酒を飲んで高座にあがり寝込んでしまう噺家を、観客は許しました。
それは彼の芸が一流だった故のことです。
古今亭志ん生の噺の間は独特なものです。
かつて、評論家小林秀雄の講演「本居宣長」を聞いたことがあります。
話し方といい、間といい、志ん生に実によく似ているので驚きました。
新潮社から小林秀雄の講演集がたくさん出ています。
学生を相手に講演した録音も残っているのです。
喋り方が志ん生そっくりです。
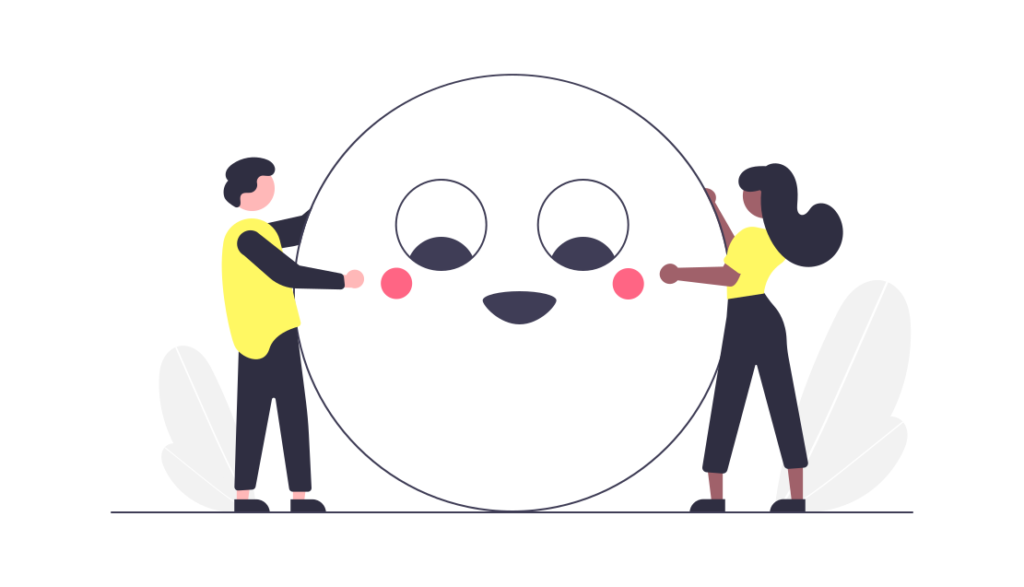
ぼやっとした口調で、これといって難しいことを続けて話しているワケではありません。
しかし含蓄があって、胸に飛び込んできます。
話というのは、内容以前のそうしたたくさんの要素に包まれているのかもしれません。
彼の評論にも似たような間があります。
しかし講演にはもっとその要素が強く滲み出ています。
志ん生と小林秀雄の接点を見た思いがしました。
難しく言えば通底するとでも言うのでしょうか。
不思議な味わいを感じたのです。
いったいどの話芸が残るのでしょうか。
難問です。
時代にあわせていかなければ取り残されます。
しかし迎合するだけなら、なおのこと生き残るのは難しいでしょう。
今回もあちこちに話が飛んでしまいました。
申し訳ありません。
最後までお読みいただきありがとうございました。