チャットGPT時代の小論文
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今年に入って生成AIに関する記事を何本か書きました。
昨年末に発表されてから、瞬く間に世界を席巻した「チャットGPT」関連の文章です。
今や、似たようなアルゴリズムを使った生成AIが次々と誕生しています。
乗り遅れたら負けというのが実感ですね。
教育の世界も全く同様です。
先端的な学校では、さっそく生徒用のタブレットなどを使って、授業に応用しています。
いくつかのキーワードから出来上がった文章をチェックし、さらに高度で論理的なものに昇華させる実験なども試みています。

その結果、何が生成AIにはできないのかという、デメリットについての判断も試みているのです。
長い間、小論文の添削をしてきた経験からいえば、怖ろしい外敵が生まれたなというのが、正直な実感です。
「てにをは」などの助詞をどう使いこなすかといった、非常に大切で、基本的な内容は、かなりこなすのではないでしょうか。
文章は助詞1つで大きく変化します。
しかしチャットGPTはかなりの確率で、うまく添削してみせる力量を持ちえていると感じます。
生成AIを支えているのは、データの総量以外にはありません。
彼らは正解か不正解かを知らないのです。
たくさんのデータの中から、最も総数の多い内容をより重視します。
多くの人が集中的に検索し、インプットする情報こそが、もっとも価値あるものなのです。
逆にいえば、知らないことには全く解答ができません。
彼らの想像力はその程度のものだとも言えます。
創造力との戦い
彼らがまだ世の中に姿をあらわしてから1年も過ぎていません。
その間に多くの人がどれだけの情報をインプットしたのか。
その結果が、現在も日々抽出されています。
一言でいえば、それほどに決定的で革新的な内容の意見は出てきてはいないのです。
ただしだからといって、これから先のことを簡単に侮ってはいけません。
彼らは疲れることを知りません。
ただひたすらデータを蓄積していく作業を続けています。
今年の小論文の入試問題に、生成AIの問題が出るのは確実です。
しかしどのような形で提出されるのか。
これは大きな問題ですね。
最も早い段階で小論文を入試に導入したのは、慶応大学のSFCでした。
もともと、インターネットの専門家を多く擁し、活用を推進した学部なのです。
当然、このテーマに着目しないワケがありません。
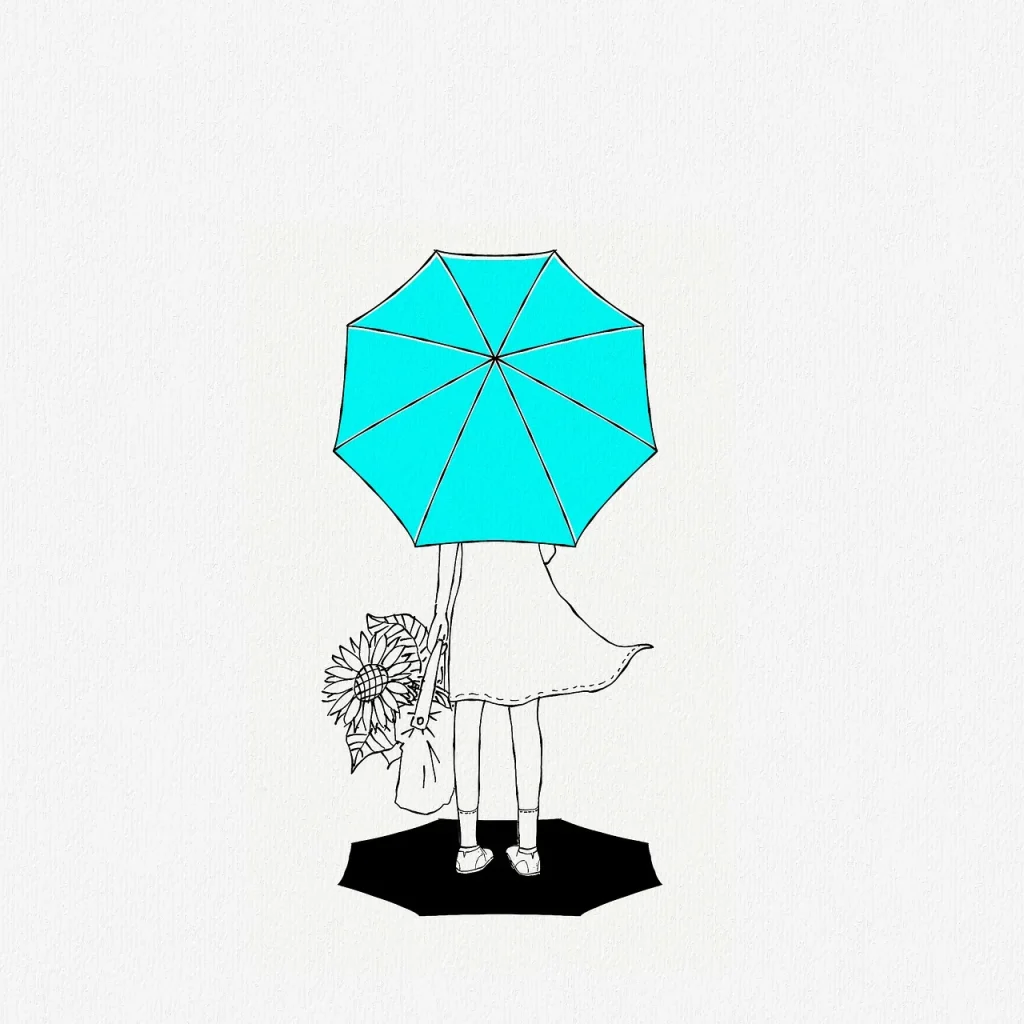
試験を担当する教授たちが、なんとかしてこのテーマを使い、先端的な入試問題を作成してみたいとする気持ちが、よくわかります。
長文が多いことは、過去問をみればすぐにわかります。
詳しく知りたければ、代々木ゼミナールが毎年改訂している『新小論文ノート』に全て網羅されています。
是非、チェックしてください。
人文系も社会科学系も、基本的に過激な発言は求めていません。
ことに人文系は独創的な視点に基づいた解答を、要求してきます。
受験生の精神的な幅の広さと深さを、その場で確認するための問題が出題されるのです。
いわゆる常識的な解答は高く評価されません。
生成AIを使って、このような解答例が出せるものでしょうか。
あるいは既存の内容から、その場で修正させるようなタイプの問題も考えられます。
あらゆる方向から推測する必要があるのです。
良い子の作文はNG
あなたはチャットGPTで検索をしてみたことがありますか。
これは必ず試みてみてください。
時代のテーマである「SDGs」とはなにかを訊ねてみれば、そのレベルがよくわかります。
一言でいえば、教科書の文章そのものです。
どこにも破綻がない。
文句のつけようがないのです。
この検索結果をあなたが採点者だとしたら、どう評価するのか。
よくもない、悪くもない。
ごく平均的で面白味のない文章だと感じるはずです。
もし、原文をコピぺして提出したら、不合格になるでしょうね。
なぜかわかりますか。
入試の試験は何が正解かを求めているワケではありません。
もちろん、トンチンカンな答えでは意味がないのは当然です。
そうではなくて、あなたがそのテーマをどれほど自分自身の問題として、実感し、把握しているのかを採点者に感じさせなければならないのです。
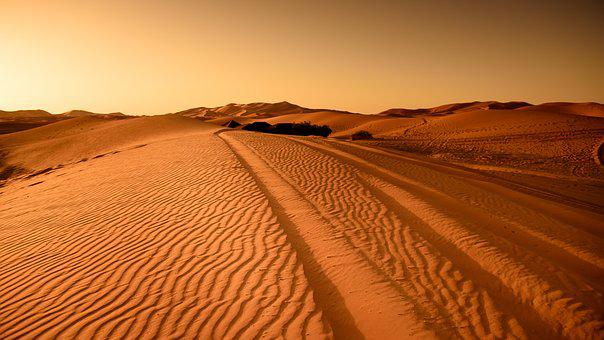
SDGsと簡単にいいますが、その捉え方は確実に変化しています。
世界の情勢も数年前と同じではありません。
貧困、飢餓、気候変動と言葉にしてみれば、内容は似ていても、提出された当初とは明らかに内容が動いています。
世界の動きも大きく変化しているのです。
2030年までに達成するはずだった目標も、確実にずれ込んでいます。
なぜか。
そこには多くの理由があるのです。
その時代の変化を確実に感じ取っているか。
入試では、それを自分の問題にしているかが、問われているのです。
評論家のようなあたりさわりのない文章では、NGです。
合格答案にはなりません。
見聞と知識が必要
試しにチャットGPTを使ってみてください。
小論文の過去問のテーマを打ち込んでみれば、その実力がよくわかります。
今年、入試問題をつくる担当者たちは、必ず生成AIを使って、解答例をいくつもつくるでしょう。
そしてこのパターンの答案は、評価しないと事前の会議で決めるはずです。
解答例をつくり上げるのは、それほどに難しい作業ではないのです。
数日もあれば、かなりの文例が出来上がってきます。
その中に、独創的なものがどの程度あるのか。
残念ながら、今の生成AIにそれだけの力量はありません。
同じ内容のものを言い換えて、別の形にして提出するのは得意です。
データの総量が脳に蓄積されているからです。
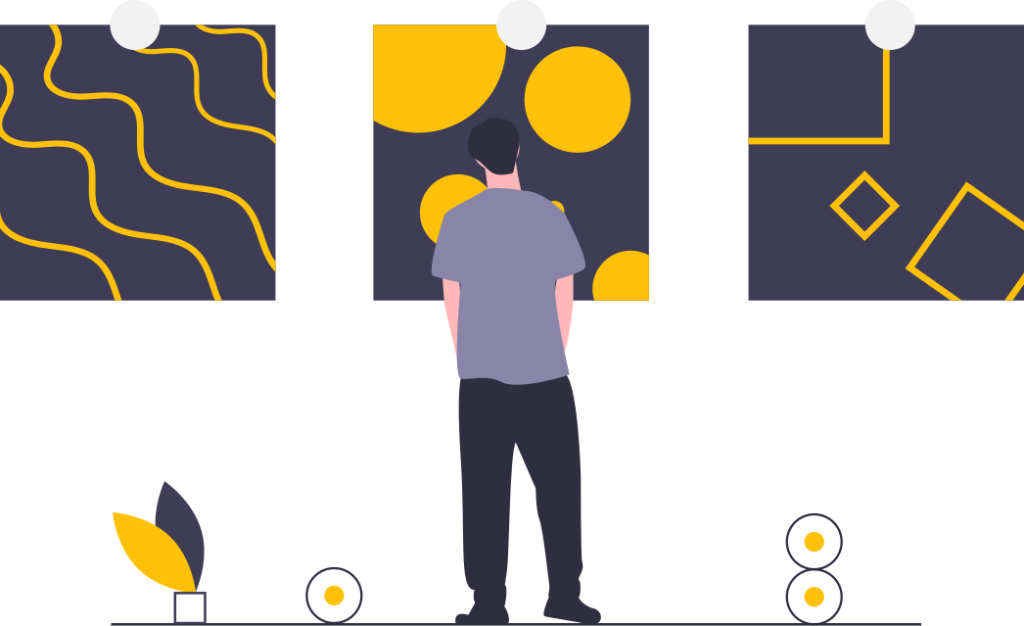
しかしそこに新しい視点があるのかどうか。
時代の空気感や、人々の意識の微妙な変化を捉えきれるのか。
それは現段階では無理でしょうね。
あまりいい表現ではありませんが、横丁の隠居のような少しかび臭い言葉が羅列されているだけなのです。
当然といえば、当然のことです。
そうしたデータが、多くの人によって検索され続けているという事実が背後にあるからです。
あなたが、本当に勝ちたいのならば、やはり知識を獲得し続けるしかありません。
歴史も大切です。
しかしその歴史は角度をかえてみた、あなたにとっての新しい歴史でなければなりません。
そのためには継続した学習が必要です。
最後はこの結論以外に道はないと信じます。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。



